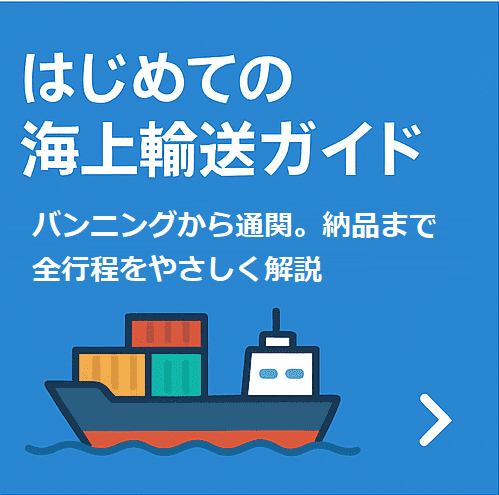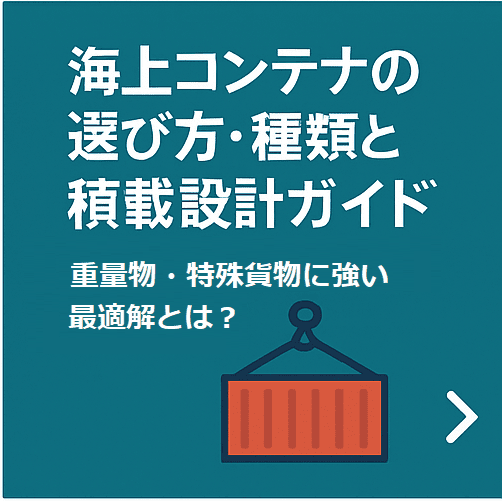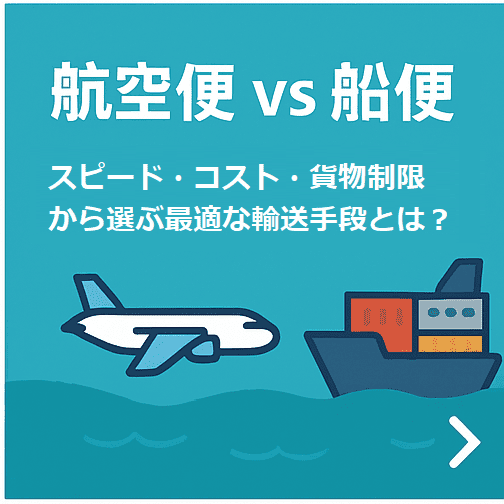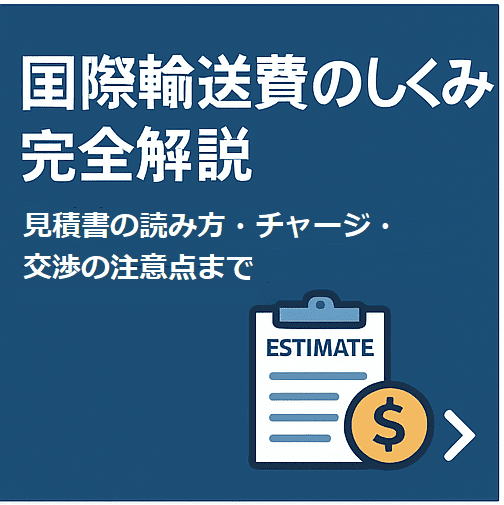「CTRL」+「D」を押すと、HUNADEをブックマークできます!
航空輸送の基礎|海上輸送との違い+実務リスクまで初心者向けに整理する
航空輸送は「早く届けたい」「小口で扱いたい」という場面で力を発揮します。
しかし、速さだけで判断すると費用や責任範囲の理解が追いつかず、後でトラブルになることがあります。特に会社で初めて航空輸送を担当する場合は、仕組み・運賃・責任範囲・保険・搭載制限(ULD) を基礎段階で押さえておく必要があります。
ここでは、初心者がつまずきやすい点をやさしい言葉でまとめ、実務判断に必要な要素まで含めて整理します。
航空輸送はどんな時に向いているのか
航空輸送の強みは「速さ」「取り扱いのしやすさ」です。ただし、高価な貨物や壊れやすい商品を運ぶ場合は、早さだけで決めるのではなく、保険付保が必要かどうかも合わせて判断します。
代表的に向いているケースは次のとおりです。
- 欠品を避けたい緊急出荷
- 展示会・工事など、日時が決まっている案件
- 高価で小口の精密機器(→ 保険必須)
- 賞味期限の短い食品や生鮮品
「早いから安心」ではなく、リスク(破損・盗難・遅延)に対して保険を付けるかどうかを必ず検討します。
海上輸送との違い|初心者がまず押さえる6つの視点
航空と海上の違いは多いですが、初担当者は次の6点を理解すれば十分です。
1. スピード
航空は1〜3日、海上は数日〜数週間。納期が固定されている案件は航空が有利です。
2. 価格
航空は速い分だけ高額です。特に軽くても大きい貨物は、容積重量で料金が跳ね上がります。
3. 重量・大きさの制限(ULDの概念)
航空は搭載に使うULD(Unit Load Device)という専用コンテナに入る大きさが基本条件です。大きすぎる貨物は搭載できません。
- 代表的ULD(AKE)サイズ:おおむね L155×W153×H163cm 程度
- 重量制限:1ULDあたり 約1,500kg前後 が目安
ULD制限を知らずに予約すると「搭載不可」が発生し、貨物が動きません。
4. フライト頻度
航空は便数が多く、小口でもスケジュール調整がしやすいのが強みです。
5. 保管環境
航空はリードタイムが短いので温度変化が少なく、食品や高価品に向きます。
6. 書類(MAWB/HAWB)の存在
航空には、航空会社用(MAWB)と荷主用(HAWB)の2種類があります。詳細は出荷手順ページで説明します。
ここまでで航空と海上の違いを整理しました。次に、実際に費用見積りや契約交渉で欠かせない「費用負担と責任範囲の考え方(インコタームズ)」を確認しておきましょう。
料金と責任に関わる「インコタームズ」の基礎
航空輸送の費用を理解するには、費用負担と輸送範囲を示すインコタームズの基礎を知る必要があります。
代表例:
- EXW:輸出側の工場渡し。そこから先は買主負担。
- FOB:航空には厳密には使わないが、海上では「輸出港まで売主負担」。
- FCA:航空ではこれを使う。指定場所まで売主負担。
- DAP / DDP:指定地まで売主が手配(DDPは関税も含む)。
航空運賃が「高い」「安い」だけでは不十分で、どこまでが売主負担かを示すインコタームズが費用と責任の前提です。
費用負担の基本を押さえたところで、次は「実際にトラブルが起こった場合、誰がどこまで責任を負うのか」を見てみましょう。
航空輸送の責任範囲|損害が出たとき誰が責任を負う?
初心者が最も見落としやすいのが「責任範囲の理解」です。
航空輸送の責任はモントリオール条約に基づいており、航空会社が賠償する場合の限度額は次のように決まっています。
航空会社の賠償限度額
22SDR/kg(特別引出権)
※1SDR=世界通貨のような単位。おおむね150円前後で変動。
例:100kgの貨物なら、航空会社の賠償上限は 約33万円 程度。
高価な商品の場合、これでは大きく不足するため、航空会社の賠償だけではカバーできません。
フォワーダーの責任
フォワーダーは運送契約の一部で責任を負う場合がありますが、航空会社と同等ではありません。書類(MAWB/HAWB)の内容が判断材料になります。

航空会社の賠償には上限があるため、高価な貨物を守るには別の手段が必要になります。それが「貨物保険」です。
高価品には「貨物保険」が必須
航空が速くても、破損・盗難・遅延のリスクはゼロではありません。特に高価品や精密機器は、貨物保険を付けることが実務の必須作業です。
貨物保険の基礎
- 付保額:貨物価額+輸送費+10%が一般的
- 付保タイミング:出荷前
- 手続き:フォワーダーまたは保険会社へ依頼
保険なしで高額品を航空輸送するのは大きなリスクです。費用や保険の基礎を理解したら、次は実際にどのような手順で貨物が動くのかを全体の流れで確認しましょう。
航空輸送の流れ(ざっくり理解)
航空輸送は次の順で進みます。
- 予約
- 集荷
- 保税地域へ搬入
- 輸出通関
- ULDへの搭載作業
- フライト
- 到着後の輸入通関→引き取り
この流れを理解すると、次の記事の「出荷手順」がスムーズに読めます。
初心者が誤解しやすいポイント
- 航空=必ず速い、とは限らない
- 壊れにくい貨物でも梱包は必須
- 費用は重量だけでなく容積重量でも変わる
- インコタームズを理解していないと費用トラブルが起きる
- ULD制限を理解していないと搭載不可が発生する
- 賠償は22SDR/kgが限度。高価品は保険必須
【KS/RA制度】航空貨物の新規制で小規模荷主が困る?今すぐ知るべき対応策!
FedExの料金が高い理由|費用が跳ね上がる“本当の原因”と安くする実務策
次に読むべき記事:航空輸送の出荷手順
航空輸送を実務として理解するには、次のステップが必要です。
- MAWB/HAWBの関係
- 出荷の具体的流れ
- 重量計算(実重量・容積重量・課金重量)
これらは次の記事で詳しく解説しています。
航空輸送の出荷手順|MAWB/HAWB・重量計算をわかりやすく整理
見積りを取りたい方へ
航空輸送の費用は、貨物の「大きさ・重さ・品目・出発地と到着地」で大きく変わります。4項目だけで最適ルートの提案が可能です。
要点まとめ
- 航空輸送は速いが、費用と責任範囲の理解が必須
- ULDの搭載制限によって出荷可否が決まる
- 航空会社の賠償は22SDR/kg。高価品は保険必須
- インコタームズが費用負担の前提になる
- 次は「出荷手順」で実務全体を理解できる

 この記事を登録
この記事を登録
 目次
目次