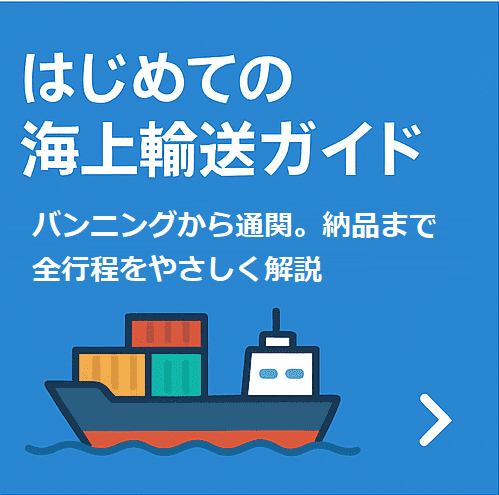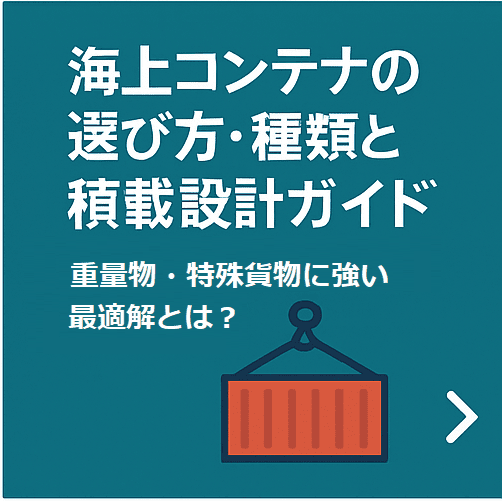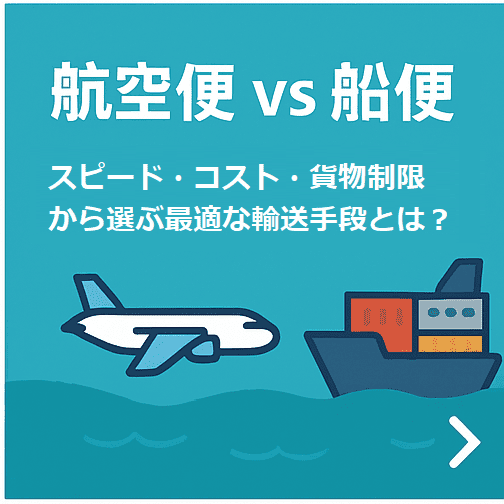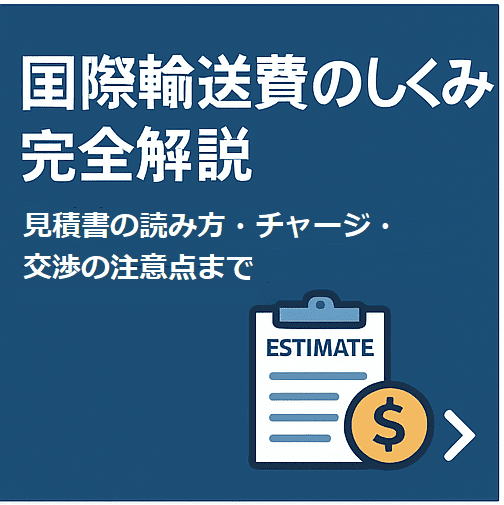「CTRL」+「D」を押すと、HUNADEをブックマークできます!
みなし輸出とは(企業・大学担当者向けの完全ガイド)
なぜ今「みなし輸出」が注目されている?
日本企業では外国人労働者、特に技能実習生や特定技能人材の受け入れが急増しています。この動きに伴い、製造現場や研究現場での「技術の教え方」や「データ共有の仕方」が、知らないうちに外為法上の『みなし輸出』に該当するケースが増えています。
つまり、海外に“モノ”を出していなくても、国内で外国人に技術を伝えた時点で輸出と同じ扱いになるのです。2022年の外為法改正により、その範囲が明確化され、大学・研究機関・中小企業の現場担当者まで管理対象が広がっています。
みなし輸出の基本
「みなし輸出」とは、日本国内で外国人や外国法人に対して輸出規制技術を提供する行為を指します。これは、実際に物を海外へ送らなくても、情報が国外に流出する危険があるため、法律上「輸出と同じ」とみなされます。
対象となるのは「技術」や「情報」であり、次のような行為が該当します。
- 外国人社員に設計図や製造ノウハウを説明する
- 留学生に研究データを渡す
- 海外親会社のサーバーへ研究資料をアップロードする
- 外国籍の派遣社員に製造装置の操作方法を教える
これらは、外為法(外国為替及び外国貿易法)に基づき規制されています。
居住者・非居住者の定義(最重要ポイント)
みなし輸出の該当可否を判断する上で最初に確認すべきは、「居住者」か「非居住者」かです。外為法では、国籍ではなく滞在期間で判断されます。
- 原則として、「日本国内に6か月以上滞在している個人」は「居住者」とされます。
- 一方、「6か月未満の滞在者」や「海外法人に雇用されている者」は「非居住者」です。
- 「非居住者」とみなされる者(例:海外企業の派遣で来日している社員など)は、滞在期間にかかわらず規制対象です。
実務ポイント: 外国人社員が入社から6か月経過しているかどうかは、みなし輸出判定の第一ステップです。採用・派遣・受入れの時点で、この区分を明確にしておくことが不可欠です。
技能実習生・特定技能人材に関する見落とし事例
近年、技能実習生や特定技能の受入企業で「知らずにみなし輸出に該当していた」事例が増えています。典型的な3パターンを挙げます。
1.技術指導による無意識の技術提供
製造ラインの設定値、金型寸法、材料配合、CADデータなどを指導時に共有している場合、これは「技術提供」に該当します。技能実習生の多くは非居住者扱いのため、経産省の許可なしに提供すれば外為法違反になるおそれがあります。
2.クラウド共有による情報流出
実習マニュアルや装置設定データをGoogle DriveやDropboxなどで共有し、海外からアクセス可能な状態にしている場合、電子的技術提供に該当します。アクセス権限管理の甘さが原因で違反リスクが高まります。
3.受入契約上の誤解
「監理団体を通しているから自社の責任ではない」と誤認して誓約書を取らないケースがありますが、実際には技術提供を行う側にも管理義務があります。契約書に責任分担を明記することが必要です。

対応策: 受入前に居住者判定を行い、技術内容を棚卸し、アクセス制限と誓約書取得を徹底。監理団体との責任分担を文書化します。
リスト規制技術とキャッチオール規制技術の区別
技術が規制対象となるかを判断するには、以下の2段階で確認します。
- リスト規制技術:軍事転用性の高い特定の技術(例:高性能センサー、暗号技術など)で、提供前に必ず経産省の許可が必要。
- キャッチオール規制技術:リストに明示されていなくても、提供先や利用目的によって規制される技術。特に懸念国や特定用途(兵器開発など)に関わる場合に該当します。
実務では、まず「リスト規制」に該当するかを確認し、該当しなければ次に「キャッチオール規制」(客観要件・インフォーム要件)に抵触しないかを判断します。この二段階判定を社内手順書に明記しておくと、担当者の判断が標準化できます。
クラウド利用時のリスクと対応策
現代の企業では、SaaSやクラウドストレージを使った情報共有が一般的です。しかし、これが「電子的な技術提供」とみなされるケースが増えています。
該当リスク
海外拠点や外国籍社員がアクセス可能な状態で技術情報をクラウドに保存すると、物理的なサーバーの場所にかかわらず「国外への提供」とみなされるおそれがあります。
実務対応策
- アクセス制御(IPアドレス制限・国別ブロック)
- 多要素認証やアクセスログ管理
- 外国籍社員・海外拠点向けには閲覧制限つきのフォルダ構成
これらの措置を講じることで、技術情報の不正流出リスクを大幅に減らすことができます。
誓約書の意義と実務での使い方
外国人社員・留学生を受け入れる際は、「みなし輸出規制誓約書」を取り交わすことが求められます。これは、技術や情報を正しく扱うことを本人に誓約させるための文書です。主な目的は以下の3つです。
- 提供される情報を社外や第三者に渡さない。
- 海外持ち出しや再提供を禁止する
- 離職・帰国後も秘密保持を続ける
誓約書は採用時・派遣受入時・研究参加時など、アクセス権が発生する段階で必ず取り交わします。特に大学では、留学生・共同研究者の参加前に実施する必要があります。
企業・大学での管理フロー
- 技術内容の棚卸し
- 対象者(国籍・在留資格・所属)の確認
- 該当判定(特定類型の識別)
- 必要に応じ経済産業省への許可申請
- 誓約書の取得と保存
- 定期的な教育と更新
この流れを年1回の監査・教育サイクルで維持することがお勧めです。
よくある誤解と注意点
- 「学生や派遣社員は対象外」→ 誤り。国籍・雇用元・滞在期間で判断する。
- 「モノを輸出していないから関係ない」→ 誤り。技術提供も輸出扱い。
- 「日本法人内の共有なら安全」→ 誤り。外国籍社員への提供は該当し得る。
罰則と違反リスク
外為法に違反すると、個人は最高5年の懲役または500万円以下の罰金、法人は1億円以下の罰金が科される可能性があります。また、企業としての信用や取引資格を失うリスクもあります。
国際比較:米国EAR・中国制度との違い(簡潔に)
- 米国(EAR)では、国内で外国人に技術を伝える行為を“deemed export”と呼び、日本と同様に規制されています。
- 中国の「みなし輸出入」は税務・物流区画での制度用語であり、技術提供の概念とは異なります。
よくある質問(Q&A)
- Q:みなし輸出はいつから厳しくなった?
A:2022年の外為法改正で定義と管理対象が明確化されました。 - Q:非居住者の判断基準は?
A:滞在期間6か月未満または海外法人所属が原則です。 - Q:派遣社員にも誓約書が必要?
A:はい。受入先で技術に触れる可能性がある場合は必須です。
まとめ
- 「みなし輸出」は国内でも適用される輸出管理制度。
- 判断基準は「居住者・非居住者」の区別から始まる。
- 技術はリスト規制・キャッチオール規制の二段階で判定。
- クラウド利用にも注意し、アクセス制御を徹底。
- 採用・研究・派遣など外国籍者にアクセスが生じる場面では誓約書が必要。
- 年1回の棚卸し・教育・誓約更新でリスクを防止する。

 この記事を登録
この記事を登録
 目次
目次