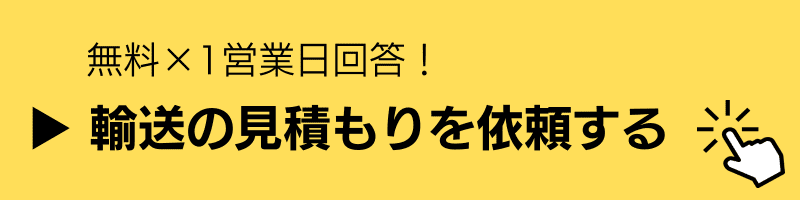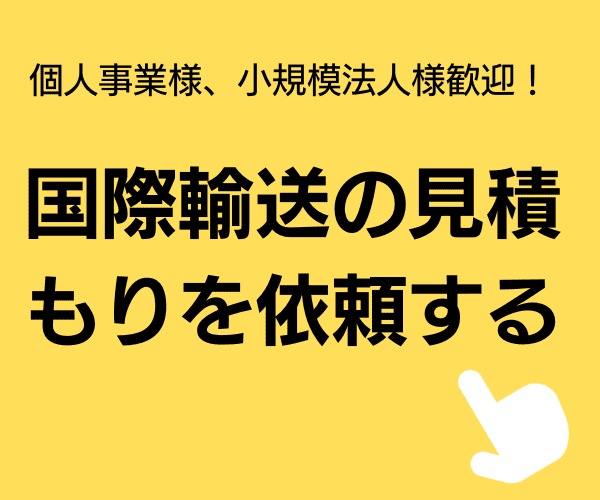| 種別 | 積み地 | 揚げ地 | 品目 | 輸送モード |
| 法人 | 東京 | ドバイ | 盆栽 | 相談希望 |
| 法人 | バンコク | 名古屋 | 生鮮果実 | リーファー |
| 法人 | 東京 | ドバイ | 盆栽 | 相談希望 |
| 法人 | バンコク | 名古屋 | 生鮮果実 | リーファー |
昨今、加工貿易をする上での原材料の到着が遅れ、工場の生産に空白期間が生じていることを耳にしませんか? もしかすると、すでに体験している方もいらっしゃるでしょう。
今回は、海外生産のデメリットついて、アパレル製品を例にとり、その原因を考察していきます。
加工貿易のデメリット 生産遅延が起きる理由
1:原材料その物の生産遅れ
原材料はその生産国(例えば中国やその他第三国)で生産されるのが殆どです。
例えば、廃ペットボトルを使用した再生繊維等が繊維に再加工されて、再度生地に仕立て直され、それがポリエステル素材の織物や編み物などの生地になり、所謂アパレル製品の原料となるケースが増えてきました。
所が、折からの海上コンテナ不足から、廃ペットボトル原料を輸送する海上コンテナが不足してしまったり、急激な海上運賃高騰により、契約金額ではペットボトル等の原材料を製糸原料生産メーカーへの供給できなくなったりしています。
結果、製糸工場には原料不足が生じ、製糸メーカー→生地メーカー→縫製メーカーなど、ドミノ倒しのように完成品の生産が滞る事態になっています。
2:生産ラインに空白期間が発生する
前途の様に、国際物流費等の値上がりなど諸所の理由から、各原材料の生産数は大きく下がっています。原材料が少なくなれば、それを使い完成品を作る工場で働く人たちも不要になってきます。
例えば、原材料を輸入し、完成品を輸出する「加工貿易」をする場合は、原材料の調達とそこで働く人たちの「雇用維持」の2つを考える必要があります。
- 安定的に原材料を調達する。
- 工場で働く人の雇用を維持する。
現在は、上記2つが非常に不安定になっているため、工場の生産活動に「空白」が生じ、結果、様々な商品(原材料)の生産数が下がっています。
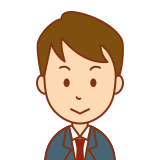
必要なときに必要な分だけ供給することが難しくなっている
3:商材の完成が遅れ船積みが遅れる
当然、機械化が進んでいない国の工場は、生産活動の多くの場面で、人の力に頼っているため、人員の削減は、より生産活動の減少に直結します。
例えば、少しくらい生産活動を改善したとしても、人員の減少を補うほど、生産効率を上げるのは難しいです。結局、工場で生産できる数量が不足し、海上コンテナなの船積みにも影響がでてきます。
ご存知の通り、海上輸送は、一度にできるだけ多くの貨物を輸送し、製品にかかる輸送費を下げられる点が魅力です。しかし、ある一定の期間内に一定の生産ができない現状では、どうしても「細切れに輸送」する必要がでてきます。
本来であれば、契約数量を全量一括で輸送できるのに、生産数が上がらないため、できた分から、一定量ずつ、複数回、輸送しているのですね! 当然、輸送回数が多くなるほど、あわせるように、商品価格も上昇してしまいます。
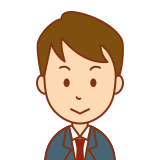
本来は、一回の輸送で済む物量であるのに、工場で働く人や原材料の不足により中々、生産ができないので細切れで輸送する必要がある。=商品代金が上昇する。
- 原材料が不足している。
- 完成品を生産する工場は、原材料がないから生産ができない。
- 生産ができないから、工場人員を減らす。
- 工場人員が少ないので生産数が落ちる。
- 生産数が落ちるから、できた分から細切れで発送するようになる。
- 細切れで発送するから、商品にかかる物流費が大きくなる。
- 結果、商品代金が上昇する。
このように、ワーカーの人件費高騰、コンテナ不足による運賃高騰が、産品価格の高騰にも直結する状況です。
特に最近は、海上運賃高騰化により、思った様に利益が出ない第三国メーカーが、受注出来る数量を減らすケースも散見されます。又、ワーカーを無理に解雇した事による労働運動等が発生し、その結果、メーカーが操業不能な状況に陥る事もあり得ます。
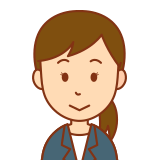
出来上がった製品の総量は減少する、及び納入期日が遅れる、最悪、輸入する事もままならない等、市場の要求に見合わない状況になってきています!
4:海上輸送ではなく航空輸送を使用せざるを得なくなる
例えば、日本側で行われるコンサートグッズ(Tシャツなど)を第三国に加工貿易委託をしている場合、コンサートの日に日本に到着させることが難しくなり、ぎりぎりのタイミングで、飛行機便での輸送も多いです。(当然、海上輸送から航空輸送に切り替えれば、国際輸送費は非常に高いです)
とはいえ、荷物の遅延は、ときに重大な損害賠償責任へとつながることもあるため、損をすると知りながらも、航空輸送を選ぶことがあります。
例えば、コンサートグッズの場合なら、コンサートの当日にグッズがあることが絶対的な条件です。
コンサートの当日、あるべきものがないから儲けるチャンスを逃した。だから、この責任は、売り手にとってもらう。
つまり、遅延喪失等の責任を取らされるケースが増えています。もちろん、このようなケースは、コンサート商品以外にも発生していることに留意します。
5:商策上の信用に関わる事も
昨今、小口個人輸入を行い大手ECサイトで販売する商流が盛んです。この生産~貿易遅延の問題で、エンドユーザーへの納入が遅れ、窓口である大手ECサイトに注文を入れた個人ユーザーから大手ECサイトに多大なクレームが入るケースがあります。
結果、売主のアカウントへ警告が入り、最悪のケースではアカウント停止などの措置を取られるケースが多々発生しています。販路を失うばかりか、市場からの信用を失くす事にも繋がります。
その他、大手アパレル販売店舗への卸販売などを手掛けていると、その販売店舗が入荷する事を前提に、事前に販売用のチラシなどが発行されて、不特定多数のユーザーがその商品を待っていることもあります。このようなユーザーが実店舗を訪れ、目的の商品が欠品している時に、どのような事になるのかは想像に難しくありません。
となると、購買契約の打ち切り等、生産遅延、物流遅延の結果、多大な販売損失を招く可能性があります。その後、市場での信用を再構築する為にはブランディング等にコストや時間を掛け直す必要が生じてしまいますし、致命的なダメージを負う事もあり得ます。
6:まとめ
1:例えば第三国メーカーとの年間購買数量を契約で縛ることで、リスクヘッジを行う事。原材料を供給するケースの場合は、原材料メーカーと年間購買数量契約を結び、投入数量の前提を固める事。とはいえ、現実問題として原料調達が難しい時代あることは否めません。その遅延が発生した際の何手か先のリスクについて常に情報収集を行う事が大事です。
2:第三国メーカーとて、人手不足である事から、余裕を持った生産スケジュールを組める様に最初の受注の段階から、メーカーのコンディションなどを勘案し、完成品供給→納入までの期間の契約を行う必要がある。
3:委託生産先のメーカーを選定する際は、生産価格もさる事ながら、余裕を持ったライン構成を持っているメーカーに発注する事が大事です。
4:ここまでの1-3までの事を疎かにする、または産品価格だけでメーカーを選定すると、最終的に、しわ寄せが物流費に跳ね返ってきてしまいます。どう考えても海上輸送一括輸送よりも、航空便での分割輸送が高くついてしまう事は否めません。それを避ける為には、余裕を持った生産計画や貿易契約を組むことがとても大事なファクターです。
5:この様な信用不振を市場で招いてしまうと、再起する事はかなりのコストや時間を要します。そうならない為には、ある程度の国内在庫を確保して行く事、その後のバックオーダーを見越して需要の流動波動性等を把握した、生産物流計画を作成する事が大変重要となります。その為には、普段から実生産メーカーとの密な関係性、フォワーダーとの情報交換などが肝要になります。
その他:実は遅延損失については基本的に貿易保険でもカバーしきれないケースが多く存在します。その為、貿易保険会社との契約を行い、その際に基本的な契約条項において遅延損失に着いいてどの様なサービスがあるかを事前に確認し、その保険会社の営業マンとの関係性を深めておく事も大変重要ですね。

 この記事を登録
この記事を登録



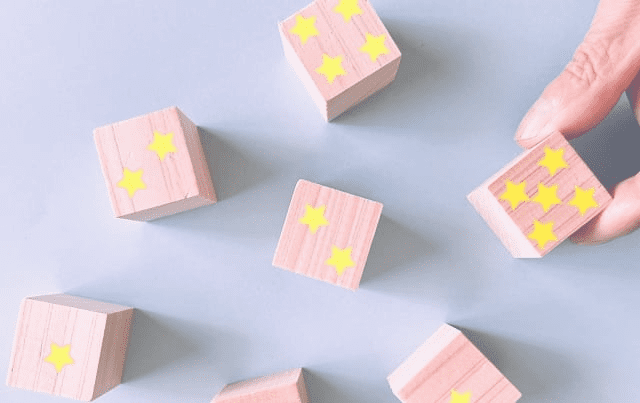
 目次
目次