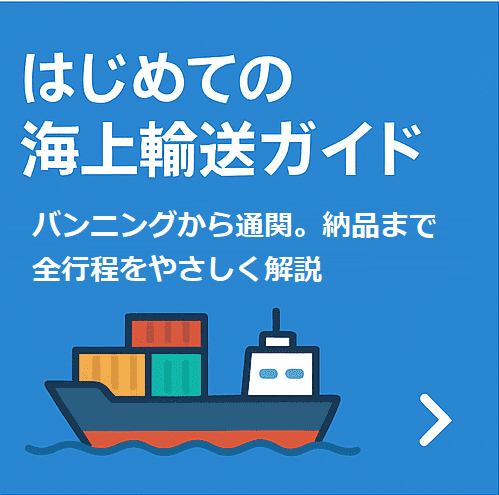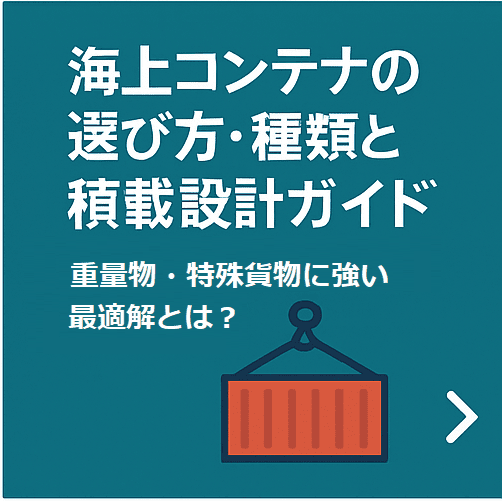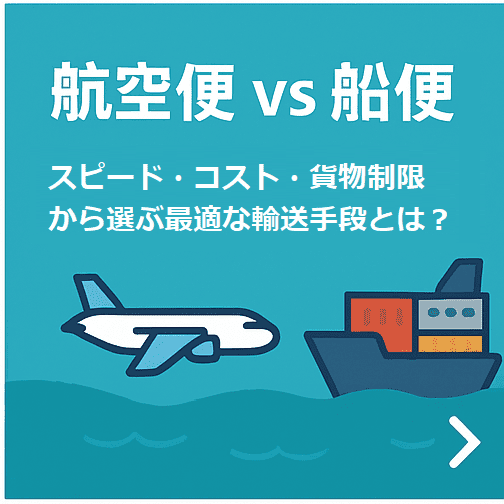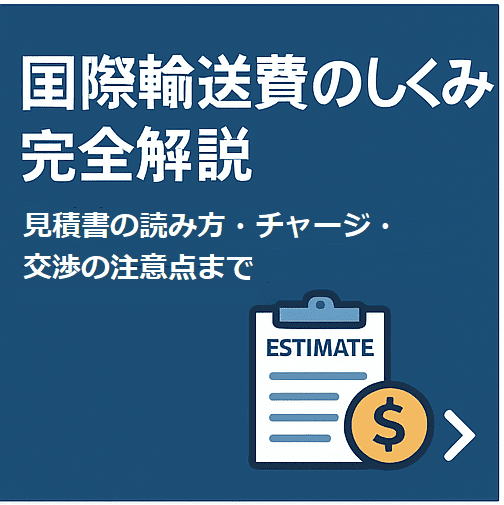「CTRL」+「D」を押すと、HUNADEをブックマークできます!
危険物クラス別ガイド|Class2・3・4・5・8・9の実務ポイント
危険物の国際海上輸送では、貨物がどの「クラス(Class)」に分類されるかが、輸送可否、必要書類、包装、隔離(Segregation)などすべての判断の出発点になります。
この記事では、IMDGコードに基づき、特に取扱い頻度が高い Class2・3・4・5・8・9 を中心に、実務担当者が誤りやすいポイントを整理します。クラス分類は、UN番号・PSN(正しい船積み品名)と密接に関係するため、実務上は必ずペアで確認する必要があります。
まずは、危険物全体がどのような仕組みで分類されているのかを俯瞰してみましょう。分類の全体像を理解しておくと、後の各クラスの特徴がより明確になります。
クラス分類の全体像(Class1〜9)
危険物は以下の9クラスに分類され、それぞれの危険性に応じて輸送規制が大きく異なります。
- Class1:火薬類
- Class2:ガス類
- Class3:引火性液体
- Class4:可燃性固体等(4.1/4.2/4.3)
- Class5:酸化性物質および有機過酸化物
- Class6:毒物類
- Class7:放射性物質
- Class8:腐食性物質
- Class9:その他の危険物
特に Class3・Class8・Class9 は一般貨物に紛れて輸送されることが多く、船会社の審査も厳しめです。
Class 2(高圧ガス)
Class2 はガス類で、圧力管理と温度変化に対する注意が最重要です。2.1(可燃性)、2.2(非可燃性・非毒性)、2.3(毒性ガス)に分かれています。Class 2 は 2.1(可燃性)、2.2(非可燃性・非毒性)、2.3(毒性ガス)に分かれます。特に 2.3 は輸送制限が非常に厳しく、多くの船会社が受け入れを拒否します。輸送可否の判断は事前照会が必須です。
代表品目
- LPG
- Aerosols(エアゾール)
- Refrigerant gases(冷媒ガス)
実務ポイント
- 温度上昇で内部圧力が急上昇 → 膨張対策必須
- 容器の UN 試験(耐圧・落下など)を必ず満たす必要あり
- Class3(引火性液体)との混載は厳しい制限
Class 3(引火性液体)
最も取扱いが多く、事故も最も多いクラス。引火点が規制の基準になります。
代表品目
- Ethanol
- Paint / Thinner
- Acetone(※Class3が正しい)
実務ポイント
- 温度管理が重要(特に夏場のCY保管)
- Class5(酸化性)との混載は厳禁
- 船会社の承認に時間がかかるケースが多い
次は、液体ではなく固体に分類される危険物を見てみましょう。Class4は液体とは異なる反応性や取り扱い上の注意点があります。
Class 4(可燃性固体)
Class4 は固体の自発発火や水反応による危険が特徴。
- 4.1:可燃性固体
- 4.2:自然発火性物質
- 4.3:水反応物質
代表品目
- Metal powder
- Phosphorus
実務ポイント
- 4.3 は湿気厳禁、結露でも反応の危険
- 通気性・水濡れ管理が輸送可否に直結
Class 5(酸化性物質)
Class5 は「他の可燃物を燃えやすくする」という特徴があります。
代表品目
- Ammonium Nitrate
- Hydrogen Peroxide
実務ポイント
- Class3・Class4 との混載禁止
- 容器は耐薬品性の高い材質が必須
- 船会社の審査が厳しめ(酸化剤事故が多いため)
Class6(毒物)やClass7(放射性物質)は特殊輸送に限定されるため、ここではより実務頻度の高いClass8へ進みます。
Class 8(腐食性物質)
液体危険物で最も多いカテゴリ。コンテナや金属部材への腐食事故に直結します。鉛蓄電池の電解液(硫酸)は典型的な Class 8 ですが、リチウム電池の液漏れも腐食性の性質を持つ場合があります。そのため、電池関連貨物では SDS の確認が必須です。
代表品目
- Acids(酸類)
- Alkalis(アルカリ)
- Battery fluid
実務ポイント
- PG(包装等級)により容器強度が異なる
- バルブ・床板の腐食事故が多いため、収納検査が必要なケースあり
- 金属との接触防止措置が必須
次に扱うClass9は、これまでのどの分類にも属さない幅広いグループです。範囲が広いため、誤分類やラベル誤りが起こりやすい点に注意が必要です。
Class 9(その他の危険物)
分類されないが危険性を持つ物質を全て包含する幅広いクラス。申告ミスが最も多いグループ。特にリチウム電池(UN3480/3090)は特別規定(SP188 など)が適用され、ワット時定格量や重量で規制レベルが変わります。また、UN3082/3077(環境有害物質)は日用品にも該当し得るため注意が必要です。
代表品目
- Lithium batteries
- Environmentally hazardous substances
- High-temperature substances
実務ポイント
- ラベル・マーキングが複雑で誤りが多い
- リチウム電池は特別規定 SP188 等を確認
- 温度管理と漏えい防止が重要
ここまでで各クラスの性質を理解しました。次に実務上欠かせない「クラス間の相性」、つまり混載や隔離の基準について確認します。
クラス別の隔離・混載の一覧(実務表)
(※後で表形式で追加可能) 例:
- Class3 × Class5 → 混載不可
- Class3 × Class8 → 隔離必要
- Class9(電池)× Class3 → 発火リスクで制限
まとめ:輸送判断で必ず確認すべき3点
- UN番号(SDSセクション14が根拠)
- クラス+PG(包装等級)
- 隔離要件(Segregation Table)
次のステップとして、必要であれば「UN番号とラベルの図版」や「混載表」を追加して、より実務的なページに拡張できます。
ここまでで輸送判断の流れを押さえました。ここからはさらに一歩進んで、コストや輸送モード差など、判断を深めるための補足事項を紹介します。
追加の実務補足
本記事の理解をさらに深め、実務判断の精度を高めるために、以下の観点を補足します。
包装等級(Packing Group, PG)の重要性
PG は I(高危険度)、II(中危険度)、III(低危険度)に分かれます。PG I は容器規格が厳格であるだけでなく、隔離基準が厳しく、船会社承認(Approval)が通りにくい傾向があります。同じ Class3 でも PG I の貨物は輸送難易度が大きく上がります。
危険物サーチャージ(DGS)とコスト構造
危険物には DGS(危険物割増)が加算され、クラスや PG により金額が異なります。Class 1、2.3、6.1、7、PG I の貨物は費用が特に高額になります。航路・船会社による差も大きく、事前見積りが重要です。
LTD QTY(少量危険物)による緩和措置
LTD QTY を利用すると包装や表示規定が一部緩和され、コストを下げられる可能性があります。対象かどうかは IMDG の該当項目で確認します。
他モード(航空輸送)との規制差
海上では輸送可能でも、航空(IATA-DGR)では輸送禁止または厳格規制となる貨物があります。特にリチウム電池はモード間の規制差が大きいため、一貫輸送の計画段階で確認が必須です。
以上を踏まえれば、危険物輸送の判断には分類知識だけでなく、コスト構造や他モードとの整合まで含めた総合的な視点が求められることが分かります。最後に本記事の要点を整理します。
まとめ
危険物輸送では、クラス(Class)の正確な理解が安全とコンプライアンスの出発点です。特に Class2〜9 に該当する貨物は、見た目が一般品に近くても輸送規制の対象となることがあります。
実務では、まず UN番号と正しい品名(PSN)を照合し、クラスと包装等級(PG)、混載可否を確認することが重要です。また、同じクラスでも PG や状態(液体・固体・ガス)によって扱いが異なるため、SDSセクション14を入念に確認してください。
IMDGコードの更新に伴い、輸送条件や特別規定(SP)の変更も随時発生します。常に最新版を参照し、船会社への事前照会を怠らないことが、遅延や拒否を防ぐ最良の手段です。危険物を安全・確実に輸送するためには、クラス分類・隔離基準・表示規定を体系的に把握し、書類と現物の整合性を常に保つことが求められます。

 この記事を登録
この記事を登録
 目次
目次