海外販売等をするために輸出取引をすると、消費税が還付されるとのお話を聞きます。消費税と言えば、10%です。これが輸出することで戻るなら、キャッシュフローの関係上、魅力があります。
そこで、今回は、輸出取引と消費税の還付関係について、NS&パートナーズ会計事務所 代表税理士の鈴木良洋氏に解説して頂きたいと思います。
この記事の要点
- 輸出取引をすると、消費税の還付申告ができる
- 還付申告ができる人は、輸出者かつ課税事業者のみ
- 消費税の還付申告をする場合は、取引毎の書類保存が重要
- 消費税は、輸出ビジネスのキャッシュフローに大きく影響する。
輸出時の税金(関税・消費税)
今回は、東京地区で税理士として活動されている鈴木氏にお話をお聞きします。この記事では、以下の解説をしています。
- 輸出取引と消費税還付の関係
- 消費税還付申告ができる人の条件
- 消費税還付に関係する国税庁の動き
- 消費税と資金繰りの関係
- 消費税還付と税理士の関係
例えば…..
- 現在、輸出取引をしているけれど、上手に消費税の還付ができていない方
- 消費税の還付申告をしているけれど、還付までにいつも時間がかかる方
- これから輸出取引を始める予定の方にも関係します。
ぜひ、輸出取引と消費税の関係を理解し、抜かりなく還付申告ができるようにしましょう!
2023年7月14日の不正事件
高級化粧品の輸出、実は「水」 東京国税局、卸会社らに追徴44億円
身は水なのに高級化粧品を取引したように装っていたとして、東京都内の化粧品卸会社や輸出会社が東京国税局の税務調査を受け、計約44億円を追徴課税されていたことがわかった。 輸出品は免税になる仕組みを利用し、多額の消費税の還付を受けようとしていたとみられる。
記事の引用元:ライブドアニュース
税理士が解説!輸出と消費税の還付

※以下、NS&パートナーズ会計事務所 代表税理士の鈴木良洋氏が執筆
——————————————————————————–
輸出事業を主として行っている事業者は、消費税が還付されます。
消費税は国内における資産の譲渡貸付け、役務の提供に対して課税されます。日本では現在10%の税率で消費税が課されています。
輸出取引については国外で消費が行われるため、輸出免税取引に該当する場合には売上にかかる消費税は課税されません。そのため輸出事業者は、国内における仕入や事業に掛かる経費とともに、支払った消費税が確定申告をすることで還付されます。
消費税の還付申告の条件は課税事業者
事業者が輸出事業で還付を受けるためには、消費税の課税事業者である必要があります。設立間もない事業者や、売上高が1,000万円以下で消費税の納付が免除されている事業者は輸出事業に伴う消費税の還付を受けることはできません。
消費税の還付を受けるためには、事前に課税事業者選択届出書を税務署に提出して課税事業者になる必要があります。また、消費税には2種類の計算方法があります。通常は売上で預った消費税から、仕入や経費で支払った消費税の差額を税務署に納める原則的な方法で計算します。
しかし、前々事業年度の売上高が5,000万円以下の事業者については、売上高に業種ごとに定められた一定の割合を乗じた金額を仕入や経費で支払った消費税とみなして計算できる簡易的な方法も選択できます。
原則的な計算方法でのみ還付
消費税は原則的な方法で計算した場合にのみ還付されます。簡易的な計算方法を選択している事業者は、事前に選択を取りやめる届出書を税務署へ提出する必要があります。休眠していた事業者や、売上高が5,000万円以下に減少してしまった事業者などは、過去に簡易的な計算方法を選択する届出書を税務署に提出したことがないか確認する必要があります。
十数年前に提出していた届出書でも、条件が整えば簡易的な計算方法の選択が復活して適用が強制されます。輸出事業で消費税の還付を受けるためには、このような前提条件を満たしている必要があります。還付が生じる事業年度で、課税事業者になっていない場合や簡易的な計算方法が適用されてしまう等のトラブルを弁護士の先生から聞くこともあります。
還付申告件数は増加傾向
近年は消費税率が2014年に8%、2019年に10%へと引き上げられたことや、取引のグローバル化を背景に、消費税の還付申告件数が急速に増加傾向にあります。還付申告件数の増加とともに不正還付の請求が目立ってきており、国税庁は警戒感を強めています。
国税庁は2022年1月に「消費税還付申告に関する国税当局の対応について」というリーフレットを公表しました。国税庁の資料(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022001-098.pdf)
資料には、必要とあれば還付申告をいったん保留し、追加資料の提出や税務調査をする場合があると明記されています。確認に時間がかかる場合は還付の留保時間が長期にわたる場合があるとも記載されています。国税側の消費税の還付申告を厳格に管理していくという姿勢が強く伺える内容となっています。
国税庁、消費税調査の専門部署を設置
国税庁は消費税の還付申告に対する調査体制を強化するために、2021年度から全国11税務署に消費税専門部署を配置し、2022年には東京、大阪などの5つの国税局にも消費税専門担当者を配置しています。これに伴い輸出事業者の税務調査の担当官は、消費税の専門官が実地調査に来るようになりました。輸出事業者の税務調査では、取引ごとの確認書類がしっかりと整理されているかどうかが重要なポイントとなります。求められた取引の輸出許可書やインボイスが、すぐに提示できる社内管理体制を構築しておく必要があります。
税務調査と裁決事例
実際に税務調査で指摘された裁決事例として次のようなものがあります。20万円超の商品を、買手の申出に従って20万円以下の商品としてアンダーバリューで郵便物として輸出を繰返していた事業者に税務調査が入りました。輸出許可が必要な商品の場合に保存が必要となる輸出許可書は当然保存されていません。裁決では20万円超の商品で輸出許可書の保存のない取引については、輸出免税を認めないと判断しました。
輸出事業では指摘事項が、取引の大部分に波及する可能性を秘めている怖さがあります。
年々、消費税還付申告に関する調査が厳しくなっている
現場で税務調査に立ち会っている身としても、消費税の還付申告に対する調査が年々厳しいものになってきていると感じています。
すべての税理士が輸出事業に関する消費税還付に精通しているわけではありません。税理士もある程度全般的な知識は有していますが、得意としている分野はそれぞれ異なります。前述したとおり、近年では消費税の還付申告は申告から還付までの期間が長期化する場合があります。
税理士にも得手不得手があり!消費税還付に長けている税理士を!
税務署では還付決済をする日は月に1度です。申告後に税務署との確認書類等のやり取りを繰り返すことで、還付までの期間はどんどん延びていきます。弊所では輸出事業者のスムーズな消費税還付申告を得意としている数少ない税理士事務所です。
取引金額の大きい事業者の方には積極的に消費税の課税期間の短縮を提案し、毎月若しくは3カ月ごとの消費税還付申告をサポートしています。税務調査においても、輸出事業に関する調査事例を他事務所よりも有していることから、事業者の方に不利にならないよう適切に対応することができます。
経済産業局は今後経済成長を実現させるためには、海外の成長市場の取込みが不可欠と説明しています。そんな中、輸出事業は日本において今後も成長分野であるといえます。事業が成長していく中で、消費税の還付は今後も会社の資金繰りに大きく影響を与えます。適切な対策と運用で、スムーズな消費税還付申告を行える事業者の方が増えることを願っております。
ここまで以下、NS&パートナーズ会計事務所 代表税理士の鈴木良洋氏が執筆
鈴木さんの解説記事の要約
ここからは、HUNADEが執筆しています。
鈴木さんの解説内容を要約すると次の通りです。
- 輸出をすると消費税の還付を受けられる。
- 還付を受けられる条件 → 課税事業者であること
- 消費税は、原則的な方法と簡易的な方法のどちらかで計算する。
- 売り上げが5,000万円以下は、業種ごとに規定する簡易的な方法により計算できる
- 消費税還付申告件数は増加。それに伴い、国税庁も税務調査を強化
- 輸出者は、輸出したことを証する書類を過不足なく整えることが重要
- 立証できない場合は、否認されて納税義務が発生する可能性あり
- 税理士には、消費税還付に疎い方がいらっしゃる。(不得手な分野)
特に留意したい3点
- 輸出還付の条件に当てはまること
- 立証書類を過不足なく用意すること
- 還付申告と資金繰りの関係を理解すること
1.輸出還付の条件に当てはまること
消費税の還付申告ができるのは、課税事業者のみです。課税事業者とは、年間の売上高がおおむね1000万円を超えて、消費税の納税義務がある方です。(正確には、1000万円以下でも届け出を出せば可能。ただし、消費税の納税義務が発生)
例えば、ネット上でよくある「副業輸出すれば、消費税が還付されるから儲かる!」等の情報を鵜呑みにして、条件を満たさない人が還付申告はできないです。
輸出消費税の還付申告ができる人は、課税事業者のみ
2.立証書類を過不足なく用意すること
輸出消費税の還付を受ける場合は、いつでも輸出取引の実態を書類で明示できる状態にしなければならないです。つまり、輸出許可書にはじまる貿易関連書類を適切に保存して、税務署から求められたら、いつでも提出できるようにしておくことが重要です。書類がそろっていない場合は、還付までの期間が非常に長くなり、最悪、否認されます。
3.還付申告と資金繰りの関係を理解すること
消費税の還付と資金繰りには、密接な関係があります。適切に資料を用意して、一定期間ごとに還付申告を繰り返せば、資金繰りはよくなります。当然、この逆のことをすれば、中々、消費税が還付されず、結果、事業資金の流動性を悪くします。
- 適切に書類を整えること
- 定期的な還付申告をすること
この2つが輸出ビジネスの資金繰りをよくする秘訣です。
輸出消費税還と税理士の関係
世の中には、税理士さんがたくさんいらっしゃいます。しかし、定期的な「消費税の還付申告」に対応できる税理士さんは少ないようです。
鈴木さんの解説部分にある通り、国税庁(税務署)は、基本的に「消費税の還付をしたくない!」立場です。税収が減るわけですから当然ですね! 消費税還付の条件等を満たすのか?否か?を厳重に確認する理由は当然です。少しでも条件を満たさなければ、そこを指摘するのが税務署です。
つまり、定期的な還付申告は、税理士の業務を圧迫し、非常に時間が取られることを意味します。これが税理士が定期的な還付申告に対応していない理由の一つです。
NS&パートナーズ会計事務所(鈴木さんの事務所)は、資金繰りの改善と輸出消費税の還付を意識したサービスを提供しています。スムーズな還付ができるよう、最大12回の還付申告にも対応できます。
現在、日本国内の事業の他、海外ビジネス(輸出事業)をしている方、又は、これから海外輸出ビジネスを始める方は、一度、鈴木さんに相談されてはいかがでしょうか?
鈴木さんは、消費税の還付申告だけではなく、小さな貿易ビジネスをされている個人事業様の会計周り(確定申告等、帳簿処理等)の支援もできます。
参考情報:輸出還付の依頼者には、次の方(業種)が多いそうです。
- 買い取り業者
- リサイクル業者
- 中国国籍の方が母国へ輸出される
- 越境ECを運営する方
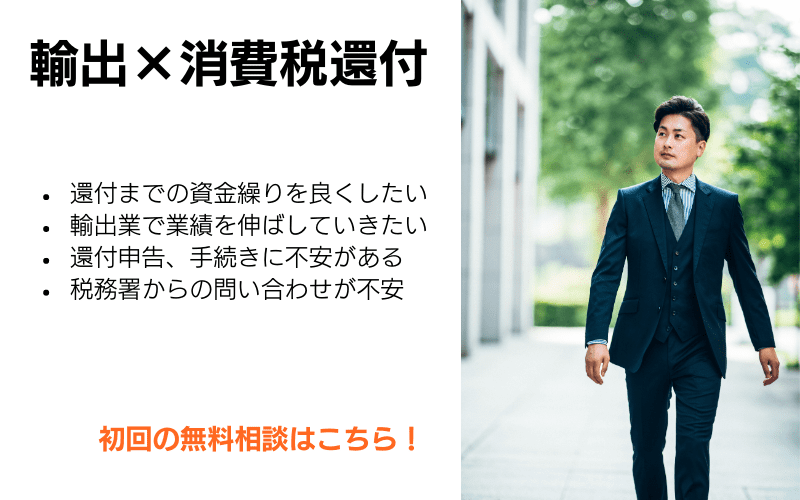

 この記事を登録
この記事を登録
 目次
目次
