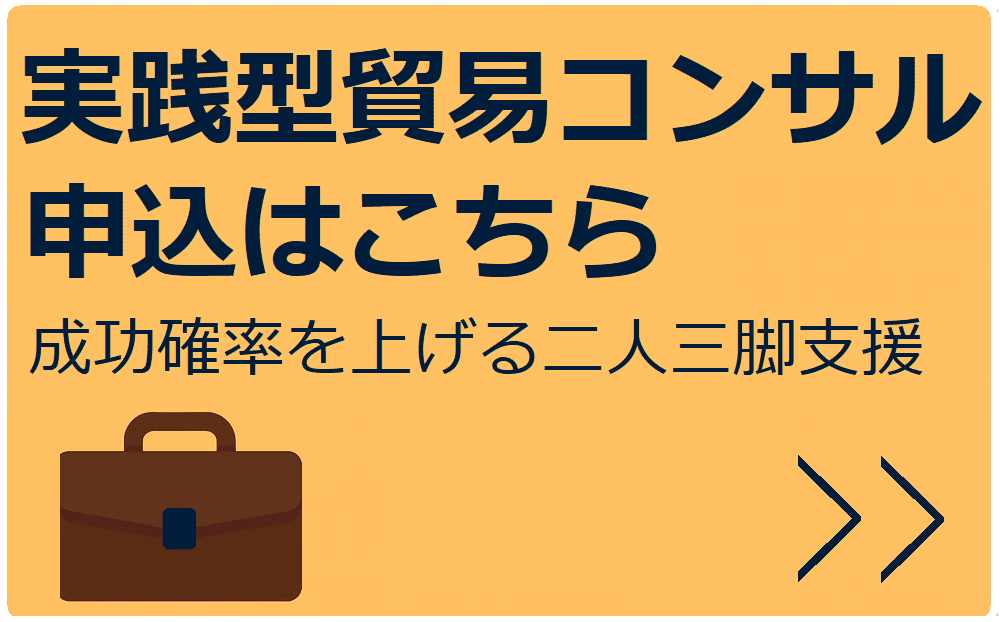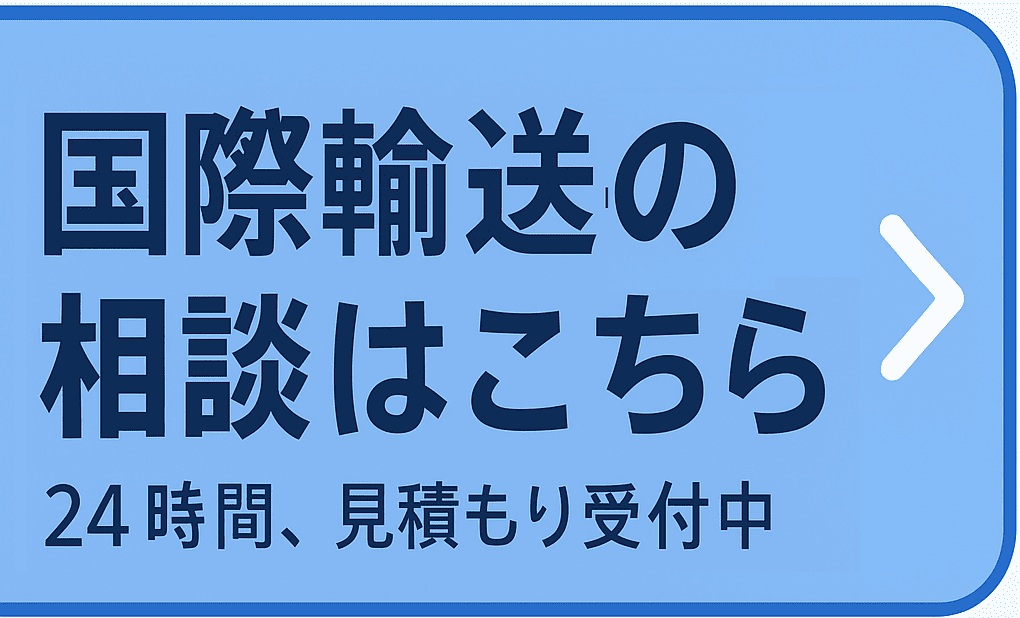婦人服の輸入で問われた課税価格と税関対応
この記事では、婦人服などの繊維製品を輸入する企業が関税の申告に関して税関と争い、審査請求を行った事例(答申第106号)をもとに、貿易事業者が注意すべき申告の実務、調査対応、社内体制づくりについて解説します。
インボイス記載額を鵜呑みにすることのリスク、実際の支払い実績との整合性をどう取るべきか、事例から読み解いていきます。
事案の概要と争点
本件は、婦人服の輸入に関して、申告に用いたインボイスに記載された価格と実際の請求書記載の金額(および支払額)に差異があったことが発端です。税関はインボイス額が実態を反映していないとして、より高額な請求書ベースで課税価格を再計算。その結果、輸入者に対して更正処分と過少申告加算税の賦課を行いました。
主な争点は、次の3点です。
- 課税価格の算定方法としてインボイスか請求書かどちらが適切か。
- 税関による調査の選定や手続きが適法かどうか。
- 加算税の賦課について「正当な理由」があったか否かです。
課税価格の算定に関する実務上の注意点
課税価格の原則は「現実支払価格」に基づくことです。これは、関税定率法第4条で明確に定められており、「輸入取引に関し売手に対して支払った総額」が基本です。単にインボイス記載額を申告に使っても、それが実際に支払った額より低い場合は、否認されるリスクがあります。
本件では、インボイスの金額が請求書や送金記録の額より低く、しかも請求書に含まれていた運賃も申告価格に含まれていませんでした。税関はこれらを根拠に、実際の支払額と一致しないインボイス価格を否認し、請求書に基づく価格+運賃を課税価格と認定しました。
重要なのは、インボイス、請求書、送金記録の3点セットが整合しているかどうかです。支払いが複数回に分かれていたり、他の費用をまとめて送金していた場合は、どの費用がどの貨物に関係しているか明確にしておかなければなりません。
また、答申書では「差額が本件輸入貨物に使用されていない生地の代金であることを客観的に証明する資料が提出されていない」と明記されています。合理的な説明には、主観的な説明ではなく、契約書や仕様書、検品報告などの客観的証拠資料の提示が必要です。

主観的な説明は無意味です。必ず客観的、合理的な立証資料が必要です。何らかの主張をするのであれば、その主張を裏付ける客観的な資料が必要です。
税関調査・更正処分への対応
税関から指摘を受けた場合、資料を精査し、合理的な説明ができるよう準備します。税関は、申告内容に疑義があった場合、調査結果に基づいて修正申告を促すことがあります。本件でも最初は修正申告の勧奨がなされましたが、輸入者が応じなかったため更正処分に至っています。
税関調査の対象企業選定は、「平等でなければ違法」というわけではありません。答申書でも、調査対象の選定は税関職員の裁量に基づき行われ、特段の違法性がなければ問題なしとされています。ただし、調査手続そのものに違法があった場合、処分自体が無効になるかどうかは別問題です。答申書では「調査手続が重大な違法を帯びる場合に限り、処分に取消原因がある」とされており、単なる手続上の瑕疵では処分自体が違法とまではされません。
過少申告加算税のリスクと回避策
加算税の賦課は、原則として「納税義務違反」があれば自動的に行われます。「正当な理由」があれば免除される可能性もありますが、その範囲は非常に限定的です。
本件では、インボイス記載額と実際の請求書・送金記録との間にズレがあることを、輸入者が確認しなかったことが問題視されました。つまり、注意すれば防げたミスであり、「正当な理由」はないとされました。
正当な理由が認められるのは、たとえば関税分類に関する判断が専門的に分かれるケース、関税定率法の解釈に争いがある場合、または税関からの事前教示に従っていた場合など、納税者の責めに帰さない客観的事情があるときに限られます。こうした判例・通達例を踏まえて、輸入者側に落ち度がないことを立証できるかが重要です。
そのため、実務的には申告価格の妥当性を社内で二重チェックし、価格決定のプロセスや値引き・減額の理由を記録として残すことが加算税を回避する上で重要です。

例えば、そんなのは知らなかったなどは、一ミリ足りとも考慮されないです。気を付けましょう。
事前教示制度の活用
申告価格や課税標準について不明な点がある場合、「事前教示」を積極的に活用しましょう。これは関税法第7条第3項に定められており、税関は適切な教示に努める義務があります。
今回の事案でも、輸入者は事前に税関に教示を求めていませんでした。もし事前に申告価格の妥当性について教示を受けていれば、結果が異なっていた可能性もあります。
日頃から制度を活用する姿勢を持ち、不明点は申告前に解消することが、税務リスクの低減につながります。

事前教示は、事後的に税関の公式見解を証明するための仕組みです。つまり、これは、万が一、分類ミス等が事後的に発見されても、税関側にも一定の責任を負わせる仕組みでもあります。=弁解する余地を残す制度
分科会の答申書から学べること
まとめ
- インボイス価格が実際の支払いと異なる場合は、現実支払価格が優先される
- インボイス・請求書・送金記録の整合性が課税価格判断のカギとなる
- 合理的な説明には、客観的証拠資料の提出が不可欠
- 税関調査に違法があっても、処分が違法になるのは重大な瑕疵がある場合に限られる
- 正当な理由が認められるのは、税関教示に従った場合や法解釈に合理的争点がある場合のみ
- 社内で申告価格決定の根拠や取引状況の管理体制を整えることが重要
- 迷ったら事前教示制度を活用し、リスクを未然に防ぐことが望ましい

 この記事を登録
この記事を登録関連記事
基幹記事
貿易学習コースの一覧
分野別記事
カテゴリの一覧
関連記事
◆スポンサード広告


 目次
目次