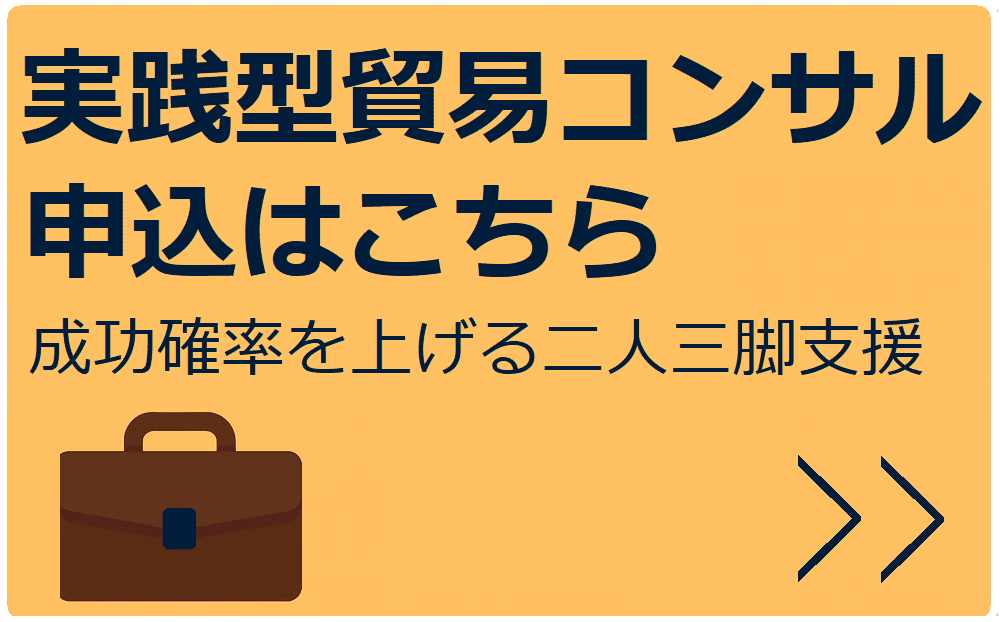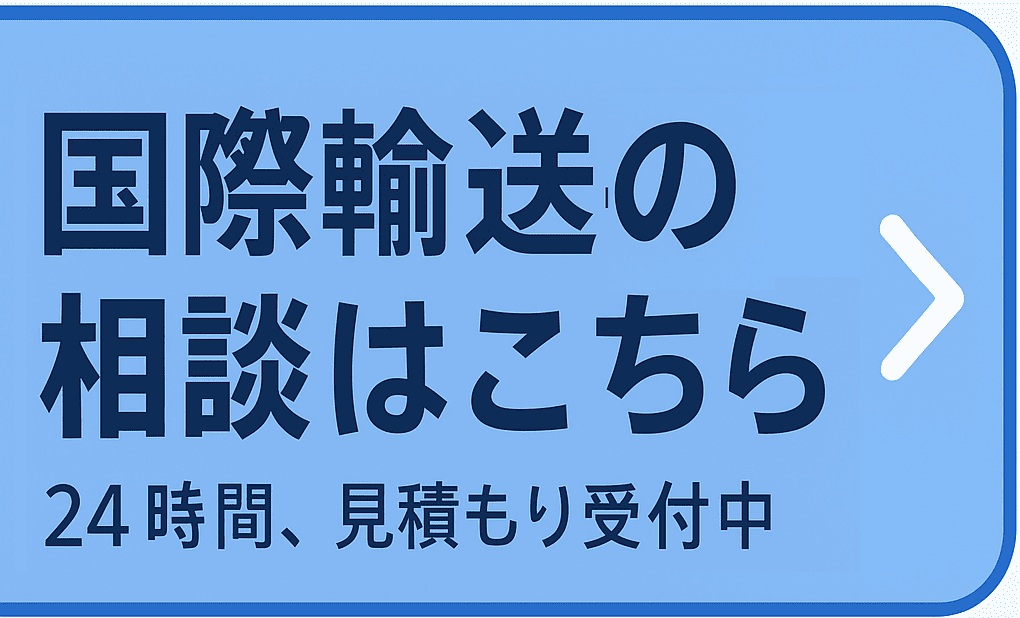商標権侵害で輸入差止?個人輸入と”業として”の境界線
答申書の概要
この記事のテーマ:関税等不服審査会・答申110号
この審査会の答申書は、税関が「商標権を侵害している疑いがある」として差し止めた国際郵便物について、輸入者が「個人で使うために買った」と主張した事案を扱ったものです。
審査会では、なぜ輸入したのか、どのくらいの量だったのか、輸入者はどんな仕事をしているのか、どのような取引だったのかなどを総合的に調べました。その結果、輸入者が商売として商品を売る人には当たらないと判断しました。そのため、今回の荷物は商標権を侵害する物品ではなく、税関が差し止めた処分は取り消すべきだという結論に至りました。
この判断は、個人が自分で使うために海外から商品を取り寄せる場合、たとえ偽物でも「商売として」行っていない限り、商標権侵害には当たらないという、これまでの法律の解釈に基づいています。
ただし、2022年10月からは法律が改正され、海外の業者から送られてくる偽物は、個人が使う目的であっても原則として輸入できなくなりました。そのため、今後はより厳しい審査が行われることになります。
この事案では、個人使用と商売目的の輸入の境界線をどう引くか、証拠があるかどうか、輸入者の説明に納得できるかどうかなどが、重要な判断のポイントになったことがわかります。
すべて個人使用目的であり、業としての輸入ではない
認定手続に対し、輸入者は「すべて個人使用目的であり、業としての輸入ではない」と主張しました。主張の中では、購入した商品がすべて自らまたは家族による使用を前提としており、商業的な目的ではないこと、商品が新品であるのは個人の保管習慣によるものであること、また数量が多いのは長年にわたって買い集めたものをまとめて発送したためであるなどの説明がなされました。
税関は事業性を疑う
税関側は、「新品状態が維持されている」「明細書やレシートなどの購入証明書類が提出されていない」「数量が43点と比較的多い」などの点を根拠に、個人使用とは言い難いとして、業性が疑われる(商売をしている)との判断を下しました。このため、関税法に基づく認定手続が開始され、関係者への意見提出機会などが与えられた上で、最終的に認定通知が行われました。
これに対し、輸入者は行政不服審査制度を活用して不服申立てを行い、自身のライフスタイルや物品の保管・取得経緯などについて詳細に説明しました。その結果、関税等不服審査会においては、主張の信ぴょう性や合理性が一定程度認められ、最終的に税関の認定通知は取り消されるという結論に至りました。
商標の使用に該当するのか?
商標法においては、「商標を付した商品を輸入する行為」は“商標の使用”に該当します(第2条、第3項)。したがって、商標権者の許可を得ずに、同一または類似の標章が付された商品を輸入する場合、それは商標権の侵害とされる可能性があります。特に、商標法第25条は登録商標の専用権について、また第37条では侵害とみなされる行為を明記しています。
ポイント:業(商売)としての側面はある?
ただし、実際の輸入行為がすべて自動的に侵害とみなされるわけではありません。「業として」の輸入であるかどうかが、非常に重要な判断基準となります。
税関および審査機関は、以下の要素を総合的に検討します。
- 輸入品の数量(多ければ業性が疑われやすい)
- 輸入者の職業(商売に関係する人物であるか)
- 輸入の頻度や方法(まとめて送る、または定期的に繰り返しているか)
- 購入経路や証拠資料の有無(レシート、請求書など)
- 品目の性質(個人で使うには不自然な種類や量)
この事例では、輸入者は「主婦」であり、商品の購入も自分や両親が過去にD国で行ったと説明しましたが、それを裏付ける書類がほとんど提出されていなかったことから、税関側は業性が疑われるとして手続きを進めました。
審査会は個別具体的に判断
審査会は特に以下の点を個別に評価しました。
たとえば「数量が多い=業性」とは限らないこと、品目構成の多様性や保管状況も重要な要素となること。また「主婦である」こと自体は業性を否定する決定的要因とは見なさず、職業にかかわらず証拠の有無や主張内容を総合的に検討しました。
さらに、購入時期の不明確さやレシートの非保管についても、「個人によって対応に差がある」とし、信ぴょう性を一律に否定することはできないと判断されました。
これらを総合的に判断した結果、審査会は「業として譲渡等する者に当たると認めることは困難」として、結果的に商標権侵害物品に該当しないと判断しました。
なお、審査請求人は、半年以上かけて争ったことに対する時間的・金銭的補償を求めましたが、審査会は「本件処分の適否とは関係がない」として判断の対象外としました。
この件から学べること
自らの使用目的を説明するための「証拠資料」を用意しましょう。購入時の領収書、使用履歴がわかる写真やメモ、品目の入手経路などがあれば、審査段階での説得力が格段に増します。
また、「数量」についても注意が必要です。たとえ同一品を複数保有していたとしても、それが自家用であるという一貫した説明ができなければ、業性を疑われるリスクは高まります。
万一、税関から差止手続きの通知が届いた場合は、期限内(10日以内)に争う意思を明確に示し、合理的かつ具体的な主張と証拠提出により、自己の立場を正当に主張が求められます。
通関時の注意点
通関実務においては、輸入者が輸入目的や商品実態を明確に把握していないと、結果的にトラブルに巻き込まれる可能性もあります。仕入担当者、通関担当者が連携し、事前に輸入物品の商標権状況をチェックする体制を整えておくことが、今後ますます重要になります。
分科会の答申書から学べること

 この記事を登録
この記事を登録関連記事
基幹記事
貿易学習コースの一覧
分野別記事
カテゴリの一覧
関連記事
◆スポンサード広告


 目次
目次