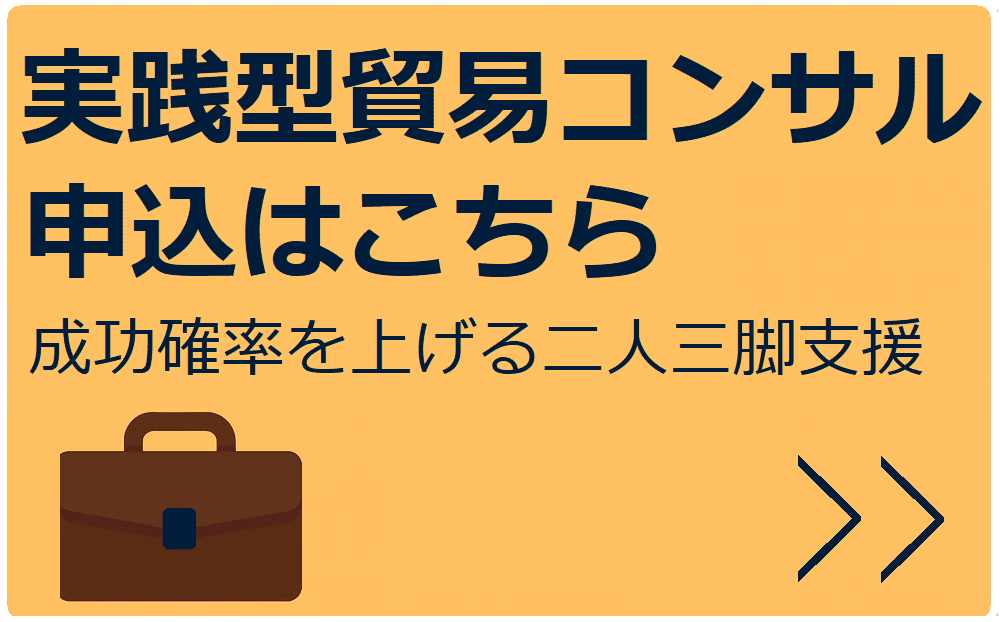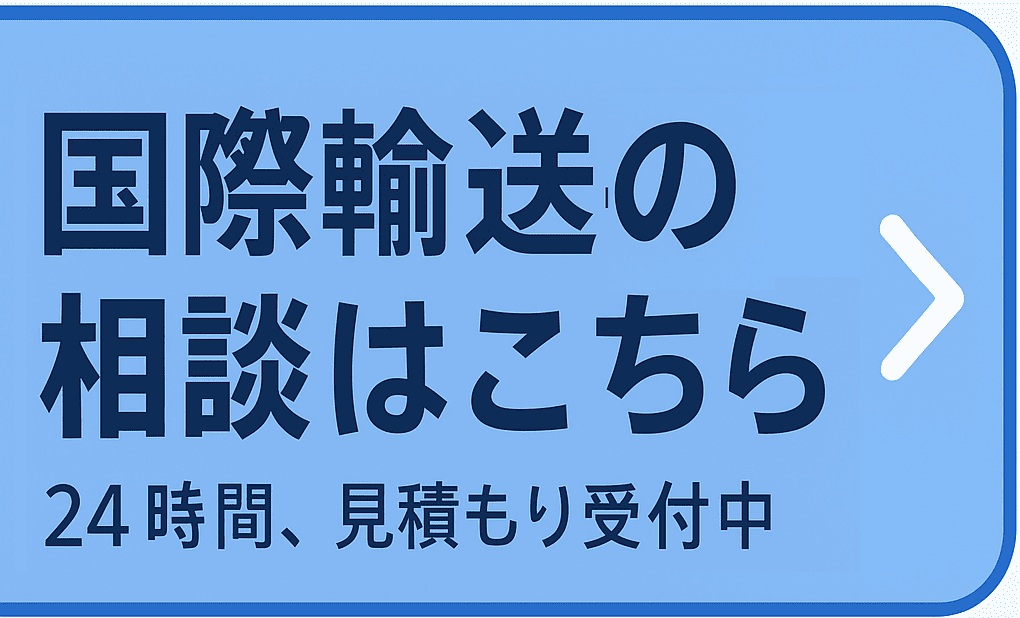関税審査の答申書から学ぶ、貿易事業者の実務ポイント
本記事では、農薬原料をめぐる関税分類争いに関する不服審査答申書(答申第111号)をもとに、貿易事業者が実務上で注意すべき点を解説します。
関税分類や更正請求、証拠資料の扱い、事前教示の活用法など、貿易実務者が直面する可能性のあるリスクと対応策を具体的に整理します。
事案の概要
農薬の原料にかかる関税について、納税者が「化学的に単一の有機化合物」として、より安い税率を適用してもらおうとした件です。
しかし、添加物がどのような目的で使われているのか、どのくらいの量が含まれているのかについて、十分な証拠が示されなかったため、申請は認められませんでした。
審査会は、これまで通りの分類と税率を適用するという判断を下しました。
この結果から….
- 関税分類は厳格に運用されること
- 申告した内容を証明する責任は納税者にあること
などがよりはっきり示されたと言えるでしょう。
対象貨物と申告内容
審査請求人は、除草剤・殺菌剤の原料を輸入し、関税率表第38.08項の「除草剤」や「殺菌剤」として協定税率3.9%で申告していました。
しかし、同原料は本来「化学的に単一の有機化合物」であり、関税率表第29類に分類されれば3.1%の税率となるため、申告後に更正請求を行いました。
更正請求と審査会判断
申告後、添加物の性質や量に基づき、29類に該当すると主張して更正請求。しかし、審査会は「添加量や目的が関税率表第29類に定める要件(”必要最小限の添加”)を満たさない」として、請求を棄却しました。
貿易者が学ぶべきポイント
1.関税分類を正しく把握すること
関税率表の解釈は、項・号・注の文言および通則に従って厳密に行われます。特に「化学的に単一の有機化合物」として29類に分類するためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 安定剤の添加は輸送・保存の目的に限られること
- 添加量は”目的を達成するための必要最小限”
- 添加により製品の性質や用途が変わってはならない
本件では、添加物が粉砕助剤としての機能を持つこと、またその量が必要最小限と認められなかったため、29類の適用が否定されました。
2.証拠の提出と立証責任は輸入者が負う点
申告納税制度では、納税者が自己責任で申告し、後に更正請求をする場合は、主張を裏付ける証拠を提出する義務があります。
このことから、審査会は次のような証拠提出を求めました。
- 添加物の性質・目的を示す技術資料や製造仕様書
- 添加量が必要最小限であることを証明する試験結果や文献
- 製造工程や使用環境を示す客観資料
しかし、本件では、添加量の正当性や添加物の役割を裏付ける明確な証拠が示されなかった為、立証不十分とされました。
3.事前教示制度の限界を知る。
事前教示とは、申告前に貨物の関税分類を税関に確認できる制度です。
しかし、本件では以下の理由から事前教示の効力が否定されました。最も重大な理由は、事前教示と実際の貨物の相違が認められた点です。
- 教示対象と実際の貨物との相違(成分構成、用途など)
- 教示時の説明内容と実態の不一致
- 教示は原則として将来の申告に適用されるもので、過去申告には適用されない。

教示時に提出した書類と現物に相違がある点が否決原因です。
4.申告納税制度と自己責任論
関税制度は申告納税方式であるため、輸入者自身が分類・税率の妥当性を判断し、責任を負います。仮に更正請求をする場合も、自ら誤りを立証しなければならず、「事前教示があるから正しいはずだ」という主張だけでは何の反論にもならないです。
5.手続き・期限管理の重要性
再調査請求や審査請求には、申告後の所定期限が存在します。本件では、ある通知に対する審査請求が3か月以内に行われなかったため、「却下」されました。
期限を一日でも過ぎれば不適法となるため、日付管理は徹底する必要があります。
実務へのアドバイス
本件を通して今後、同様の事案を防ぐには、以下の点に留意した方が良いでしょう。
しっかりと社内体制を構築する
- 商品分類の知識を共有する社内マニュアルの整備
- HSコードの根拠を文書化し、輸入時に確認
専門家と連携すること
全てを社内で済ませようとする所に無理があります。必ず外部の専門家の知見を入れましょう。
- 税関OBや通関士など外部の専門家と連携
- 曖昧な商品については事前教示を取得
証拠資料の管理
立証責任は輸入者側にあります。立証するための資料管理を徹底しましょう!
- 製造工程、添加物の性質・用途などを記録・保存
- 将来の更正請求や調査対応の備え
分科会の答申書から学べること
まとめ
本件答申書からは、以下の教訓が得られます。
- 関税分類は通則や注の厳格な読み込みが不可欠
- 添加物の性質や量も分類に大きな影響を与える
- 立証責任は輸入者にあり、十分な証拠が求められる
- 事前教示は有効な手段だが、適用限界に留意
- 更正請求や審査請求は、期限管理が命
これらを踏まえ、輸入申告時のチェック体制と証拠管理を徹底することで、後のリスクを大幅に低減できます。貿易実務の現場で、確実な対応を行うための参考としていただければ幸いです。

 この記事を登録
この記事を登録関連記事
基幹記事
貿易学習コースの一覧
分野別記事
カテゴリの一覧
関連記事
◆スポンサード広告


 目次
目次