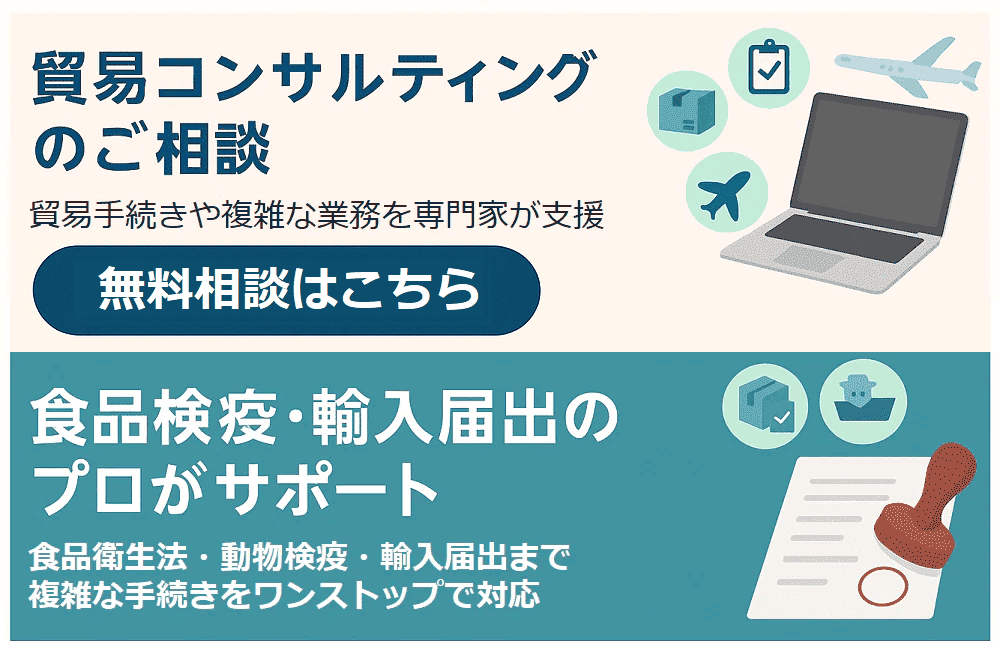輸入食品実務者(Q&A/FAQ)
食品を日本へ輸入する際には、厚生労働省の「輸入食品監視指導計画」に基づく手続きや検査だけでなく、書類準備・検査対応・違反速報への即応・輸入後の改善など、全工程にわたる正確な知識と実務力が求められます。
本FAQ集では、輸入前の事前調査から輸入後のフォローまでを5つのシーンに分け、実務者が実際に直面する39の疑問に回答。HSコードの判定、海外違反事例の活用方法、検査命令品目の対応、違反発生時の初動フローなど、現場で役立つ情報を網羅しました。
シーン1:輸入前の事前調査
Q1. 輸入予定の食品が「検査命令実施通知」かどうかは、どこで確認できますか?
A1. 厚生労働省の「輸入食品監視指導計画」と「検査命令品目リスト」で確認できます。HSコードや品名で照合し、該当すれば輸入前に指定検査機関での検査が必要です。
Q2. 海外での違反事例を日本の輸入判断に活かす方法はありますか?
A2. EU RASFF、FSA IIH、FDA IRR/Import Alerts、英FSA Imports Intelligence Hub(IIH、旧EWS)、FDAのImport Refusal Reports等で同一品目・産地・HSコードの違反傾向を把握し、日本の自主検査や仕入先評価に反映します。

GLOBEFISHは主に市場・貿易情報であり安全違反データベースではないです。
Q3. 自社製品のHSコードを誤った場合の影響とチェック方法は?
A3. 分類誤りは課税額や検査命令対象判定のミスにつながり、通関遅延・追徴課税・是正指導のリスクがあります。税関の検索ツール、通関士の確認、事前教示制度で確定してください。
Q4. 動物・植物検疫(MAFF)の対象かどうかはどこで判定しますか?
A4. 畜水産物や生鮮農産品等は動物検疫所・植物防疫所の対象となる場合があります。該当時は食品衛生法の手続と並行し、各所の要件を満たす必要があります。
Q5. 食品添加物の使用可否はどう確認しますか?
A5. 日本で認可されていない添加物・使用基準超過は違反となります。成分規格書を取得し、日本の基準(使用基準・成分規格)に照合してください。
Q6. サプリメント等の区分判断は?
A6. 形状・表示・用途により医薬品や保健機能食品に該当し得ます。表示内容を含めて所管官庁の基準に照らして事前確認しましょう。
Q7. 事前相談はどこにすれば良いですか?
A7. 関税分類は税関の事前教示、衛生要件は検疫所の事前相談が有効です。書類案や規格書を用意して相談すると判断が早まります。
Q8. 輸送・保管条件(コールドチェーン)の事前確認ポイントは?
A8. 温度逸脱は品質劣化や微生物リスクを高めます。積付け計画、温度データロガー、到着時の温度記録の取得を準備してください。
シーン2:輸入申告前の準備
Q9. 輸入申告前に必要な基本書類は?
A9. 輸入届出書、原材料・成分表、製造工程図、規格書、ラベル案等。高リスク品や検査命令品目は分析証明・公的証明が追加で必要です。
Q10. ラベル表示はいつ、どの程度準備すべき?
A10. 食品表示法への適合を輸入前に確認します。品名、原材料、アレルゲン、栄養成分、原産国、輸入者情報等を網羅し、誤表示防止のため版管理を行います。
Q11. 原産国表示やアレルゲン表示の注意点は?
A11. 原材料の混合比や加工実態により表示が変わる場合があります。原材料原産地表示は食品表示基準改正(2017)に基づきます。

アレルゲンは、2023/3/9に「くるみ」を追加しています。
Q12. 過去に違反した品目を再輸入する際のポイントは?
A12. 改善報告や再検査証明を準備し、是正後の仕様書を提出。強化検査対象かを確認のうえ、必要なら自主検査を追加します。
Q13. 検査命令品目の試験項目はどう選ぶ?
A13. 指定項目を基本に、海外違反傾向(IIH/EWS・FDA等)を加味して追加項目を設定。ロット特性に応じて最適化します。
Q14. どの検査機関を使えば良い?
A14. 指定(登録)検査機関から、対象品目・試験法に対応し、リードタイム・費用・品質システムが妥当な機関を選定します。
Q15. 複合加工品の分類・基準確認は?
A15. 最終製品の性状と主原料で分類が変わります。該当規格(成分規格・添加物・微生物基準)を総合的に確認してください。
Q16. 書類不備を防ぐベストプラクティスは?
A16. チェックリスト化、版管理、仕入先レビュー会、通関業者・検疫所への事前相談が有効です。
シーン3:検査・審査の対応
Q17. 検査結果が出るまで貨物はどう扱う?
A17. モニタリング検査は結果判明前でも輸入手続・通関が可能(検査費用は無料)。命令検査は結果判明まで輸入不可です。
Q18. 一部だけ先に販売できますか?
A18. 原則不可。同一ロットは結果判明まで不可です。ロット分割での別申告は事前計画が必要です。
- モニタリング検査=可能
- 命令検査=不可
Q19. サンプリングは誰が、どのように実施しますか?
A19. 検疫所職員等が所定の方法で採取します。必要量や保存条件は試験法に従います。
Q20. 不合格時、再検査は可能ですか?
A20. 再検査の可否は所管検疫所に確認しましょう。
Q21. 検査費用は誰が負担しますか?
A21. 原則、輸入者負担です。事前見積もりと予算化を行いましょう。
Q22. リードタイムを短縮するには?
A22. 書類の完全性、検査機関の事前予約、到着即日のサンプル引取、迅速法の活用等で短縮可能です。
Q23. 高リスク品で追加提出が求められる書類は?
A23. 原材料証明、製造工程詳細、HACCP関連資料、輸出国公的証明等が求められる場合があります。
Q24. 品質トラブルが疑われる場合の任意検査は可能?
A24. 可能です。自主検査を追加して安全性を確認し、結果を当局判断の参考資料として提示することがあります。
シーン4:違反速報を受けた場合の対応
Q25. 輸入予定品と同じ違反速報が出たら?
A25. 直ちにロット・仕入先・産地を突合し、該当すれば輸入計画を見直すか、自主検査を追加します。輸送中であれば到着後優先検査を手配します。
Q26. 違反が発生した場合の初期対応フローは?
A26. ①品質責任者報告 → ②在庫・輸送中ロット特定 → ③販売・出荷停止 → ④仕入先へ原因確認 → ⑤自主検査 → ⑥必要に応じ行政報告 → ⑦対外広報の準備。社内マニュアル化と訓練が必須です。
Q27. リコール判断の基準は?
A27. 健康被害の可能性、違反の重大性、流通範囲、回収実行性を総合評価します。必要に応じて所管庁に相談し、クラス区分と公表方法を決定します。
Q28. 仕入先への是正要求(CAPA)はどう設計する?
A28. 原因分析、是正策、予防策、期限、エビデンス提出を明記し、完了確認まで追跡します。
Q29. 契約・品質協定書の見直しポイントは?
A29. 仕様逸脱時の通報期限、検査証明の提出義務、変更管理、監査権限、賠償条項を明確化します。
Q30. 代替仕入先の即応手順は?
A30. 事前承認リストを整備し、規格書・サンプル・試験成績書の迅速取得手順を定めます。
Q31. 海外警告(IIH/EWS等)を社内でどう回す?
A31. 受信窓口を決め、購買・品質・物流へ即時配信。該当品目があるかをダッシュボードで自動照合する体制が有効です。
シーン5:輸入後のフォローと継続改善
Q32. 記録保存は何を、どのくらい行う?
A32. 輸入届、検査結果、成分規格書、ロット追跡、是正記録など。社内規程で保存期間と保管方法を定めます。
Q33. 年次レビューでは何を確認する?
A33. 違反・不適合の傾向、仕入先の合否率、検査コスト、是正効果をレビューし、翌年度の検査計画に反映します。
Q34. 監査に備えて整えるべき資料は?
A34. 手順書、教育記録、検査台帳、追跡記録、是正記録、仕様変更履歴等を整備します。
Q35. 監視指導計画の改訂があったときの社内対応は?
A35. 改訂点を一覧化し、影響品目の特定、検査計画・表示・契約の改訂、社内教育を実施します。
Q36. 自主検査の頻度はどう設計する?
A36. 海外違反率、仕入先合否率、品目リスク、季節性、クレーム件数をパラメータに、リスクベースで頻度を設定します。
Q37. 社内教育の頻度と内容は?
A37. 年1回以上の全体教育に加え、制度改正や不適合発生時は臨時教育をするのが望ましいです。HS分類、表示、検査手順、初期対応フローが重要です。
Q38. 海外制度(IIH/IFIS/FSANZ/FDA)のウォッチ体制は?
A38. 情報ソースの定期購読、RSS/メールアラート、週次ミーティングでの共有、該当品目の自動突合を仕組み化します。
Q39. データ活用の具体策は?
A39. HSコード・産地・仕入先単位で違反率ダッシュボードを作成し、調達判断と検査頻度の根拠にします。

 この記事を登録
この記事を登録
 目次
目次