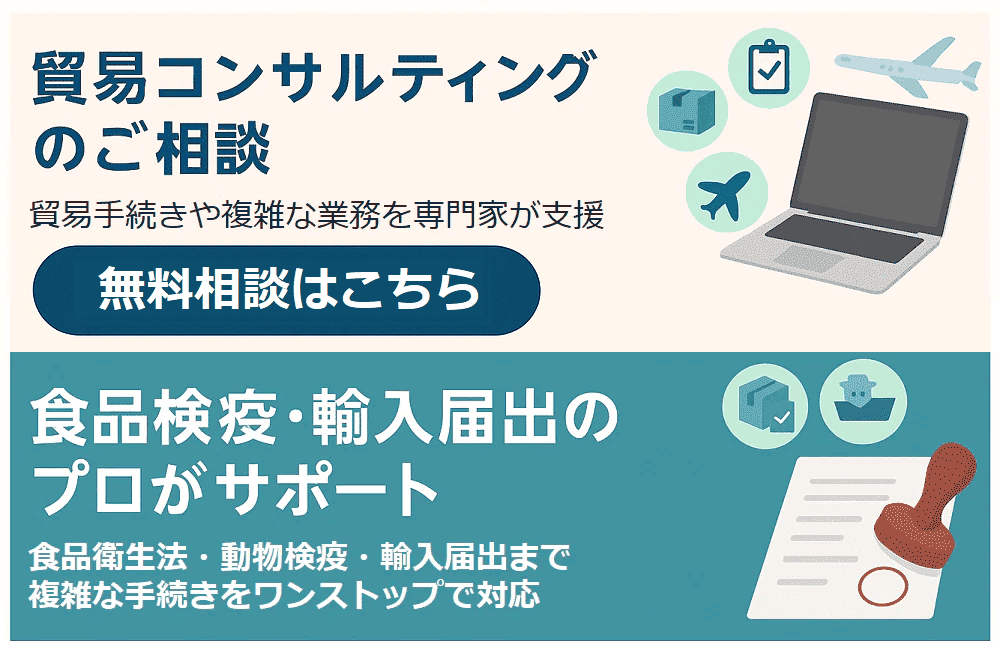養殖えび(冷凍えび)監視リスク
- 養殖えびはニトロフラン、クロラムフェニコールの残留がND(不検出)基準で、検出されると違反。
- サンプリングは尾部筋肉を個別採取し混合分析、薬剤使用記録と「不使用証明書」を必ず添付。
- 加工場ではロット混合禁止、保管タンク間の交差汚染防止、輸送は-18℃以下を維持し温度記録を保存。
- 違反時は検疫所の指示に従い、原則『廃棄又は積戻し』。社内ではロット隔離・原因分析(CAPA)・関係者連絡を実施」
- 検疫所連絡→ロット隔離→再検査→輸出者連絡→廃棄・返送判断→社内報告の流れ。
- 高リスク産地(インド・ベトナム・ミャンマー)は監査と薬剤記録徹底、混合防止管理を強化。
養殖えび特有の動物用医薬品残留・交差汚染リスク
養殖えびは、病気を防いだり成長を早めるために、育てている段階で動物用の薬が使われることがあります。この薬の残り(残留)が基準より多いと、日本に輸入するときに不合格になります。特に「ニトロフラン」や「クロラムフェニコール」という薬は、日本ではごくわずかでも検出されると違反になります。
また、えびを加工するときに、別の原料から薬が混ざってしまう「交差汚染」や、複数の原料を混ぜたことで汚染が広がる危険もあります。
最新違反傾向と原因(産地別薬剤検出・加工工程リスク)
インド、ベトナム、ミャンマーなど主要産地でニトロフランやクロラムフェニコール検出事例が継続。特に加工場で複数ロットを混合する工程や、凍結前の保管タンクでの交差汚染が原因となるケースが報告されています。港湾保管や輸送中の温度管理不備による品質劣化も課題です。
実務者向け管理基準(薬剤管理・サンプリング・加工・輸送)
- ニトロフランやクロラムフェニコールという薬は、日本では検出されない(ND)ことが基準です。わずかでも出ると違反になります。
- 検査用のサンプルは、えびの尾の筋肉を1匹ずつ取り、混ぜて均一にしてから分析します。
- 養殖場では、使った薬の記録(薬の種類、使った日、量)を管理簿に残し、「薬を使っていない証明書」を必ず発行します。
- 加工場では、異なるロットを混ぜないこと、保管タンク同士で薬が混ざらないよう対策します。
- 輸送中はマイナス18℃以下を保ち、その温度の記録を残します。
養殖えび輸入で頻発する失敗事例と改善策
- 失敗例1:加工場で複数のロットを混ぜたため、高リスクのロットが原因で全部が汚染された。 → 改善策:ロットごとに分けて加工し、専用のラインを使う。
- 失敗例2:養殖場で薬の使用記録がきちんと残っていなかった。 → 改善策:定期的に監査を行い、統一された記録用テンプレートを使う。
- 失敗例3:輸送中に温度が上がって品質が悪くなった。 → 改善策:温度を記録する機器(温度ロガー)を使い、異常があればすぐに知らせる仕組みを整える。
冷凍・養殖えびの表示ルールと加熱表示の注意点
名称は「冷凍えび」または「養殖えび」。原材料名にはえびの種類(例:バナメイえび)を明記し、原産国名を記載。アレルゲン表示「えび」を必ず行う。加熱調理の必要がある場合はその旨を明記。
実務TIPS
- 違反が見つかったときの流れ:まず検疫所に連絡 → 該当ロットを隔離 → 再検査 → 輸出者へ連絡 → 廃棄・返送・再加工の判断 → 社内報告。
- 事前検査の例:ニトロフランとクロラムフェニコールを同時に検査する場合、期間は約5〜7日、費用は1ロットあたり5〜8万円。
- ロット管理方法:QRコードでロット番号、薬の使用記録、検査証明をまとめて管理。検査用のサンプルは2年以上保管する。
- 国際基準の比較:日本、EU、コーデックスの薬剤残留基準の違いを把握し、仕入れ先との交渉に役立てる。
- 検査の効率化:リスクが高い国やロットから優先して検査し、リスクが低いロットは定期的にチェックする。
国別違反傾向・管理基準・サンプリング方法と実務メモ
| 国・地域 | 近年の違反傾向 | 推奨管理基準 | 推奨サンプリング | 実務メモ |
|---|---|---|---|---|
| インド | ニトロフラン検出 | ND | 尾部筋肉採取 | 加工場での混合ロット管理強化 |
| ベトナム | クロラムフェニコール検出 | ND | 同左 | 養殖場監査と薬剤記録徹底 |
| ミャンマー | 両成分検出事例 | ND | 同左 | 保管タンク間の交差汚染防止必須 |

 この記事を登録
この記事を登録
 目次
目次