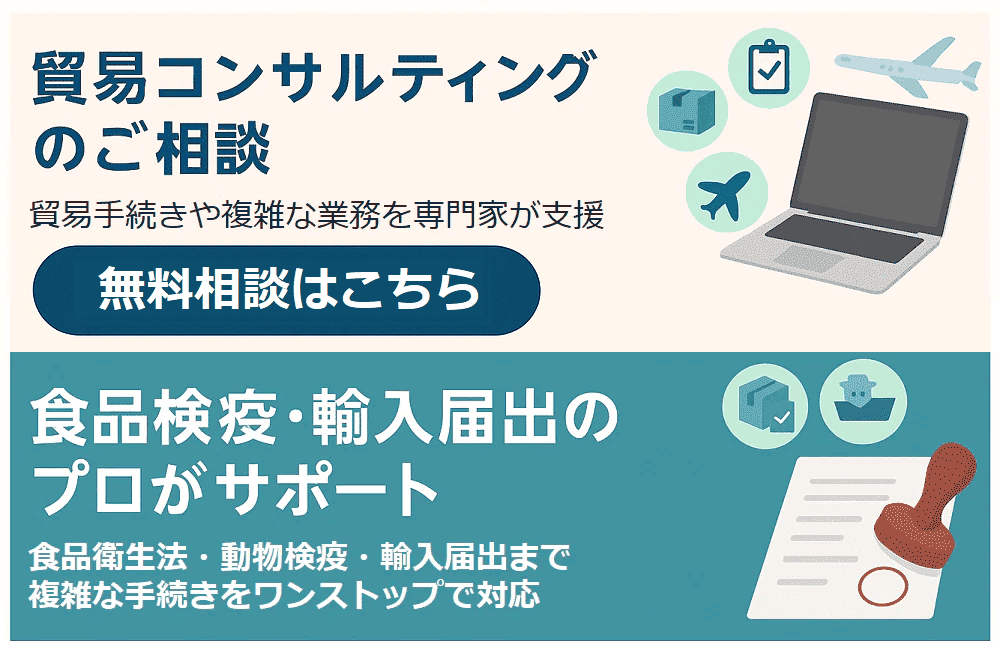冷凍かつお・まぐろ輸入ガイド
- 冷凍かつお・まぐろは2ヒスタミン等を含む魚介類の監視強化対象
- 主な輸入国は台湾・インドネシア・ベトナム・韓国・スリランカ(年別に上下)
- 想定リスクはヒスタミン基準、腸炎ビブリオ、サルモネラ汚染。
- 輸入前にHPLC/ELISAでヒスタミン検査、腸炎ビブリオ・サルモネラ選択検査を実施(自主検査として有効)
- 漁獲後、速やかに冷凍。輸送中-18℃以下維持、温度ロガーが必要
2025年度、厚生労働省の「輸入食品監視指導計画」では、冷凍かつお・まぐろ(生食用を含む)が重点監視品目に位置付けられました。背景には、国内の寿司・刺身需要の拡大に伴う輸入量の増加と、輸送・保存工程における温度逸脱や衛生不備による食中毒事故の懸念があります。
2024年の輸入統計によると、主な輸入先は台湾、インドネシア、ベトナム、韓国、スリランカで、過去5年間の違反報告はこれらの国に集中しています。
冷凍かつお・まぐろが輸入食品監視計画の重点品目に指定
ヒスタミン中毒
- 発生要因:漁獲後に適切な温度管理が行われないと、魚肉中の遊離アミノ酸からヒスタミンが生成されます。
- 基準目安:公的基準値も国際的にほぼ同様です。
微生物汚染のリスク
- 腸炎ビブリオ:低温管理が不十分な場合に増殖します。
- サルモネラ:加工施設での衛生管理不備により汚染が発生する事例があります。
法的枠組み
- 食品衛生法第11条:輸入時には規格基準への適合が義務付けられています。
- 厚生労働省通知:衛生証明書の取得や自主検査の実施を推奨しています。
違反時の措置
違反があった場合、廃棄、積戻し、または加熱用に限定した販売などの方法があります。
国別リスク傾向(2020〜2024の事例分析)
- 台湾:ヒスタミン基準超過の事例が複数発生。原因は漁獲から冷凍開始までの時間遅延。
- インドネシア:腸炎ビブリオ陽性検出例が多発。水揚げ港の衛生環境が課題。
- ベトナム:初期処理遅延によるヒスタミン生成の違反事例。
- 韓国:温度管理は比較的安定するが、衛生証明書記載内容との乖離が稀に見られる。
- スリランカ:過去にサルモネラ検出例あり。
輸入前にできるヒスタミン・微生物対策と検査方法
(1)輸入前の自主検査
- ヒスタミン:HPLCまたはELISA法でロット検査
- 微生物:腸炎ビブリオ・サルモネラを中心に選択検査
(2)漁獲後処理と冷凍工程
- 理想は漁獲後、速やかに血抜き・内臓除去・急速冷凍
- HACCP認証施設の利用と温度管理記録の提出確認
(3)輸送時の温度管理技術
- コンテナ内部を積込前に予冷(-20℃)
- 輸送中は-18℃以下を維持
- センサーや温度ロガーを二重設置(推奨)
- 電源断対策として予備発電機を搭載
違反事例と成功事例
違反事例
- 台湾産冷凍まぐろ:ヒスタミン超過 → 廃棄
- インドネシア産かつお:腸炎ビブリオ検出 → 積戻し
成功事例
- 漁獲後1時間以内に急速冷凍+輸送中温度変動1℃以内 → 命令検査回避
命令検査の流れと費用・期間の目安
- 発動条件:過去違反履歴、指定高リスク国、モニタリング違反時
- 工程:届出 → 検査指示 → サンプリング → 分析 → 結果報告
- 費用:1ロットあたり3〜8万円(項目により変動)
- 期間:概ね5〜10営業日
事前準備チェックリスト(冷凍かつお・まぐろ輸入版)
- 発注仕様書に「ヒスタミン検査済み」「-18℃以下での輸送維持」を明記
- 漁獲〜冷凍までの時間記録をサプライヤーから取得
- 温度ロガーで全ルートを記録・保管
- 検査結果・温度記録をロット単位で保管
実務者向けヒントと品質・温度逸脱防止策
- ヒスタミン発生抑制:漁獲後ただちに血抜き・内臓除去・氷冷
- 積込時チェック:コンテナ庫内温度を積込前に-20℃以下に予冷
- 温度変動対策:停電・機器故障リスクに備えた発電機・予備冷凍機の設置
- 顧客対応:生食用として販売する場合は検査証明書と温度管理記録をセット提供
- 港湾対応:混雑港よりも通関処理の早い港を選び、温度逸脱リスクを減らす
まとめ:冷凍かつお・まぐろ輸入を安全に行うためのポイント
- 冷凍かつお・まぐろはヒスタミン・微生物リスクが高く、2025年度重点品目に指定
- 漁獲後〜凍結までの時間と輸送温度管理が品質と通関リスクの分岐点
- 自主検査、温度記録、サプライヤー監査でリスクを最小化
- 証明書・温度管理記録を備えて市場での信用を確保

 この記事を登録
この記事を登録
 目次
目次