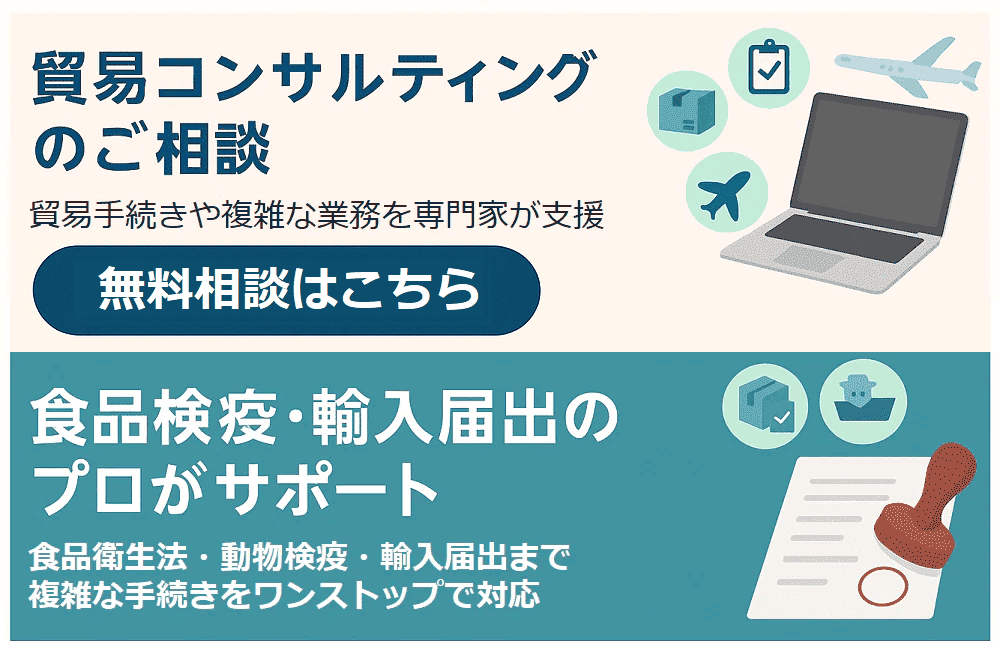緑茶(輸入原葉)輸入完全ガイド
茶は嗜好品でありながら、乾燥・加熱・焙煎など多段階の工程を経るため、残留農薬に加えて工程由来物質(アントラキノンや多環芳香族炭化水素:PAHs)が検出されるリスクがあります。さらに、ハーブブレンドでは原料の混成・粉砕により異物や他植物由来アルカロイドの混入にも注意が必要です。
この記事では、緑茶を輸入販売するときに必要な知識をご紹介していきます。
お茶輸入の基本と目的区分
海外からお茶を輸入する際は、まず輸入目的を明確にします。
- 個人使用目的:自分で飲むための輸入。販売は不可。
- 商売目的:国内販売用の輸入。輸入時から「販売用」として手続きを行い、食品衛生法や関税法などの審査を受けます。
この記事では商売目的での輸入に焦点を当て、規制・許可・リスク管理・実務手順を解説します。
関係法令と所管
お茶(緑茶・紅茶・ウーロン茶・ハーブブレンド等)の輸入は、以下の法令が関係します。
| 法令 | 所管 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 関税法 | 税関 | HSコード分類と関税徴収 |
| 食品衛生法 | 厚生労働省(検疫所) | 食品の安全性確認(残留農薬、カビ毒、異物混入など) |
| 植物防疫法 | 農林水産省(植物防疫所) | 害虫・病原菌の侵入防止(乾燥のみの茶葉が対象) |
| 薬機法 | 厚生労働省 | 薬効成分を含む場合の規制 |
HSコードと税率
お茶のHSコードは0902に分類されます。
- 0902.10:発酵していない緑茶(3kg以下)
- 0902.30:部分発酵茶(ウーロン茶等)
関税率は無税〜十数%。EPA適用国からの輸入では無税の場合もあります。消費税は軽減税率8%(飲用に限る)。20万円以下の少額貨物は簡易税率15%が適用される場合があります。
お茶輸入の手続きの流れ
1. 仕入先を選ぶ
- 使用農薬や加工工程が日本基準に適合しているか確認。
- ISO/HACCPなど衛生認証、検査証明を取得可能か。
2. 必要書類(食品衛生法)を用意する
- 食品等輸入届出書
- 原材料表(農薬・添加物・アレルゲン情報)
- 製造工程表(加熱・乾燥・焙煎・ブレンド工程)
- 製品カタログやラベル案 ※日本語または英語。他言語は和訳必須。
3. 関係機関での手続き
- 税関:HSコード・関税計算
- 食品検疫所:安全性確認(残留農薬、工程由来物質)
- 植物防疫所:必要な場合のみ
- 薬機法対象の場合は事前に輸入不可リスクを精査
4. 輸入許可取得
- 検査命令対応(命令検査、モニタリング検査)
- 不適合時は積戻し・滅却・再加工
5. 国内販売手続き
お茶の輸入許可が下りたら、日本国内で販売ができます。ここから先は、輸入後の販売時に関係する法律です。
- 食品表示法(原材料・アレルゲン・原産国)
- 景品表示法(虚偽・誇大広告禁止)
- 健康増進法(効能表示規制)
- 計量法(正確な重量表示)
- 有機表示は有機JAS認証必須
1.食品表示法
- 商品につけるラベルの内容を規制するための法律
- 管轄官庁:消費者庁
- 食品表示法の詳細
2.景品表示法
- 製品内容を誤認させて販売することを防ぐ法律
- 管轄官庁:消費者庁
- 景品表示法の詳細
3.健康増進法
- 健康に関する効果・効能を誤認させて販売することを防ぐ法律
- 管轄官庁:消費者庁
4.計量法
- 内容量の測り方について決める法律
- 管轄官庁:経済産業省
5.その他
有機やオーガニック表現:輸入したお茶を販売するときに「有機」などの表示をする場合は「有機と表示できる条件」を満たすこと求められます。何でも有機品とは表示できないため、ご注意ください。
効果・効能の表現規制:「このお茶を飲むと痩せる~」など、何かしらの効果効能をうたうことはできません。日本では、この効果・効能をうたえるのは「薬品」に指定されている物だけです。その他の物を販売するときに、効果効能をうたうと「薬機法違反」になるため、注意しましょう!
お茶の輸入に関するリスクと違反傾向
茶の輸入時は、下記のリスクがあります。しっかりと確認しましょう!
残留農薬
- 対象例:クロルピリホス、アセタミプリド、イミダクロプリド、ビフェントリン等
- 国別傾向:
- 中国:ネオニコチノイド系、クロルピリホス、アントラキノン
- インド:有機リン系・合成ピレスロイド系、PAHs
- スリランカ:焙煎設備由来PAHs、金属片混入
- ベトナム:残留農薬、表示不備
- ケニア:ピレスロイド系、小石・植物片混入
工程由来物質
茶葉の工程上、発生する危険性です。
- アントラキノン:乾燥燃料や煙の接触で生成
- ベンゾ[a]ピレン等PAHs:高温焙煎・燻乾で発生
異物・アルカロイド混入
他、以下の物も不純物として混入するリスクがあります。
金属片、小石、植物片、ピロリジジンアルカロイド等
茶の種類や加工方法にもこんなリスクがあり!
- 緑茶(不発酵茶):低温蒸熱処理により一部農薬が減少。
- 紅茶(発酵茶):発酵工程中の農薬分解は限定的。乾燥温度が高く、PAHsリスクが上がる可能性。
- ほうじ茶:高温焙煎で一部農薬濃度は低下するが、高温に伴うPAHs生成の管理が必要。
- ブレンドハーブティー:原料多様化に伴い農薬やアルカロイドの混在リスクが高く、原料別検査が必須。
健康影響とリスク評価
厚生労働省やFAO/WHOの合同食品添加物専門家会議(JECFA)の評価によると、見つかった残留農薬の多くは、一番高く検出された場合でも一日摂取許容量(ADI)の範囲に収まり、すぐに健康被害が出る可能性は低いとされています。
ただし、基準値を超えたり、複数の農薬が同時に残っている場合は健康リスクが高くなるため、輸入段階での厳しい管理が必要です。
国際・国内基準の活用
- 安全性確保のためには、国際的な農業・食品安全基準が指標となります。
- 生産段階ではGAP(適正農業規範)や有機JAS基準の導入確認
- 輸入時は日本の食品衛生法で定められた残留基準値(ポジティブリスト制度)との照合
- 加工工程ではHACCPやISO 22000等の衛生管理認証の活用
これらの基準や制度を組み合わせることで、国境を越えた食品安全管理が実効性を持ちます。
実務的な管理・検査のポイント
1. 残留農薬対策
- よく問題になる農薬例:クロルピリホス、アセタミプリド、イミダクロプリド、ビフェントリンなど。
- 産地ごとの農薬使用状況をリスト化し、日本の基準と照らし合わせます。
- 出荷前にISO17025認定の検査機関で分析します。
- 古い葉や茎が多いと農薬が残りやすいため、原料の葉の年齢や部位を指定します。
2. 工程由来物質(アントラキノン・PAHs)対策
- 乾燥に使う燃料(石炭・木材など)や煙との接触を管理します。
- 熱源を密閉し、必要に応じてフィルターを設置します。
- 焙煎の温度・時間は標準手順書(SOP)で管理。外注工場からは最新の環境測定結果を提出してもらいます。
- 試験的に焙煎したサンプルでアントラキノンやベンゾ[a]ピレンの検査を事前に行います。
3. 異物や有害成分(アルカロイド)混入対策
- 受け入れ時に、ふるい・風選・磁石・金属探知機で異物を取り除きます。
- ハーブブレンドの場合は、原料ごとに農薬やアルカロイド(例:ピロリジジンアルカロイド)を検査します。
- ブレンド後は品質を均一にするための検査計画を立て、ロットの定義と保存サンプルの管理を厳格にします。
4. 表示・規格管理
- カフェインの表示や抽出液換算のルールを社内で統一します。
- 香料やハーブの原材料名を正確に表示し、アレルゲンが混ざる可能性がある場合は注意表示を検討します。
- 「有機」などの任意表示を行う場合は、証明書やトレーサビリティ資料を必ず揃えます。
5. 検査命令時の効率化
- 定期的に輸入しているロットは、製造SOPと事前分析をセットで運用し、到着後の検査待ち時間を短縮します。
- 複数品目や共同輸入の場合は、リスクが最も高いロットを優先的に検査して、通関の停滞を避けます。
お茶を”輸入するとき”のリスクを小さくするコツ
- 契約の段階で安全条件を明確にする
仕入れ契約には、必ず「工程で発生する有害物質(アントラキノン・PAHs)の管理方法」や「乾燥に使う燃料の種類、間接加熱の使用」などを記載しておきます。 - 輸送中のニオイや湿気対策
コンテナ内の防臭・防煙対策として活性炭シートを使い、湿気対策には乾燥剤と換気(ベンチレーション)を組み合わせます。 - HSコードを早めに確定
発酵度(緑茶・紅茶など)やフレーバーの有無によってHSコードが変わるため、製品設計段階で決定します。 - 違反時の対応フローを決めておく
検疫所に連絡 → ロット隔離 → 再検査 → 輸出者通知 → 処理判断(廃棄・返送・再加工) → 社内報告の順で対応します。 - 事前検査でトラブル防止
残留農薬とアントラキノン/PAHsを同時に分析する事前検査パッケージを活用。1ロットあたり6〜8日、費用6〜9万円で結果が得られます。 - 輸送品質管理
40ftコンテナなら活性炭シート約10枚、乾燥剤は20kgを目安に使用。状況に応じて通風型や断熱型のコンテナを選びます。 - ロット追跡管理
バーコードやQRコードでロット番号と検査証明を紐付け、保存サンプルは2年以上保管します。 - 共同輸入時の効率化
過去の農薬検出率や違反履歴から最もリスクの高いロットを優先的に検査します。 - 厚労省データの活用
国別・品目別の違反傾向を年1回見直し、検査頻度や監査対象を調整します。
お茶の輸入”後”のリスクを小さくする方法
PL保険に入る
万が一、お茶を飲んだお客様に健康被害が出たときの損害賠償リスクを減らすために加入しておく保険です。治療費や慰謝料の負担を軽くできます。
ロットを追跡できるように管理する
バーコードやQRコードでロット番号と検査証明をセットで記録します。もし問題が起きても、どのロットかすぐに特定できるようにし、サンプルは2年以上保管します。
輸送中の品質を守る
コンテナの中に活性炭シートや乾燥剤を入れてニオイや湿気を防ぎます。さらに、断熱や通風機能のあるコンテナを使うことで、温度や湿度の変化による品質劣化を防ぎます。
まとめ
以上、お茶を輸入するときに必要なポイントをご紹介してきました。お茶を輸入するときは、個人用なのか、販売用なのかによって、輸入に関する規制が違います。まずは、どちらの目的で輸入するのかをハッキリさせましょう。販売目的で輸入するときは、輸出者からお茶に関するいくつかの資料を取り寄せて、食品衛生法をクリアできるように準備をする必要があります。
仕入先監査では「畑(使用農薬・収穫管理)」「工場(乾燥・焙煎・煙管理)」「ブレンド(均質化・トレサビ)」の三点を必ず現地確認すること。到着後は工程由来物質のスポット検査を組み合わせ、継続ロットでデータを蓄積し基準化します。
- 茶は残留農薬+工程由来物質の二重管理が必須
- 乾燥・焙煎のSOPと燃料管理を監査・契約で担保
- ブレンド品はロット定義と保存サンプルを厳格化
- 商売目的輸入は食品衛生法・関税法・必要に応じ植物防疫法や薬機法が関係
- 国別・工程別リスクを踏まえた事前検査が違反回避の鍵
- 書類整備、工程監査、輸送・保管管理を徹底し、輸入から販売までのリスクを一貫管理することが必須

 この記事を登録
この記事を登録
 目次
目次