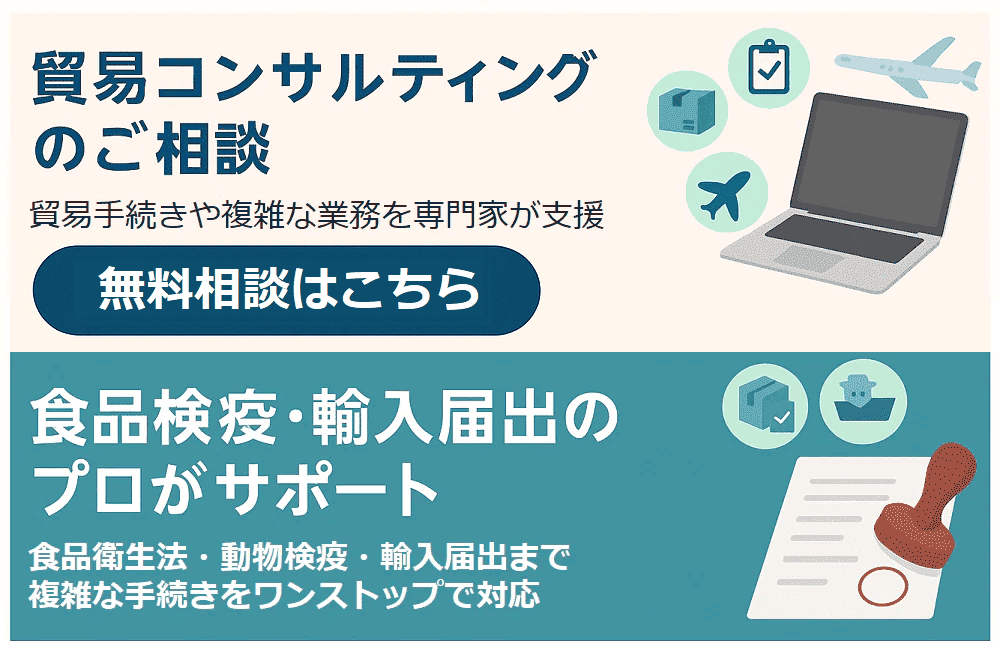カシューナッツ輸入の現状とリスク
- カシューナッツはカビ毒(総アフラトキシン10 µg/kg、総量15µg/kg)、残留農薬、異物混入が三大リスク。
- 原料水分5%以下、雨季収穫や低グレード品はロット検査と証明書添付を徹底。
- インド産カシューナッツのクロルピリホスで検査命令
- 異物防止は金属探知機・輸送時は乾燥剤・温湿度ロガーを使用する。
- 国別違反例(インド、ベトナム、コートジボワール等)を踏まえ、輸出国ごとの重点管理と契約書での基準適合条項化を行う。
カシューナッツは菓子、惣菜、ナッツミックスなど幅広い食品に利用され、日本でも需要が高い輸入品です。しかし、輸入時には以下の三大リスクが常に伴います。
- カビ毒(アフラトキシンB1・総アフラトキシン)
- 残留農薬
- 異物混入

特に厚生労働省は、ナッツ類の一部を重点監視対象としたことがあります。
カシューナッツ特有のリスク要因
カシューナッツは殻にカシューオイルという強い酸性物質を含み、皮膚炎などを引き起こす可能性があります。そのため、多くは輸出前に現地で殻を除去しますが、この工程が不衛生だとカビ毒汚染や異物混入が発生しやすくなります。さらに、乾燥工程の管理不足や保管中の湿気がカビ毒発生の要因となります。輸送・保管中には害虫防除のための農薬使用による残留事例も報告されています。
品質管理とリスク対策
1. カビ毒管理
- 原料の水分は8%以下に保つ
- 出荷前にアフラトキシンB1と総アフラトキシンを分析
- 雨季に収穫したものや低グレード品はロットごとに検査し、証明書を必ず添付
2. 残留農薬対策
- 輸出国で使われる農薬リストを入手し、日本の基準と照合
- 特にネオニコチノイド系、有機リン系農薬は重点確認
- ISO17025認定の検査機関でロットごとの分析を推奨
3. 異物混入防止
- 割れや欠けを除く工程に金属探知機やX線検査機を導入
- 手作業選別の衛生監査を定期的に実施
- 焙煎工程の温度・時間を標準化し、異物混入を防止
4. 表示・規格確認
- 加工形態(生、ロースト、塩味など)をはっきり表示
- アレルゲン表示や交差汚染の注意書きを記載
- 最終加工国の原産国名+要件該当時に原料原産地表示
5. 輸入時に必要な書類
- アフラトキシン分析証明書(B1と総量)
- 残留農薬分析証明書
- 異物検査記録(X線・金属探知)
- 原産地証明書、加工国証明書
- 輸送時の温湿度記録(ロガーデータ)
最新の規制動向と追加リスク事例
近年、カシューナッツに関する規制やリスク管理は国際的にも変化しています。消費者庁では、食品表示基準の見直しの一環として、カシューナッツを含むナッツ類のアレルギー表示義務化を検討しており、今後は輸入時点での明確なアレルゲン管理と表示が一層重要となる可能性があります。
異物混入の原因は加工工程だけでなく、流通段階の梱包材破損や輸送中の事故によっても発生します。近年では、割れカシューナッツに錠剤様異物が混入し自主回収に至った事例もあり、形状や等級を問わず全ロットでの異物検査体制が求められます。
また、厚生労働省の基準では、総アフラトキシン10 µg/kgを上限値としており、HPLC(高速液体クロマトグラフィー)やELISA法などで検査が行われます。輸入業者は分析証明書に試験方法の記載があるかを確認することが望まれます。
残留農薬の違反事例では、クロルピリホスやプロフェノホス(有機リン系)、アセタミプリドやイミダクロプリド(ネオニコチノイド系)などの検出が報告されています。これらの農薬名と日本の基準値を事前に輸出国のサプライヤーと共有し、適合証明書を添付してもらうことが違反防止の鍵となります。
実務TIPS
- コンテナ輸送時は、乾燥剤と温湿度ロガーを使用する
- 契約書に「カビ毒・農薬残留基準適合」「異物混入防止管理」条項を盛り込む
- HSコードは殻なし・生・ローストなど形態で分類が変わり、税率や検査項目も異なる
国別違反傾向(過去事例)
- インド:総アフラトキシン超過、異物混入(植物片)
- ベトナム:総アフラトキシン超過、農薬残留
- コートジボワール:異物混入(金属片)、カビ毒検出
- ブラジル:総アフラトキシン超過、プロフェノホス残留
- モザンビーク:アフラトキシン汚染、乾燥不十分によるカビ臭
実行ポイントまとめ
カシューナッツ輸入では、カビ毒・残留農薬・異物混入という三大リスクを輸出国ごとに管理することが不可欠です。原料調達から加工、輸送まで一貫して監査し、雨季収穫や低グレード品は厳格なロット管理と証明書添付を徹底しましょう。(推奨管理)厚労省の統計データを活用し、国別・品目別の重点管理を行うことで、違反リスクを最小限に抑えられます。

 この記事を登録
この記事を登録
 目次
目次