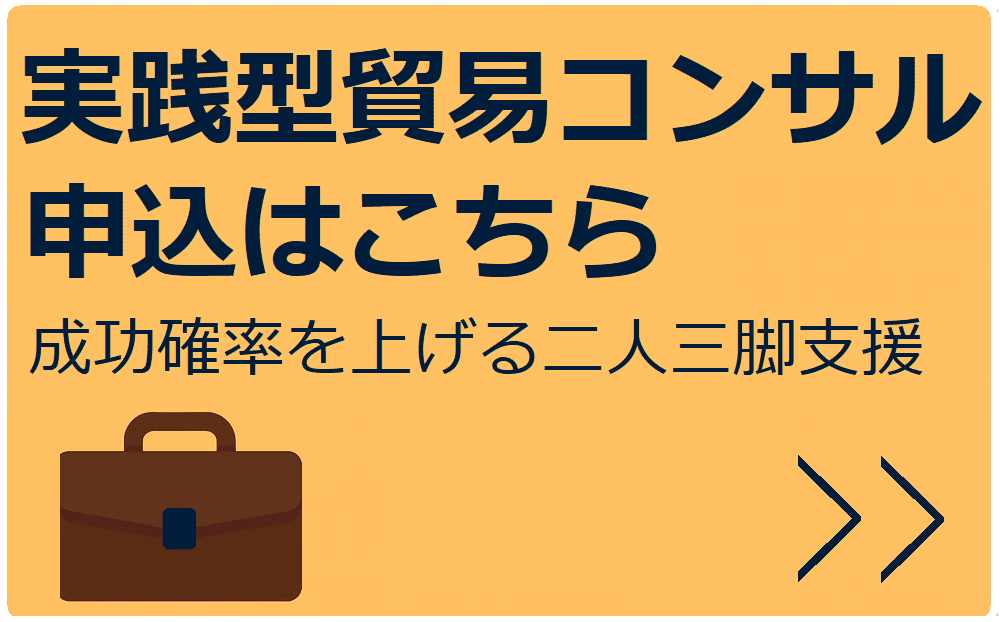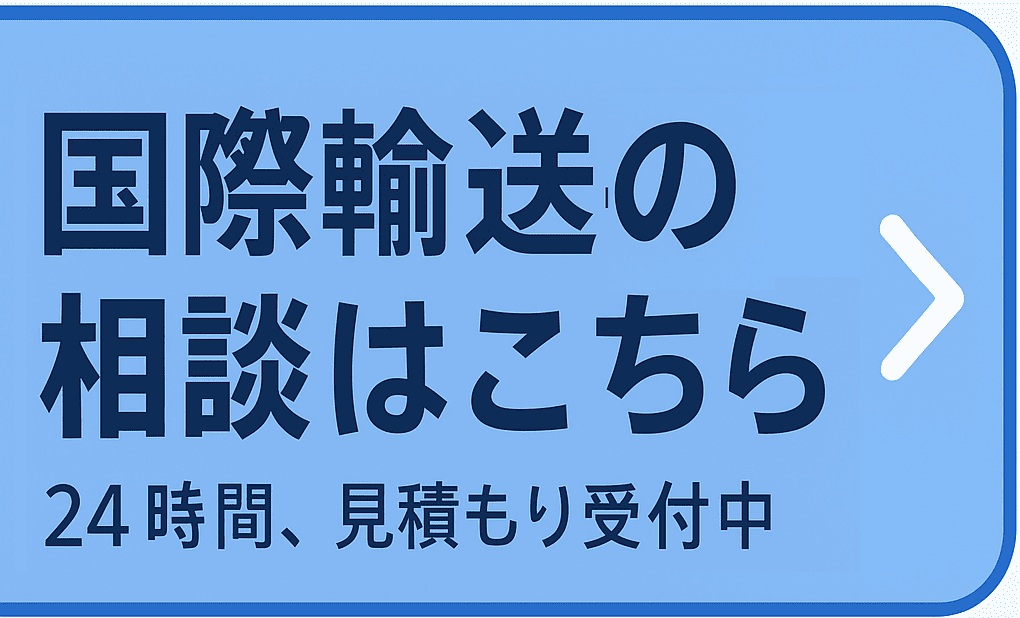オンラインプラットフォーム上の取引は「どこの裁判所で裁かれる?」
- オンライン販売で能動的に顧客を狙うと、相手国裁判所で訴えられるリスクが高まる
- プラットフォーム運営者も「積極的役割」があれば免責が狭まり、差止め対象になる。
- ブロック後の接続継続は米CFAA違反リスク—停止要請に従うことが必須。
この記事で分かること
海外のお客さんとAmazonやeBay、SNSなどを通じて商品を売買する時、もしトラブルになったらどこの国の裁判所で争うことになるのでしょうか。実は、これが勝負の分かれ目になることが多いのです。
この記事では、アメリカの会社と海外の人たちが実際に裁判で争った重要な事例を、裁判所の公式記録をもとに調べました。そして、日本の中小企業の皆さんが実際に使える判断基準をまとめました。
重要な結論
調査の結果、以下の3つのポイントが明らかになりました。
1.特定の相手を狙った営業活動は危険
以下のような行動を取ると、相手の国で裁判を起こされるリスクが高まります。
- 特定の顧客に電話で営業をかける
- 個別に配送方法を提案する
- 現地での商品受け渡しを行う
- その地域に特化した広告を出す
2.積極的な販売活動は責任を重くする
- 大量の商品を出品する
- 広告を最適化して販売を伸ばそうとする
- その他の能動的な販売活動

これらの行為は、プラットフォーム(Amazon等)や出品者の法的責任を重くする傾向があります。
3.不正なアクセスはアメリカの法律で厳しく処罰される
アクセスを制限された後も接続を続ける
これらの行為は、アメリカのCFAA(コンピューター不正アクセス禁止法)などで違法とされやすく、厳しい処罰の対象となります。

要するに: 海外取引では「どこまで積極的に販売活動をするか」と「どこで裁判になるリスク」のバランスを考えることが重要です。売上を伸ばそうとするほど、海外での裁判リスクも高まることを覚えておきましょう。[F1,F3,F5]
何が起きた?
1) Yahoo! v. LICRA(米・第9巡回, en banc 2006)
背景:フランスの裁判所は、Yahoo!(米国)のオークションに出品された●チス関連商品の表示を、フランス法(反ヘイト規制)に基づき差し止め、違反金の支払いを命じました。Yahoo!は米カリフォルニア北部地裁に「フランス判決は米国内で執行できない」との確認判決を求めました。
主張:フランスの団体(LICRA等)は「米国の裁判所には我々への管轄権がない」と反論しました。
判断:第9巡回大法廷は、地裁に管轄がある前提を認めつつも、「事件はまだ成熟していない」などの理由で訴えを却下しました。裁判官の判断理由は分かれました[F1]。
要旨(25字):越境表現+外国判決の米執行、確認訴訟は却下[F1]。
学び:海外で差し止めや警告を受けても、米国での確認訴訟がすぐ認められるとは限りません。現地当局や団体の働きかけ(書簡送付・代理人活動)が米国の管轄発生に十分かどうかは、その接触の質に左右されます[F1]。
2) L’Oréal v. eBay(EU司法裁判所, 大法廷 2011, C‑324/09)
背景:eBay上でロレアル(仏)の商標が付いた化粧品がEU域内向けに違法出品される問題が発生。ロレアルが英国高等法院を経てEU司法裁判所(CJEU)に付託しました。
判断:CJEUは以下のように判断しました。[F3,F4]
- 商標権者はプラットフォーム運営者にも侵害防止の差し止めを求められる
- 運営者が「積極的役割」(出品の最適化・広告での販促など)を担う場合、Eコマース指令14条のホスティング免責の適用が狭くなる
- EU域内消費者を狙った提供の有無も審理要素となる
要旨(25字): 運営者に差止可能/能動(積極的な)関与で免責は制限される。
学び:大量出品の最適化や地域ターゲット広告は、新たな責任リスクを生みます。販売拡大と訴訟リスクは常にトレードオフです。
失敗の原因
海外取引でトラブルになったケースを分析すると、多くの企業が同じような失敗をしていることが分かりました。以下の3つのパターンに当てはまらないよう注意しましょう。
1. 特定地域を狙った営業の痕跡を残してしまう
- その地域だけに向けた広告を出す
- 「EU向け」「ヨーロッパ仕様」などの表記を使う
- 現地の言語でFAQ(よくある質問)を作る
- その国専用の配送規約を作る

これらは「その地域のお客さんを意図的に狙って商売した」という証拠になってしまいます。そのため、その地域の裁判所で裁判を起こされたり、販売を禁止されたりするリスクが高まります。
2. 「親切な一押し」が裏目に出る
- 電話で商品について詳しく説明する
- 自社で配送方法を手配・提案する
- 現地に行って商品の設置や確認作業をする
- その他のオフラインでの追加サービス

最初はオンラインだけの取引でも、このような「親切な追加サービス」を重ねると、「相手の地域に積極的に関わっている」と判断されやすくなります。過去の裁判例(Erwin事件やBoschetto事件など)でも、このパターンで問題になっています。
3. アクセス制限を無視してしまう
運営者から「アクセスを停止してください」と要請され、技術的にもブロックされた後に、それを回避して接続を続けること

「ユーザーが同意していた」「利用者の承認があった」と主張しても、運営者のブロックを無視すると、アメリカのCFAA(コンピューター不正アクセス禁止法)違反に問われる可能性があります。これは完全に「赤信号」の状態です。
貿易実務者が学ぶべき4つのポイント
1.出品・広告の粒度管理
EUや各国の消費者を狙う表現(言語・配送地・価格)はログを保存。テスト配信も記録し、「どこを狙っていないか」まで説明できるようにします[F3]。
2.“追加接点”を設計して残す
配送・引渡地・検収地を契約やインボイスに明示(英語原語:place of performance)。不要な電話勧誘や断定表現は避け、やり取りはプラットフォーム内メッセージに限定します。
3.技術的制限を越えない
停止要請(cease-and-desist)があれば即停止し協議。IPブロック回避やスクレイピングはCFAA等のリスクがあるため、必ず法務確認を行います[F5]。
4.プラットフォームとの役割分担
自社が能動的に最適化・販促する場合は監視・削除体制(notice-and-takedown)を強化。受動的に徹するなら、“受動性”を示す設計証拠(UI制約・審査フロー)を残します[F3]。
今日からやることチェックリスト
- 広告運用:地域ターゲティングの設定書と配信ログを保管(いつ/どこを狙ったか)。
- 契約・インボイス:配送・引渡・検収の場所(place of delivery/acceptance)を英語原語併記で明示。
- コミュニケーション:電話よりプラットフォーム内のテキスト。断定的品質表示(mint等)は根拠資料とセット。
- 技術遵守:ブロック通知が来たら即停止—API等の正規ルートに切替。
- 削除体制:侵害通報の受付~削除~再発防止の標準手順(SOP)をファイル化。
インサイト

売上拡大のために“能動的”に動けば、その分“管轄と責任”を引き寄せます。
ターゲティング広告、在庫最適化、自社手配配送といった行為は、買主地やEU域内などに「足跡」を残すことになります。どこまで能動化するかを事前に設計し、証拠として残す仕組みを作っておけば、狙った市場だけでなく想定外の地域で訴えられるリスクも、自ら選んで管理できるようになります[F1, F3, F5]。
要点まとめ(箇条書き)
- 狙い撃ち(targeting)や追加接点は管轄を引き寄せる。
- 運営者の能動的関与は免責を狭め、差止の対象になり得る。
- ブロック後の接続継続はCFAA違反リスク—停止要請に従う。
- 販売拡大と訴訟露出はトレードオフ—能動化の度合いを設計・ログ化。

※本記事は法律的助言ではなく、貿易実務の参考情報です。
Factリスト
- [F1]U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit (en banc):Yahoo! Inc. v. La Ligue Contre le Racisme et l’Antisemitisme, 433 F.3d 1199, No. 01‑17424, Decided Jan. 12, 2006(フランス団体に対する地裁の管轄判断を巡りつつ、成熟性等の問題で確認訴を退け)。9th Cir.公式PDF:https://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/opinions/2006/01/11/0117424.pdf
- [F2](参考・地裁)U.S. District Court, N.D. Cal.:Yahoo!, Inc. v. LICRA, 145 F. Supp. 2d 1168(2001)/169 F. Supp. 2d 1181(2001)(管轄肯定・米国内執行不可の判断)。公式転載(CourtListener等)
- [F3]Court of Justice of the European Union (Grand Chamber):L’Oréal SA and Others v. eBay International AG and Others, Case C‑324/09, Judgment 12 July 2011(商標権者は運営者に差止請求可、能動的役割でホスティング免責が狭まる)。EUR‑Lex公式:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A62009CJ0324
- [F4]CJEU Case Info:C‑324/09(手続・文書一覧)。CURIA公式:https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B324%3B9%3BRP%3B1%3BP%3B1%3BC2009%2F0324%2FJ&language=en%2F1000
- [F5]U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit:Facebook, Inc. v. Power Ventures, Inc., 844 F.3d 1058, No. 13‑17102, Filed July 12, 2016(ブロック後接続はCFAAのwithout authorizationに該当し得る)。9th Cir.公式PDF:https://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/opinions/2016/07/12/13-17102.pdf
- [F6]GovInfo(米政府公開DB):Facebook, Inc. v. Power Ventures, Inc., USCOURTS‑ca9‑13‑17154(関連文書アーカイブ)。https://www.govinfo.gov/app/details/USCOURTS-ca9-13-17154/USCOURTS-ca9-13-17154-0
全期間の人気記事(貿易トラブルカテゴリ)
24時間の人気記事(貿易トラブルカテゴリ)
判例トラブル一覧

 この記事を登録
この記事を登録関連記事
基幹記事
貿易学習コースの一覧
分野別記事
カテゴリの一覧
関連記事
◆スポンサード広告


 目次
目次