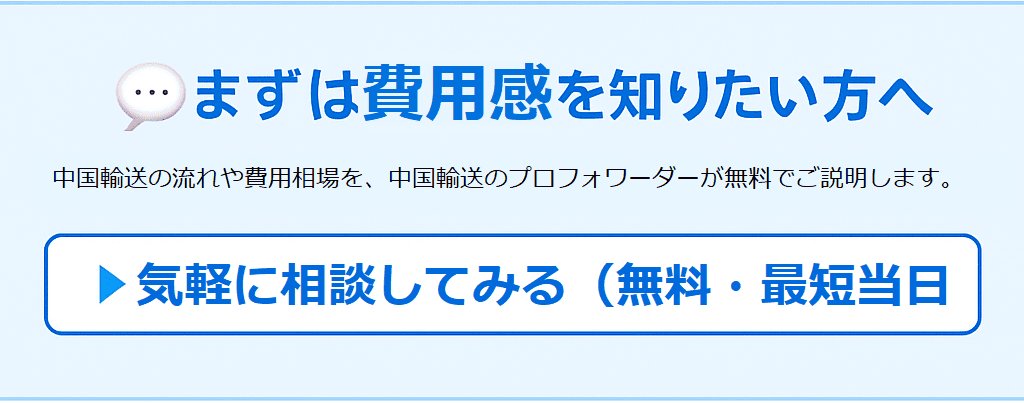「CTRL」+「D」を押すと、HUNADEをブックマークできます!
なぜ”高速化”は小さな積み重ねで決まる?
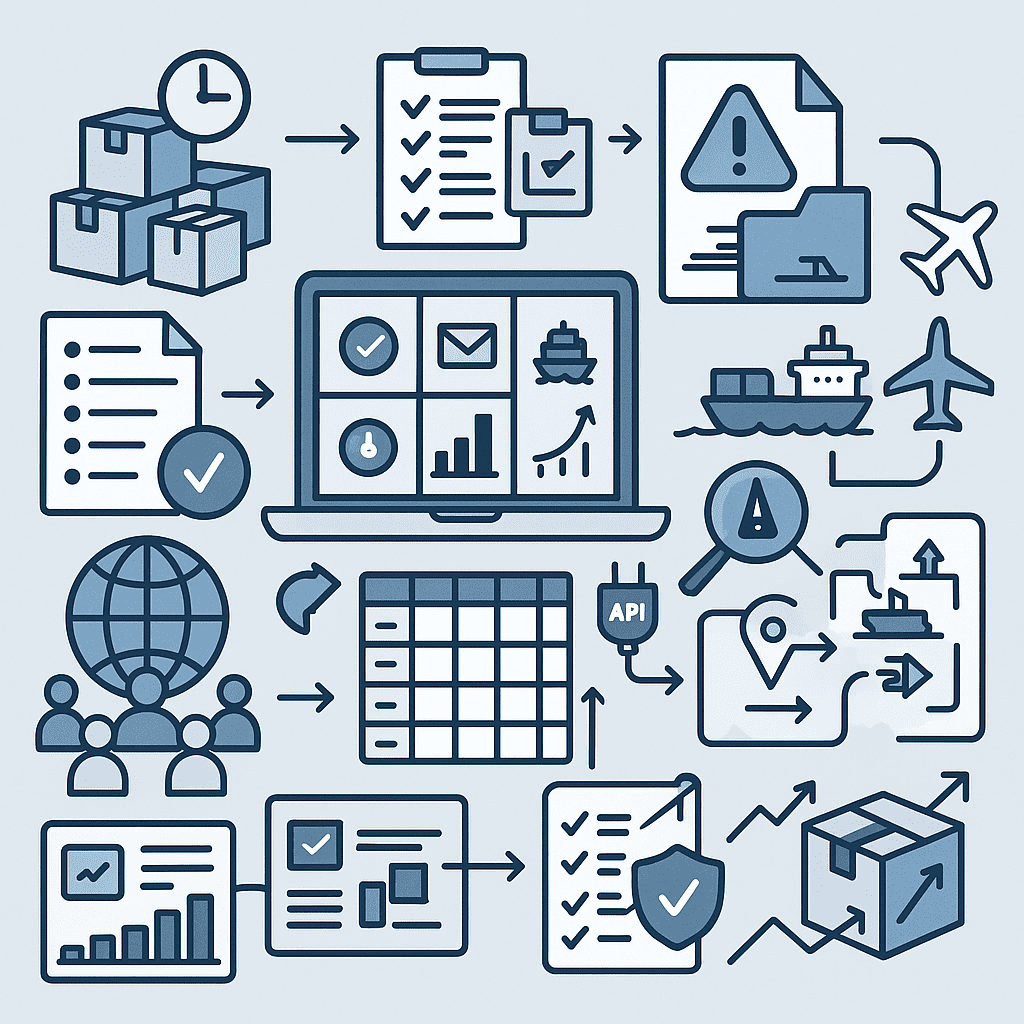
はじめに|“速さ”は小さな作業の積み重ねで決まります
中国から日本へのリードタイム短縮は、船や飛行機の速度ではありません。情報の正確さ、判断の早さ、連携のうまさで決まります。遅れの多くは、梱包設計、ラベル貼り、SI提出、カット管理、通関書類準備、港での搬出予約など、小さな作業の遅れが積み上がって起きます。
このページは、中国輸送の実務担当者が「明日から回せる」形で、工程別の高速化ノウハウをご紹介していきます。
輸送を早くするための全体の流れをつかもう
まずは、どの工程でスピードの差が生まれるのかを理解することが大切です。以下は、一般的な海上輸送の流れです。
工場出荷 → 船積書類作成 → 通関申告 → 出港 → 日本到着 → 通関完了 → 搬出・納品
それぞれの工程に“高速化のポイント”があり、どこか一つでも乱れると全体が遅れます。記事の後半では、各工程での改善策を順に紹介します。まずは基本用語をおさらいしておきましょう。
用語ミニ辞典(1行で理解)
まずは、記事で登場する用語の解説です。
- SI:船積指示書。船社やNVOCCへ出す積付・本船情報です。
- VGM:Verified Gross Mass。総重量の確定申告です。(SOLAS改正で義務化&VGM未提出は本船積み不可。)
- AFR:日本向け海上コンテナ貨物の事前情報。本船の積地出港の24時間前までに電子提出(JP24)
- D/O:荷渡指図書。eD/Oはその電子版です。
- CY/CFS:コンテナヤード/混載倉庫。CY直送は積替えを減らします。
- AEO通関業者:税関の認定業者。AEO特例により通関手続の簡素化・迅速化のメリットがあります(検査免除を意味しません)。
- 到着前審査で審査済+他法令(関税法70条)クリア、Sea Waybill等で原本待ちなし、eD/Oや搬出予約を前倒し――の条件が揃うと当日搬出が現実的になります。
これらの用語をなんとなくでも理解しておくと、次の説明がスムーズに入ってきます。難しい言葉が出てきたら、「今はなんとなくの理解でOK」と思って読み進めてください。
今日から始める「15分の高速化習慣」
輸送を早くするには、まず現状を“見える化”することから始めましょう。以下の手順で、社内でのスピードを数字で把握できます。
- 「物流KPI」スプレッドシートを複製(社内共通フォルダに保存)
- フォワーダーポータルの出港一覧CSVを貼り付け
- ピボットで「CUT遵守率」「到着当日出荷率」を自動計算
- 毎朝9時に更新し、URLをチームに共有
たったこれだけでも、どこにボトルネックがあるのかが一目でわかるようになります。
遅延の原因(ボトルネック)を5つに分けて整理しよう
数字を見える化したあとは、「なぜ遅れているのか」を明確にします。原因は大きく分けて5つです。
- 情報管理 – 書類の提出漏れや承認遅れが発生しやすい。
- 物理作業 – 梱包やラベル貼りの不統一がボトルネックに。
- 締切管理 – CUTやAFR提出の逆算が曖昧。
- 通関書類 – HSコード誤りやB/L原本待ちによる申告遅延。
- 日本側の搬出管理 – D/O発行待ちやトラック確保の遅れ。
1. 情報管理
- 課題:SI・Invoice・PLの提出漏れ、形式のバラつき、承認待ちの長期化。
- 最短化案:書類のテンプレを固定する。共有フォルダに「到着前」ディレクトリを作成し、提出物(書類)を一本化。
最初に整えるべきは「情報の流れ」です。SI・Invoice・PLなど、提出書類がバラバラなフォーマットで回っていると、承認待ちが長期化します。これを防ぐには、書類のテンプレートを固定し、共有フォルダに「到着前」ディレクトリを設けて提出物を一本化するのが効果的です。
また、Google DriveやNotionを活用して「最新書類はどれか」をチーム全員が即確認できるようにしましょう。こうすることで、メール検索や添付ファイルのやり取りが大幅に減り、確認作業もスピードアップします。
2. 物理作業
- 課題:梱包仕様の不統一、ラベル欠落、バンニング待ちが発生しやすい。
- 最短化案:出荷チェックA4(写真の並べ順つき)で“出す前”に完結
梱包仕様やラベル貼りが統一されていないと、現場での混乱が起きやすくなります。たとえば「出荷前にA4チェックシートを使い、写真の順番通りに確認する」だけでも、積み間違いやラベル漏れを防げます。
さらに、南部の多湿地域ではプラパレット、内陸の乾燥地域では合板パレットを使うなど、地域条件別に最適な梱包方法をマニュアル化すると安定します。ここでは「出荷する前に確認を終わらせる」ことが鍵です。
中国輸送を止めない梱包・ラベル・バンニング標準化の実務ポイント
3. 締切管理
- 課題:CY搬入、VGM、AFRなどのカット逆算が曖昧になりやすい。
- 最短化案:カレンダーにカット逆算テンプレを登録。祝日前は自動で3営業日前倒し。
輸送が遅れる原因の多くは、「逆算のずれ」です。CY搬入、VGM、AFRなど、すべての締切が曖昧だと、1件の遅れが連鎖していきます。カレンダーにカット逆算テンプレートを登録し、祝日前は自動で3営業日前倒しにするルールを設定しましょう。
また、社内で「CUT日の守り方」を共有し、トラブル時に誰がどの締切を再設定するかを明文化しておくと、緊急時でも混乱しません。
中国輸入の当日搬出を実現する方法|予備審査・eD/O・搬出予約の実務ノウハウ
4. 通関書類
- 課題:HSコード誤り、B/L原本待ち、申告内容の不一致になることが多い。
- 最短化案:SKU申告マスターを作り、品名・HS・材質・原産国を固定。通関業者レビューを月末で一括管理する。
通関書類の遅れは、最終段階での大きな時間ロスにつながります。SKU単位での申告内容を固定化した「申告マスター」を作り、品名・HSコード・材質・原産国を定義しておくと、申告の誤りを防げます。
また、通関業者と月1回のレビューを行い、過去の修正履歴を整理しておくことも大切です。これにより、申告の再提出や照会対応の時間を削減できます。
中国輸送を遅らせないノミネーション活用と書類・カット管理の実務
5. 日本側の搬出シーン
- 課題:D/O発行待ち、搬出予約システムの操作遅れが発生する。
- 最短化案:eD/Oを標準化。ETA確定時点で搬出予約とトラック確保を前日までに完了
最後のボトルネックは「日本側での搬出予約」です。D/O発行待ちやトラック確保の遅れが出やすい部分です。これを解決するには、電子D/O(eD/O)を標準化し、ETA確定時点で搬出予約とトラック手配を前日までに完了させるのが理想です。
さらに、港湾や通関の進捗を一元管理できるツール(例:DIGISHIP)を導入すると、搬出準備の進行状況がリアルタイムで確認でき、チーム全体の動きがスムーズになります。

いずれも、標準化(SOP化)とデジタル化で解決可能です。
この学習コースを読まれましたか?
高速化を“見える化”するKPIの設計と運用
改善を続けるには、「どれくらい速くなったのか」を数値で確認できる仕組みが欠かせません。ここでは、輸送のスピードを客観的に測るKPI(重要業績指標)の設定例を紹介します。
代表的なKPI指標
| 指標名 | 内容 | 目的 |
|---|---|---|
| 到着当日出荷率 | 当日に搬出できた件数 ÷ 総件数 | 実際のリードタイム短縮効果を把握 |
| CUT遵守率 | 締切を守った件数 ÷ 総出港件数 | スケジュール管理の精度を測定 |
| eD/O比率 | 電子荷渡指図書の利用率 | 書類電子化の進捗確認 |
| CY直送率 | 工場から港へ直送した件数 ÷ 全出荷件数 | 積替えロスの削減効果を把握 |
| 検査率 | 検査対象件数 ÷ 総申告件数 | 品質管理の安定度を確認 |
| 平均リードタイム(LT) | 出港から納品までの日数 | 輸送の総合的なスピードを測定 |
これらをGoogle Data StudioやPower BIにまとめることで、毎朝の更新と共有が簡単になります。特に「CUT遵守率」と「当日出荷率」は最もわかりやすく、チームの意識を高める指標です。
まずは“見える化”から
はじめはExcelやスプレッドシートでも十分です。週1回でも集計を続けることで、どこに遅れが発生しているかが自然に見えてきます。スピード改善の第一歩は、数字で自分たちの動きを可視化することです。
トラブルが起きたときの対応力を高める
どんなに準備を整えても、輸送中のトラブルは避けられません。台風による遅延、港でのストライキ、通関システムの障害など、予期せぬ出来事に備えておくことが大切です。
1. 早期発見の仕組みを整える
MarineTraffic、PortCall Monitor、Windyといったツールを活用し、船の位置や天候を自動で監視します。SlackやTeamsに連携すれば、異常が起きたときに自動通知を受け取ることができます。
2. 代替手段をあらかじめ決めておく
主要港(上海・寧波・青島など)ごとに3社ほど代替フォワーダーを登録し、契約書には「緊急時の便変更は承認不要」と明記しておくとスムーズです。例えば、上海からの便が欠航した場合、すぐに大阪経由や航空便への切り替えが可能になります。
3. 具体的な対応手順を明文化する
| トラブル内容 | 対応フロー |
| 通関システム障害 | NACCS障害情報を確認 → 税関に連絡 → 暫定取扱要領に基づく紙申告へ切替 |
| 港のストライキ | 管理局発表を確認 → 別港に振替 → 工場へ積込停止の連絡 |
| 台風接近 | 船社スケジュールを確認 → ETA再計算 → 倉庫搬入延期を指示 |
| 船便延期(ロールオーバー) | 新しいB/L番号登録 → 通関書類差替え → 顧客へ新ETA連絡 |
また、SlackやLINE WORKSに「連絡網テンプレート」を設定しておくと、誰が何分以内に行動するかを即確認できます。
| 担当 | 代替担当 | 連絡手段 | 応答SLA |
| フォワーダー責任者 | ロジ担当マネージャー | Slack/電話 | 15分以内 |
| 通関業者担当 | 通関代理人 | メール/LINE WORKS | 20分以内 |
| 工場出荷責任者 | 生産管理者 | 30分以内 |
トラブル時に動ける人を決めておくだけでも、対応スピードは大きく変わります。
教育と仕組みで“速さ”を継続させる
高速化を一時的な取り組みで終わらせないためには、社内教育と運用ルールの共有が欠かせません。
1. 手順書の整備
まずは、誰が見ても同じ作業ができるように、標準手順書(SOP)を作ります。
- 手順書01:配送業者の指定(FOB/FCA条件+指定フォワーダー+締切明記)
- 手順書02:梱包・ラベル統一(合板パレット・統一サイズ・2面ラベル)
- 手順書03:書類の早期準備(SIテンプレ+Sea Waybill+電子署名)
- 手順書04:到着前の搬出予約(到着前申告+eD/O+前日スロット確定)
2. 教育ツールの導入
新人や外部スタッフでもすぐ理解できるよう、次のような仕組みを取り入れましょう。
- LINE WORKSのチェックリスト機能で、作業完了をリアルタイム共有。
- 「5分でわかる動画マニュアル」で各工程の流れを短く説明。
- 現場QRコードから手順書を開けるようにし、スマホでも確認可能に。
これにより、経験の差に関係なく、全員が同じスピード感で業務を進められます。
まとめ|“速さ”を生むのは、特別な仕組みではなく日々の整え方
輸送を速くするために必要なのは、最新の船やシステムではありません。重要なのは、毎日の小さな作業を丁寧に整え、誰でも同じルールで動ける環境を作ることです。
- 締切を守る仕組みをカレンダーで自動化する
- 書類・梱包・搬出方法を標準化する
- データでスピードを“見える化”し、改善を続ける
- トラブル対応と教育を仕組み化する
この4つを徹底すれば、輸送のスピードは確実に上がります。今日から少しずつ、小さな改善を積み重ねていきましょう。
大切なポイントのまとめ
- 配送を速くするには、輸送手段ではなく、締切の設計と情報共有の工夫が重要
- 約束事とダッシュボードで責任と期限を一か所で管理
- 梱包・ラベルを統一して物理的なロスを削減
- デジタル連携+進捗の見える化で改善を自動的に継続
- リスク分散と代替ルート設計で突発的な遅延にも強い配送網を構築
中国輸送の基本コース
中国輸送の”高速化”コース

 この記事を登録
この記事を登録
 目次
目次