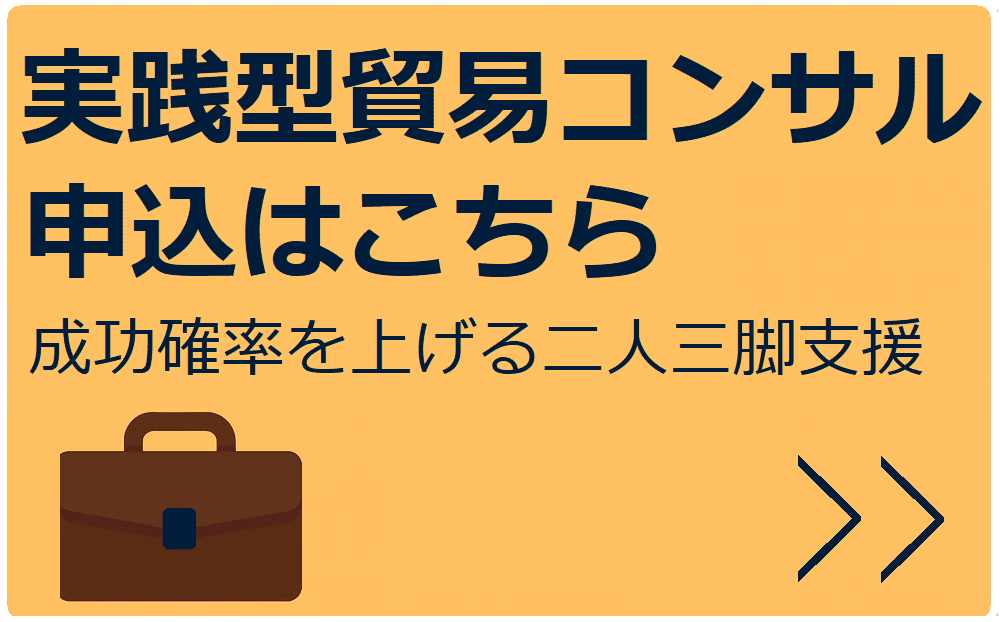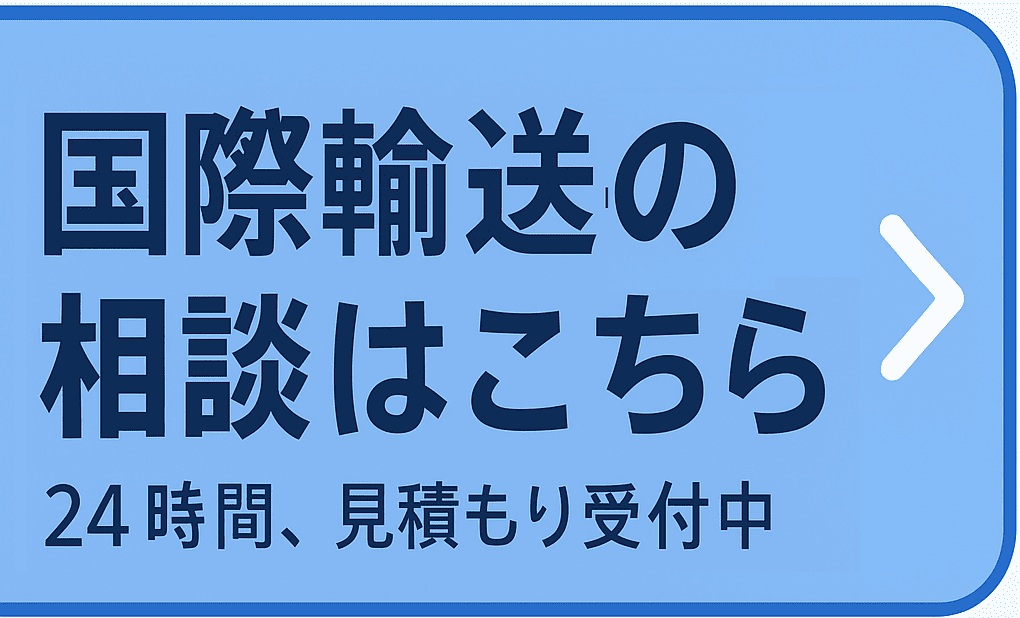中国海事裁判:A/N関連費用の線引き
- 中国の海事裁判ではA/N関連費用(滞箱費・港湾費・倉庫費など)の負担主体が繰り返し争われている。
- 判例は「D/O換取後は収貨人負担」「中継港は合意なければ請求不可」「行政扣押中は行政負担」と整理された。
- 実務では費目ごとに原因・立場・法的根拠を明確化し、時効管理を徹底することが重要。
事件の概要
中国の海事裁判では、滞港(port stay)、滞箱(container detention=滞箱费)、港湾費(port/terminal charges=码头费/堆存费/THCなど)の費用を「誰が払うのか」「その負担が妥当か」が繰り返し争われています。特にA/N(到貨通知=Arrival Notice)に関連する費用では、「誰が」「いつから」「どの範囲で」支払うのかが大きな争点です。この点については、多くの裁判で判断が積み重なっており、実務でも参考になります。
この記事では、中国の各級法院や最高人民法院が公表した一次情報をもとに、代表的な判例の結論を整理します[F1][F2][F3][F4][F5][F6]。
事案の背景(タイムライン)
- 2015年(最高人民法院・民提字第119号):集装箱の超期使用費(detention)の時効は「免箱期(free time)満了の翌日から1年間」と判示。英語版ホワイトペーパーでも明記されています[F4]。
- 2017年(广州海事法院):海関など行政機関による扣押(seizure)の期間中に発生した堆存費(storage)は、行政機関が負担すべきと整理。保管費用の主体が示されました[F2]。
- 2019年(宁波海事法院・(2019)浙72民初1817号):滞箱費490,811.19元などの負担が争点となり、判決文で具体的な金額も公表されました[F6]。
- 2021年(上海海事法院・(2021)沪72民初878号):滞箱費・倉儲費・海関検査費・操作費など、A/N関連の費目合計38,680.87USDの負担をめぐり争われました[F3]。
- 2024年(广东高院・典型案例):①D/O(提貨単)交付後の目的港費用の負担主体、②中継港での長期滞留と費用請求の可否について、費目ごと・場面ごとの線引きを具体化しました[F1]。
- 併せて(宁波海事法院・報告):違法品や“洋垃圾”案件では滞留が長期化する傾向があり、荷主側の過失評価について整理されています[F5]。
主張
事例A(广东高院・典型案例01)
承運人は「収貨人がD/O(提貨単)を受け取った後に長期間貨物を引き取らず、その結果発生した倉租(warehouse rent=仓租费)などの費用は托運人(shipper)が負担すべき」と主張しました。これに対し托運人は「そのような合意はない」と反論しました[F1]。
事例B(广东高院・典型案例03)
承運人は「中継港(南沙)で発生した保管費(堆存費・滞箱費)は収貨人が支払うべき」と主張しました。これに対し収貨人は「契約上の引取地は卸貨港(黄埔)であり、中継港での費用負担は認められない」と反論しました[F1]。
事例C(上海海事法院・(2021)沪72民初878号)
委託者は「海外港での検査や滞留によって発生した碼頭費・堆存費・滞箱費・操作費を立て替えており、その分を請求する」と主張しました。これに対し被告は「貨物代理人(フォワーダー)の過失がある」「立証が不十分」として抗弁しました[F3]。
事例D(广州海事法院・保管費用)
承運人は「扣押期間に発生した堆存費を貨主などに請求できる」と主張しました。これに対して裁判所は「行政による扣押に伴う保管は行政委託の性質を持つため、費用を負担すべきは行政機関である」と整理しました[F2]。
判決理由(要点)
D/O換取後の地位変動
収貨人がD/O(Delivery Order=提貨単)を受け取り、貨物の権利を行使し始めた時点で、運送契約上の立場は実質的に収貨人へ移ります。そのため、特別な合意がない限り、その後に発生する目的港での費用やリスクは収貨人が負担するのが原則です[F1]。
中継港での保管費の扱い
契約上の卸貨港ではない中継港で長期間貨物を保管した場合、その費用を収貨人に請求するには契約や法律上の根拠が必要です。根拠がなければ請求は認められず、承運人には「契約で定められた卸貨港に貨物を引き渡す義務」が重視されます[F1]。
行政扣押中の堆存費
《行政强制法》に基づき、行政による扣押(差押え)の期間中に発生した保管費用は、原則として行政機関が負担します。そのため、港湾事業者から承運人、さらに貨主へと費用を転嫁することは否定される場合があります[F2]。
時効(limitation)
最高人民法院・民提字第119号の判例では、滞箱費(detention)の時効は「免箱期(free time)が終了した翌日から1年間」と明示されています。これはDemurrage/Detentionの時間管理を徹底すべきだという指針です[F4]。
費用の正当性と過失の立証
海外港での検査や強制執行に伴う費用については、相手方の過失を十分に立証できなければ求償が認められない場合があります。費目ごと(码头费・堆存费・操作费・海关检验费)に因果関係や法的根拠が審査されます[F3]。
違法貨物と適法性の影響
禁制品や申告不実によって貨物が滞留した場合、荷主側の過失が大きく評価されます。その結果、堆存費や滞箱費が長期に膨らみ、損害が拡大するという構造が裁判所から指摘されています[F5]。
なぜトラブルが起きた?
A/Nの「包括請求」慣行
費目ごとの法的根拠や因果関係を示さずに、一括で請求するケースが多いことが問題です。また、托運人(shipper)から収貨人(consignee)へ立場が移るタイミングを無視して請求することも、トラブルの原因になります[F1][F3]。
中継港での「先置き」
契約上の目的港ではなく中継港に貨物を置く慣行があり、その費用を誰が負担するのかについて、事前の合意や法的根拠が欠けていることが目立ちます[F1]。
行政扣押時の費用把握不足
行政が貨物を扣押(差押え)した場合、本来は行政機関が保管費の債権者です。しかし、これを誤解して港湾事業者や承運人が荷主に二重請求や誤請求をすることがあります[F2]
時効管理の欠落
滞箱費などの請求は「免箱期が終わった翌日から1年」という短い時効があります。この起算点を誤解し、時効を過ぎて請求権を失うリスクがある点も大きな課題です[F4]。
貿易実務者の学ぶべき事
1.費目ごとの「根拠紐付け表」をA/Nに添付
码头费(ターミナル費用)、堆存费(ストレージ費用)、滞箱费(コンテナデマレージ)、海关检验费(通関検査費用)、操作费について、それぞれの発生原因(例:customs inspection=海关检验)、誰の行為が原因か、相手の立場(shipper/consignee)を「1明細1根拠」で記載することで、請求の透明性を高めます[F3]。
2.D/O換取の社内トリガー化
D/O(Delivery Order=提貨単)が発行されると、費用負担は収貨人に移るのが原則です。このタイミングを社内システムでトリガーに設定し、名義変更や請求先切替を自動化します。契約書やB/L裏面条項との照合も徹底します[F1]。
3.中継港での保管に関する「事前同意書」
契約上の卸貨港以外で貨物を保管する場合、費用負担者・保管期間の上限・移送条件を事前に書面で合意する必要があります。合意がなければ請求が認められないという判例対策になります[F1]。
4.行政扣押への対応プロトコル
行政から扣押通知を受けたら、行政機関を正式な費用負担者として交渉する手順を整えておきます。これで港湾事業者→承運人→荷主への誤った転嫁を防げます[F2]。
5.時効管理ダイアリーの導入
免箱期(free time)終了翌日を「T0」とし、そこから1年後に自動アラートが出る仕組みを導入します。同時に、遅延を証明するゲートイン・ゲートアウト書類を確保しておくことも重要です[F4]。
今日からできる行動リスト
- A/N様式の見直し:費目、根拠条文、発生港、相手方の立場(shipper/consignee)の4項目を必須欄として追加する。
- D/Oモニタリング:D/O(提貨単)が換取されたら即日通知を行い、請求先の切替をRPA(自動化ツール)で処理できるようにする。
- 中継港での保管稟議:契約上の卸貨港以外に貨物を置く場合は、必ず社内稟議を経て、相手の承諾書を取得してから実施する。
- 扣押対応:行政による扣押が発生した際に備え、行政機関宛ての債権提示用の雛形を整備しておく。
- 時効管理:免箱期(free time)のカレンダーを運用し、満了の翌日から1年間の請求期限を可視化しておく。
💡インサイト(中小企業への学び)
「A/Nに書いてあるから請求できる」という単純な考え方は成り立ちません。費用の負担者や請求の根拠は、次の条件によって大きく変わります。
- D/O(提貨単)が換取されたかどうか
- 貨物が置かれているのが契約港なのか中継港なのか
- 行政による扣押(差押え)があったかどうか。
この3つの条件を踏まえないと、請求が認められない可能性があります。
実務では、費目ごとに「発生原因 × 相手の立場(shipper/consignee) × 法的根拠」をセットで整理しておくことが重要です。さらに、免箱期が満了した翌日から1年間という時効管理を徹底することで、少額の費用が積み重なって大きな損失になる事態を未然に防ぐことができます[F1][F2][F4]。
要点まとめ
- D/O換取後の目的港費用は収貨人側へ移行[F1]。
- 中継港の堆存・滞箱は、合意なければ請求不可[F1]。
- 扣押中の堆存費は行政機関負担(行政委託保管)[F2]。
- 滞箱費の時効は免箱期満了翌日から1年(最高法)[F4]。
- 費目は“原因×地位×根拠”で明細化し請求[F3]。
Factリスト
- [F1] 广东省高级人民法院|「广东法院海事审判典型案例」(公開:2024-05-30)
广东法院海事审判典型案例_广东法院网 - [F2] 广州海事法院|「货物扣押期间保管费用的承担主体」(2017-01-25)
广州海事法院网广州海事法院政务网站,广州海事法院网,广州海事法院,广州海事法院网是人民群众了解和联系广州海事法院的重要窗口,承载着司法公开、法治宣传、服务群众、接受监督等重要使命。是广州海事法院的政务网站,是广州海事法院在互联网上唯一的正式身份。 - [F3] 上海市高级人民法院(上海海事法院)|(2021)沪72民初878号
貧今偏互雫繁酎隈垪利--加登猟慕 - [F4] 最高人民法院|(2015)民提字第119号(滞箱費の時効起算に関する再審判決)
公式裁判文は中国裁判文書網(China Judgments Online)に収載されていますが、現在はログイン等のアクセス制限があり直リンクを提示できません。公式入口: https://wenshu.court.gov.cn/(検索語例:「(2015)民提字第119号
马士基 集装箱 超期使用费」)。※必要であれば、判決の公開ページに到達できる手順を書面化します。 - [F5] 宁波海事法院|「涉外、涉港澳台案件审判情况报告(2016年1月–2020年6月)」https://zjjcmspublic.oss-cn-hangzhou-zwynet-d01-a.internet.cloud.zj.gov.cn/jcms_files/jcms1/web3782/site/attach/0/6f50760d8d544c64b47acb32a2e0c96e.pdf
- [F6] 人民日报海外版(公告)|「(2019)浙72民初1817号」
人民日报海外版 - 中华人民共和国宁波海事法院公告
全期間の人気記事(貿易トラブルカテゴリ)
24時間の人気記事(貿易トラブルカテゴリ)
判例トラブル一覧

 この記事を登録
この記事を登録関連記事
基幹記事
貿易学習コースの一覧
分野別記事
カテゴリの一覧
関連記事
◆スポンサード広告


 目次
目次