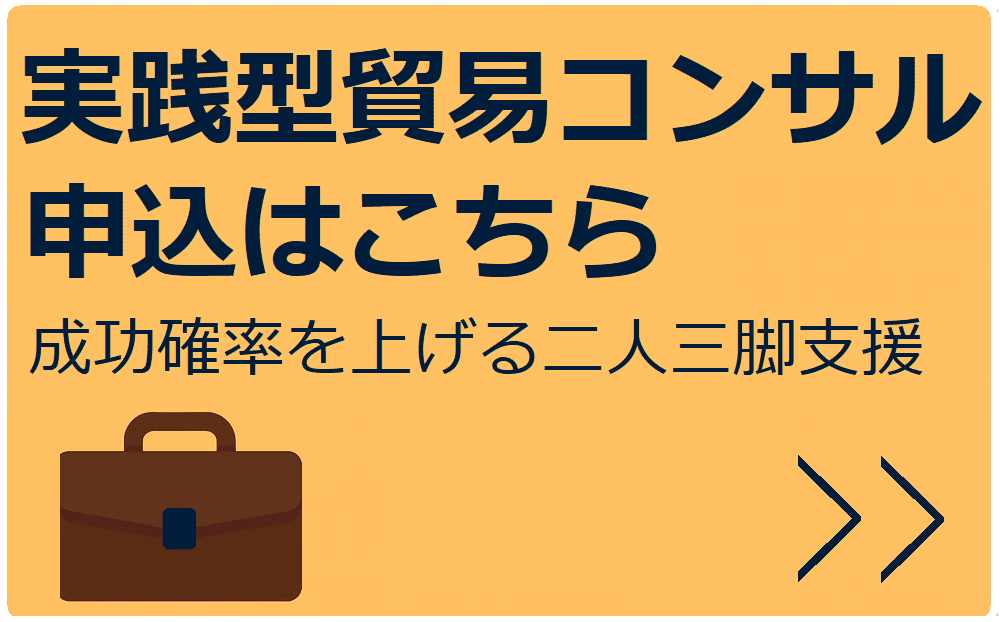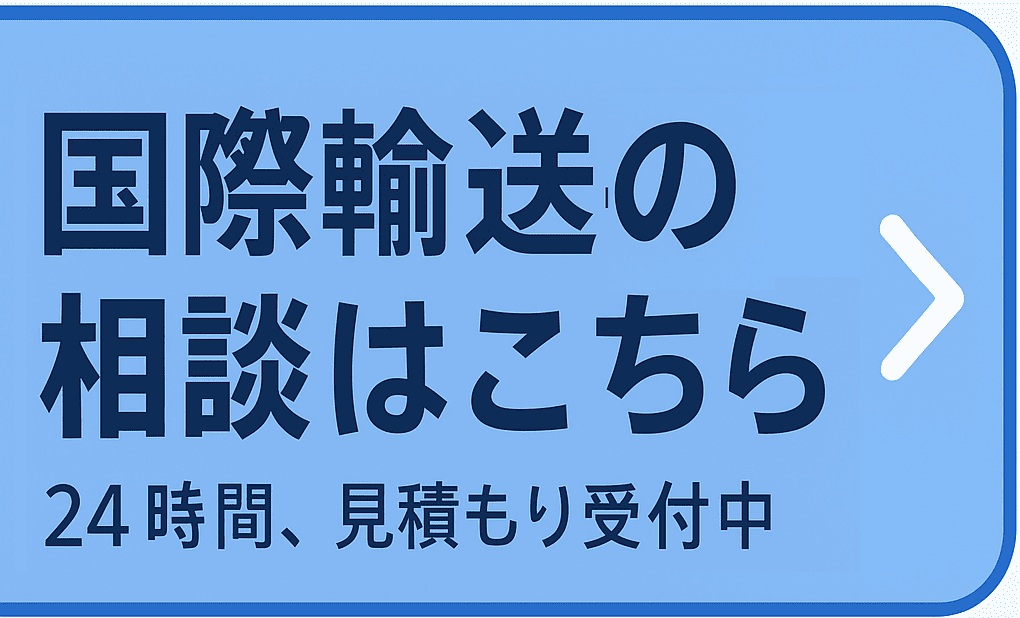輸入通関の失敗事例 問屋契約で加算税!?
はじめに
輸入ビジネスにおいて、「課税価格の申告」は単なる数字ではありません。特に問屋契約などの複雑な契約形態を伴う取引では、その背後にある商流や所有権の構造、販売形態を税関がどのように評価するかによって、申告価格の妥当性が大きく問われます。もし、税関の評価と食い違った場合、輸入者は後から追徴課税や過少申告加算税の対象となるおそれがあります。
本記事では、関税等不服審査会の答申(第95号・第97号・第101号)をもとに、複数の実例を通じて課税価格申告にまつわるリスクと、その回避策を実務目線で詳しく解説します。
事案に共通する背景と失敗のポイント
各答申で共通して見られたのは、輸入者が「製造者インボイス」に基づいて申告価格を設定していたことです。通常、この価格が輸入取引における支払価格であれば、関税定率法上の「現実支払価格方式」が適用されます。
しかし、問屋契約においては、輸入者と実際の製造者との間に売買契約がなく、商品と代金の直接的なやり取りが存在しない場合が多くあります。このような取引では、「現実支払価格」とは認められず、税関は別の課税方式を採用する必要があると判断します。その結果、製造者の価格よりも高く評価された「国内販売価格方式」が適用され、その差額に対して過少申告加算税が課されました。
現実支払価格が使えない場合の課税方式
関税定率法では、課税価格を決定するためにいくつかの方式が定められており、その適用には優先順位があります。
- 「現実支払価格方式」で、売手と買手の間に成立した輸入取引に基づく価格を用います
- 「同種又は類似の貨物の価格方式」
- 「製造原価方式」
- 「国内販売価格方式」が適用されます。
これらは順番に検討され、適用ができないと判断された場合に次の方式へと進みます。輸入者が希望する方式を任意に選べるわけではなく、実際の取引の性質や入手可能な資料に基づき、税関が客観的に判断します。
問屋契約は「輸入取引」ではない可能性
問屋契約は、通関評価の観点から見ると注意が必要です。問屋契約では、名義上は輸入者が通関手続きを行うものの、実際の売買契約は海外の問屋企業と他の小売先との間で成立しており、輸入者自身が対価を支払っていない場合があります。
このような契約では、商品に対する所有権が輸入者に移転しておらず、売手と買手の実質的な関係がないため、税関は「輸入取引が存在しない」と判断します。したがって、現実支払価格方式は否定され、より下位の方式へと移行していきます。
また、こうした取引においては、契約書の提示だけでなく、実際の取引実態(利益の帰属先、代金の支払先、リスク負担の所在など)を裏付ける資料が求められます。これらが揃っていないと、輸入者側の主張は認められない可能性が高くなります。
製造原価方式にも高いハードルがある
次の候補となる「製造原価方式」は、輸出国の製造者が作成した帳簿や会計資料をもとに、製造原価に利潤や一般経費を加えて算出する方法です。
しかし、この方式の適用には極めて厳格な要件があり、原価計算書、損益計算書、監査済み帳簿など、第三者が確認可能な資料の提出が求められます。答申事例では、いずれも製造者インボイスだけでは情報が不十分であり、製造者の内部資料を十分に収集できていなかったことから、この方式の適用は否定されました。
輸入者がこの方式を選択するには、製造者との信頼関係や情報開示契約などをあらかじめ整備しておくことが望ましく、現実的には中小企業にとって大きな負担となるケースもあります。
国内販売価格方式で求められる資料とは
製造原価方式が使えない場合、最後の手段として「国内販売価格方式」が適用されます。この方式では、輸入品が日本国内で実際に販売された価格(特に販売数量が最も多かった価格)をもとに課税価格を計算します。そこから、控除可能な費用(関税、消費税、国内輸送費、流通マージン、利潤・一般管理費など)を差し引くことで、理論上の課税価格を算定する仕組みです。
控除に必要な資料としては、損益計算書、販売台帳、インボイス、納品書、物流費の請求書などが求められます。これらの資料がなければ、正確な控除ができず、結果として課税価格が高くなり、税額も増えることになります。
「正当な理由」は簡単には認められない
過少申告加算税が課される場面では、輸入者側が「正当な理由があった」と主張することがあります。しかし、関税法や国税通則法では、「真に納税者の責めに帰すことができない客観的事情」がある場合に限り、加算税の賦課を免除できるとされています。これは非常に限定的な判断であり、たとえば社内手続きの遅れや帳簿の不備といった理由として認められません。
実際の答申事例では、税関が申告前に国内販売価格方式の使用を明確に指示していたにもかかわらず、輸入者が別の方式で申告し続けたことで、「調査を予知してされた申告」と見なされ、加算税の対象となりました。また、過去の販売実績資料や損益データを保有していたのに、それを活用せずに誤った方法で申告した点も問題視されました。
実務上の対応と体制整備
このようなリスクを未然に防ぐためには、輸入前の段階から実務体制を整えることが不可欠です。具体的には、自社が締結している契約の構造を見直し、それが「売買契約」なのか「問屋契約」なのかを明確に把握する必要があります。また、どの課税価格方式が適用される可能性があるかを事前に検討し、それぞれの方式に対応できる資料を用意しておくことが求められます。
税関からの文書指導や口頭説明はすべて記録に残し、社内で共有・確認する体制を整えましょう。判断が難しい場合には、税関との事前協議制度や事前教示制度を活用することで、申告時の不確実性を減らすことが可能です。
さらに、申告後に修正を行う場合でも、税関の調査開始前であれば「自主的な修正申告」として加算税を免れる可能性があります。したがって、課税価格に疑義がある場合には、早期の判断と行動がカギになります。
分科会の答申書から学べること
まとめ
- 問屋契約では「現実支払価格方式」が使えない可能性がある
- 国内販売価格方式は販売データと控除費用の証明が必須
- 製造原価方式を主張するには詳細な帳簿と会計資料が必要
- 税関の指摘を無視すると「正当な理由」が認められず加算税の対象になる
- 曖昧な契約形態ではなく、取引実態を可視化し、事前準備を徹底することが重要
- 事前教示制度を積極的に活用し、申告ミスの予防を図ることが実務上有効

 この記事を登録
この記事を登録関連記事
基幹記事
貿易学習コースの一覧
分野別記事
カテゴリの一覧
関連記事
◆スポンサード広告


 目次
目次