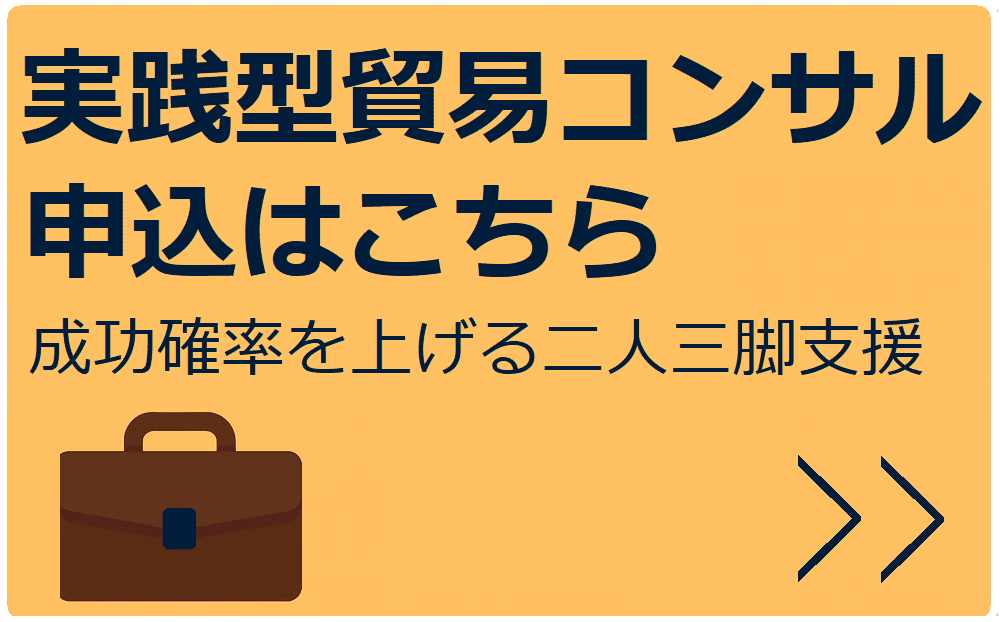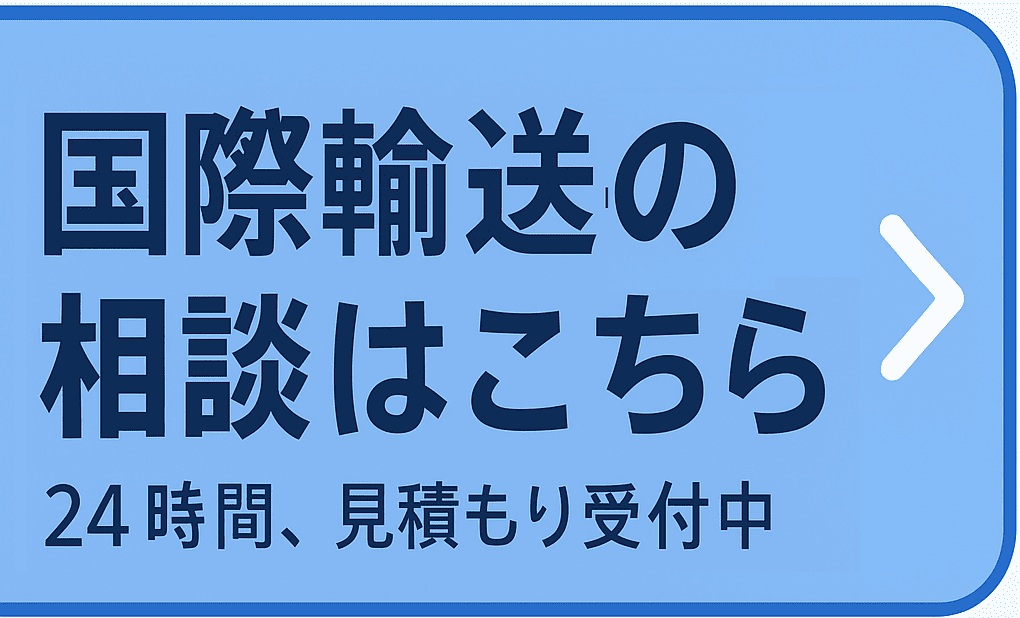問屋契約に潜む税関リスク
はじめに
本記事では、関税等不服審査会による第94号答申書をもとに、輸入者が実務上どのようなリスクに直面するのかを明らかにします。特に「輸入取引」の該当性や課税価格の決定方法が争点となった今回の事案は、小規模な貿易事業者にとっても他人事ではありません。答申の経緯を追いながら、契約形態や申告資料の不備がどのような課税リスクを生むのかを解説します。
事案の概要と争点整理
本件は、問屋契約に基づいて貨物を輸入した事業者が、製造原価ベースの課税価格を主張したところ、税関はこれを認めず、最終的に国内販売価格方式に基づいて課税価格を更正したというものです。
審査請求人は、ベンダーと審査請求人2(米国法人)との取引を「輸入取引」と見なし、その価格を課税価格とすべきと主張しましたが、税関と審査会はこれを否定。「輸入取引」の該当性が本件の最大の争点となりました。さらに、積算価格方式や国内販売価格方式の適用可能性をめぐる主張もありましたが、いずれも審査会は認めませんでした。
また、審査請求人2については、そもそも納税義務者でないため審査請求の適格性がないとして、却下されています。
貿易事業者が学ぶべきポイント
「輸入取引」の定義と実務上の注意点
「輸入取引」とは、単に貨物を輸出国から日本へ運ぶ取引を指すのではなく、売買契約に基づいて現実に輸入された取引を指します。本件では、ベンダーと審査請求人2との間の売買契約ではなく、日本側の問屋契約に基づき輸入が実行されたことから、「輸入取引」とは認定されませんでした。したがって、どの取引が現実に輸入をもたらしたのか、その契約関係や物流責任、所有権移転のタイミングを明確にしておくことが重要です。
課税価格の決定方法とその根拠資料
税関において課税価格を決定するには、明確な裏付け資料が必要です。本件では製造原価方式による申告が主張されましたが、生産者の商業帳簿や販売経費、利潤などの資料が不十分であり、認められませんでした。結果的に、国内販売価格方式が採用され、1年間の損益計算書を基に国内経費率が算定されました。積算価格方式を用いたい場合は、あらかじめ必要な帳簿資料の整備が不可欠です。
申告内容の正確性と事後調査への備え
課税価格を正しく申告できなかった場合には、加算税の対象となる可能性があります。本件では、過少申告加算税が賦課されました。税関は「正当な理由」があるかどうかを厳しく判断しており、通達や制度の理解不足による誤申告は、理由として認められませんでした。税務上の責任回避には、日頃の法令理解と記録保存が不可欠です。
審査請求の適格性
審査請求は誰でも行えるわけではありません。今回は、審査請求人2が輸入者でなく、納税義務者でもなかったため、そもそも審査請求の資格を欠くとして却下されました。実務上は、誰がどの処分に対して不服申し立てができるのか、処分の主体と対象を明確にしておく必要があります。
実務への示唆と教訓
本件から得られる実務上の教訓は多岐にわたります。まず、契約書・インボイス等には、取引当事者の役割や責任範囲を明確に記載することが重要です。所有権や危険負担の所在、販売経路の設定は、輸入取引の判断に直結します。また、税関からの疑義が生じた際は、速やかに資料を提出し、誠実に説明責任を果たす姿勢が求められます。
さらに、関税評価協定や関税定率法の制度を理解し、法令や通達の改正情報に常に目を光らせておくことが、トラブル回避の最善策となります。
分科会の答申書から学べること
まとめ
- 輸入取引の該当性は、契約内容や物流責任、所有権移転に基づき厳格に判断される
- 製造原価方式など特例的な評価方法を使うには、十分な資料の整備が必要
- 申告誤りには加算税が課され、「正当な理由」も限定的に解釈される
- 審査請求の適格性には、納税義務者であることが不可欠
- 契約書やインボイスの記載、取引実態の整理が実務トラブルを回避する鍵

 この記事を登録
この記事を登録関連記事
基幹記事
貿易学習コースの一覧
分野別記事
カテゴリの一覧
関連記事
◆スポンサード広告


 目次
目次