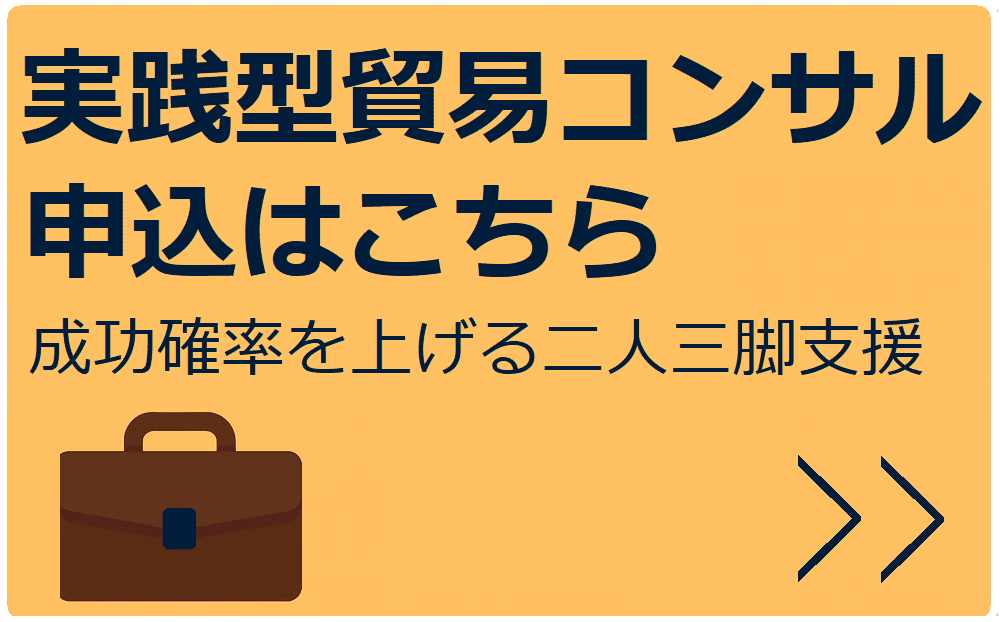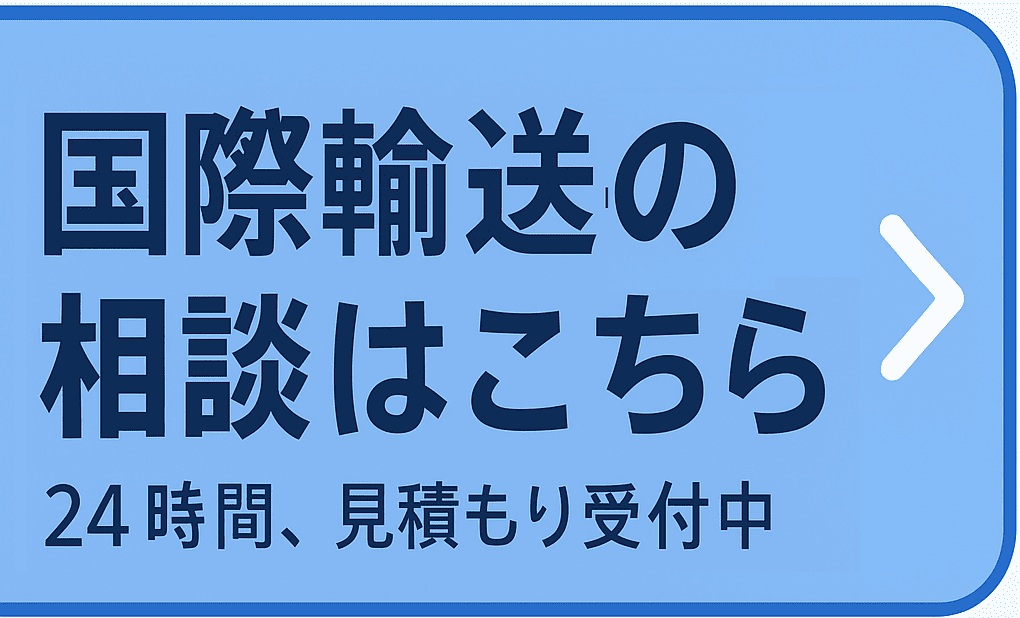差額関税と審査会答申から学ぶリスク管理
はじめに
輸入申告において「申告価格の正確性」は、税関との信頼関係を築くうえで最も重要です。しかしながら、価格の根拠が曖昧なまま申告を続けると、後の調査で大きなトラブルを招く可能性があります。今回は、豚肉の輸入取引を巡る関税不服審査の事例をもとに、行政手続や制度論争のポイント、貿易事業者が実務で注意すべき点を解説します。
答申第114号サマリー
関税等不服審査会関税・知的財産分科会 答申3(PDF:179KB)(令和2年12月10日)
事案概要
食肉輸入会社が豚肉の輸入申告価格を偽って申告し、関税脱税で刑事告発された事案。同社は関税当局の追加関税・加算税処分に不服を申し立てた。
主な争点と判断
輸入会社の主張
- 申告は正当で不正はない
- 納税義務は別法人にある
- 差額関税制度は違憲・違法
審査会の判断
- 刑事・行政訴訟の有罪・適法判決を重視
- 審査請求人が実際の輸入者で納税義務者
- 差額関税制度の合憲性を確認
結論
審査会は追加関税・加算税処分を適法と判断し、不服申し立てを棄却。差額関税制度の合憲性と適正な価格申告の重要性が確認された。
豚肉輸入を巡る事案の全体像
事案の中心は、ある食肉輸入会社が自社とは別法人の名義を使って冷凍豚肉を輸入し、その申告価格を本来より高く設定していたという点にあります。後の税関調査によって、これが意図的な価格操作(高額偽装)であり、約59億円分の関税が過少申告されていたと判明しました。税関はこれに対して更正処分と過少申告加算税の決定処分を行い、さらに刑事告発に至る重大な案件となりました。
申告業務を実際に担っていたのは別会社(G社)でしたが、実態として輸入指示や資金決済、利益の帰属がすべて申請法人側にあったため、実質的な輸入者とみなされ、責任を問われたのです。
関税法上の更正処分と加算税のしくみ
関税法では、誤った申告に対して税関が本来の金額に修正する「更正処分」があります。これは税関調査の結果、インボイス価格などが不適切だった場合に発動され、追徴課税とともに加算税が課されることもあります。加算税は過少申告に対するペナルティであり、納税義務者の故意や過失の有無が重視されます。
今回のように意図的な価格偽装があった場合、加算税率も重くなり、企業にとって大きな損失となりかねません。
審査請求の主張と論点
企業側は、G社は独立した法人であり、輸入価格は取引実態に基づく正当なものであったと主張しました。また、自社は関税法に定める納税義務者に該当しないとも訴えました。さらに、豚肉の差額関税制度自体が不合理で違憲・違法であるとの制度批判も展開し、処分の取消しを求めたのです。
この中で注目すべきは、「立法不作為」という主張です。企業は、差額関税制度が長年見直されておらず、制度の継続自体が違法だと主張しました。
しかし、審査会は、制度が合憲である限り、改正がなされていないことだけで違法とは言えないという立場を取りました。これは、制度そのものへの不満や批判だけでは行政救済の根拠にならないことを示しています。
行政不服審査制度の基本と制限
行政不服審査は、処分を受けた者が納得できない場合に、その是正を申し立てる手続です。申立ては原則として「処分を知った日から3か月以内」に行う必要があり、形式・内容ともに厳格な基準が課されます。
今回のように、制度批判に終始する場合や、申請者が納税義務者でないと主張しても、実態として影響を受ける者であれば「法律上の利益がある」とされ、請求自体は認められる可能性があります。
ただし、審査請求は新たな事実認定の場ではありません。特に、過去に刑事・行政訴訟で判決が確定している事案は、それらの判決内容が審査会においても拘束力を持ち、判断の基礎となります。今回も、有罪判決と行政訴訟の棄却判決が前提とされ、処分の適法性が認められました。
実務で注意すべき管理と体制構築
この事案から得られる教訓は、「申告の形式ではなく実態で判断される」ことです。名義人や通関手続の委託先が誰であれ、実質的に輸入を主導していれば、納税義務者としての責任は免れません。
実務対応としては、インボイス、契約書、送金記録など、価格の妥当性を証明できる資料をきちんと保存しておくことが第一です。さらに、社内においても価格決定の経緯を記録し、関係部門間で透明性のある意思決定フローを整備することが必要です。
また、調査や処分を受けた場合に備えて、税関対応マニュアルや顧問弁護士との連携体制を構築しておくこともリスク管理上有効です。特に小規模な貿易業者ほど、こうした体制が手薄になりがちですが、事後対応ではなく予防的な仕組みこそが最大の防御になります。
分科会の答申書から学べること
まとめ
- 申告価格の妥当性は、インボイスや送金実績など客観的資料で裏付けることが重要
- 通関名義と異なっても、実質的に取引を主導していれば責任を問われる可能性がある。
- 差額関税制度などの制度批判は、審査請求の根拠にはなりにくく、実態の証明が不可欠
- 審査請求には期限があり、また確定判決がある場合にはその影響が大きくなります。
- 事前の価格検証体制と、万一のための税関対応フローを整備しておくことが、トラブル回避の鍵となります。

 この記事を登録
この記事を登録関連記事
基幹記事
貿易学習コースの一覧
分野別記事
カテゴリの一覧
関連記事
◆スポンサード広告


 目次
目次