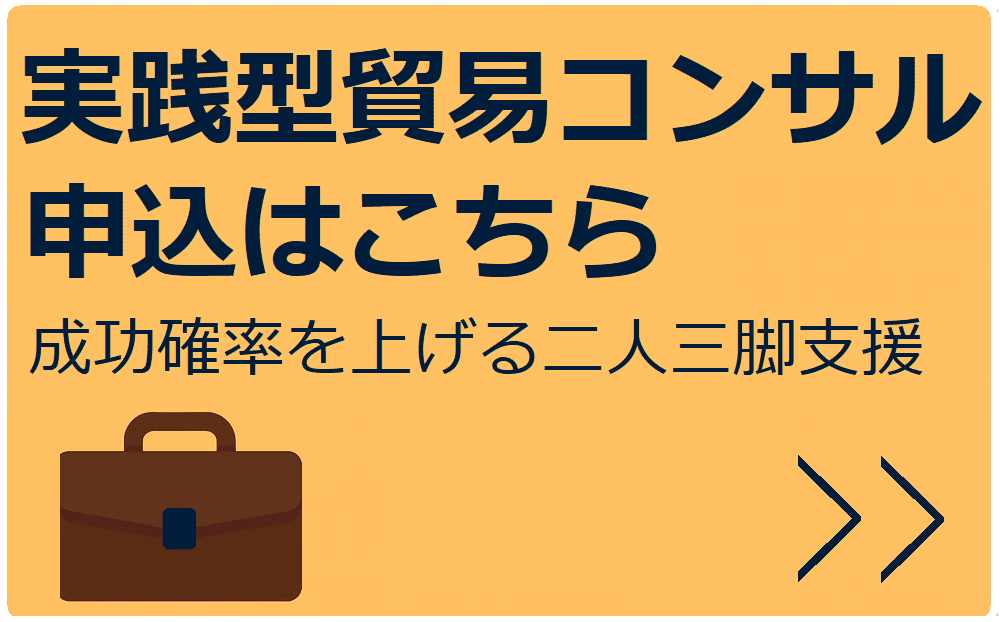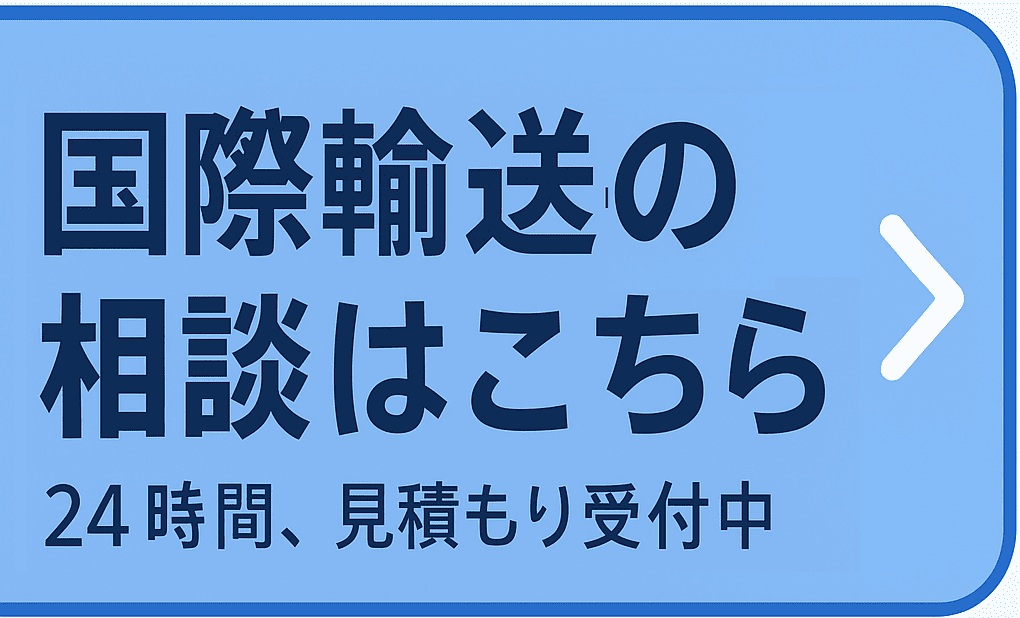靴の原産性判定をめぐる関税審査
背景(サマリー)
株式会社Aは、E国など東南アジア諸国に婦人靴の製造を委託し、日本へ輸入する際、EPA(経済連携協定)やGSP(特別特恵関税制度)による関税の優遇措置を受けていました。
しかし、税関による事後調査の結果、輸入された靴の一部にG国で生産されたヒールや中底などの部品が含まれていることが判明。これにより、たとえ原産地証明書が提出されていても、原産性に疑問が生じたため、税関は優遇税率の適用を認めず、通常税率での更正処分と過少申告加算税の賦課を決定しました。
まずは、関税等不服審査会(答申115号)の要約です。
申立人(株式会社A)の主張
「正規の原産地証明書を提出しているため、優遇税率の適用は正当である。」
- コスト分析表の「仕入地」欄はサンプル作成時の情報であり、量産品の仕入地とは異なるため、その記載は原産性判断の根拠にはならない。
- サンプル用部材はG国から調達したが、量産品についてはE国で仕入れている。
- 送金記録や現地企業からの証明書も提出し、量産品がE国原産であることを主張した。
審査会の判断
- コスト分析表に記載された「仕入地」情報は量産品にも適用されていると認められ、その信憑性は高いと評価された。
- 原産地証明書が提出されていたとしても、実際にG国産の部品が使われていれば原産性は認められず、優遇税率の対象外となる。
- EPA税率またはGSP税率の適用を受けた貨物のうち、ヒールを使用したものについては、優遇税率の要件を満たさないと判断され、税関の更正処分および加算税の賦課は妥当
一方で、ヒールを使用していないGSP税率適用貨物は、原産性を否定する明確な証拠がないことから、優遇税率の適用が妥当とされ、税関の更正処分等は取り消すべきと結論づけられた。
はじめに
国際物流や貿易の現場では、EPA(経済連携協定)やGSP(特別特恵関税制度)などを活用して、関税の優遇を受けて輸入を行う事業者が数多く存在します。中でも、小規模な輸出入事業者にとって、これらの税率優遇制度の活用は、仕入価格や販売価格の競争力を左右します。
しかし、原産地証明書を提出しても、それだけで必ず優遇措置が適用されるわけではありません。税関は、書類上の情報と実際の取引実態が一致しているかを厳格に審査しています。とくに、靴のように多様な部材から構成される商品においては、どの国からどの部品を調達しているのかという「仕入地」の情報が重要な判断材料です。
本記事では、コスト分析表に記載された「仕入地」の情報がきっかけとなり、原産性が否認された事例を通じて、国際取引における注意点と実務的なリスク管理の重要性を解説します。
問題の背景と経緯
本件は、日本の企業が婦人用靴をE国から輸入し、GSPやEPA税率の適用を受けていた事例です。企業は適正に原産地証明書を提出しており、当初は問題なく通関が行われていました。
しかし、後日行われた税関の事後調査で、コスト分析表に「G国」から仕入れたとされるヒールや中底といった靴の部分品の記載があったことが発覚します。企業側は「その記載はサンプル用であり、量産品はE国から調達した」と説明しましたが、税関はこの記載を量産品の実態を反映したものと判断し、原産性を否認しました。
さらに重要なのは、ヒールを使用した靴は原産性が否認された一方で、ヒールや中底などG国製の部品を使っていない靴は、原産性を否定する根拠がないとして、関税の優遇措置が認められた点です。このように、関税審査においては「製品ごとの個別判断」がなされることがある点も実務者としては押さえておきたいポイントです。

重要なポイント:製品ごとに個別判断される余地がある
税関が重視した判断ポイント
税関は、原産性の確認にあたって複数の資料を総合的に審査します。本件では、特に次の3点が重要視されました。
1.書類とコスト分析表に記載された仕入地情報との一致
コスト分析表に記載された仕入地情報とインボイスや注文書に記載されたオーダー番号、スタイル番号が一致していたことです。この一致は、税関にとってその表が量産品に関する実際の情報であると判断するに十分な要素となりました。
2.企業側の説明に一貫性の不足
企業側の説明に一貫性がなかった点です。単価は更新しているが仕入地は更新していないと主張したにもかかわらず、実際には「仕入地も随時更新されている実態」が見られ、記載運用の整合性に欠けていたとされました。
3.E国当局からの情報提供
E国当局から提供された情報です。これには、G国からE国に対してヒールや中底の輸出が確認される資料が含まれており、企業の主張を否定する要素として働きました。さらに、当初は原産地証明書の適格性を認めていたE国当局も、最終的には日本税関の判断を追認する形で「原産性否認」に同意する意向を明確に表明しました。
加えて、企業が提出した送金資料や現地メーカーからの証明書、サンプル用の領収書などは「量産品の原産性証明としての証明力が低い」と評価され、税関によって十分な証拠とは認められませんでした。
原産地証明書だけでは不十分な理由
多くの事業者が誤解しがちなのが、「原産地証明書さえあれば大丈夫」という認識です。確かに、税関での優遇税率適用にあたっては証明書の提出が要件となりますが、それだけで関税優遇が保証されるわけではありません。
原産地証明書はあくまで証憑の一つであり、それが示す内容と、実際の製造・調達・物流の流れが一致しているかが問われるのです。とくにサンプル品と量産品で調達元が異なるような場合には、それぞれのプロセスを明確に分けて管理し、誤認や混同を防ぐことが求められます。
今回のケースでは、原産地証明書そのものの正当性に疑義はなかったものの、コスト分析表などの実務資料により「実態と異なる」疑いが生じ、優遇措置が取り消されました。つまり、書類と実態の整合性が保たれていなければ、たとえ正規の証明書があっても税関は適用を否認するということです。
実務者が注意すべきポイント
この事例から学べる最大の教訓は、内部資料や参考資料として使用しているつもりの書類であっても、税関の審査対象になることです。とりわけ、コスト分析表のように「誰が、いつ、何を、いくらで、どこから仕入れたか」が明記されている資料は、非常に高い証明力を持ちます。
企業としては、サンプル用と量産用の記録を明確に分け、仕入地や原材料に関する記載は常に最新で正確な情報に保つことが必要です。また、社内で「記載は重要視していない」としていても、税関の視点ではそのような主観は関係なく、客観的な記録に基づいて判断されるという点を忘れてはなりません。
加えて、仕入地や原材料の変更がある場合には、製品の原産性に影響があるかどうかを事前に確認し、必要であれば原産地証明書の再取得や取引先への説明などを行うべきです。誤った申告を防ぐためには、輸入・通関の現場と、仕入・生産管理部門との連携も欠かせません。
分科会の答申書から学べること
まとめ
- コスト分析表は単なる社内資料ではなく、税関にとっては「量産品の実態」を判断する重要な証拠資料である
- 原産地証明書の提出だけでは優遇税率が保障されるわけではなく、実態と一致しているかどうかが常に問われる
- サンプルと量産品の記録は明確に分け、仕入地や部品構成などの記録は都度更新し、整合性を保つ
- 原産性に影響する可能性のある材料変更や記載の更新漏れには細心の注意を払い、部門間で情報を共有する体制づくりが重要
- ヒールを使用した靴は原産性が否認され、使用していない靴は優遇が認められたという個別判断が下されたことも押さえておくべき実務ポイントである

 この記事を登録
この記事を登録関連記事
基幹記事
貿易学習コースの一覧
分野別記事
カテゴリの一覧
関連記事
◆スポンサード広告


 目次
目次