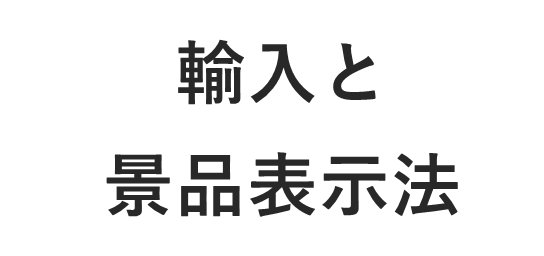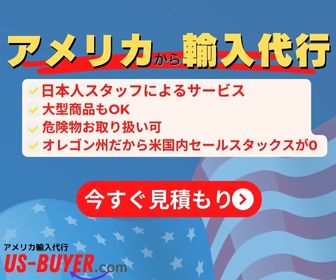世の中で宣伝されている商品やサービスを見ていると、
「このプロテインを飲めば三か月で6kg減少する」
「他社製品と比較して50倍の○○を含有」
などと、実に様々なアピール文を目にします。「本当に?」と疑問を感じながらも、ある種の冒険的な気持ちで新しい商品やサービスを手にする方も多いのではないでしょうか。一方、これを提供する事業者側で考えると、自社の商品やサービスを少しでも多くの方に販売するために実態以上に、良く見せようと考える方も多いです。
そんな両者による取引の公平性を高める法律が「景品表示法(けいひんひょうじほう)」です。景品表示法は、日本国内で何らの商品やサービスを提供するときに「事業者側の不正競争」を防止するための法律です。もちろん、これは、輸入した商品を日本国内で販売するときにも関係します。
景品表示法を理解しないまま商品を販売すると、最悪、是正命令や課徴金が課される可能性もあります。ぜひ、この機会に学んでみましょう!
景品表示法
景品表示法とは、商品やサービスを提供する事業者が偽りの情報を表示して、消費者をだまし、不当な販売ができないようにするための法律です。(正式名:不当景品類及び不当表示防止法)
景表法の2つの目的
景品表示法の目的は、次の2つです。
- 事業者が商品やサービスを過大に表現することにより、消費者の判断を誤らせることを防止
- 事業者による過大な表現の競争を防止し、商品自体の競争を促すこと。
事業者による不公正な表現や偽りの販売を防止して、消費者の保護を目的としています。ちなみに、事業者とは、商業、工業、金融等を営むすべての人(役員、従業員、代理人当)を指し、営利を目的としない、共同組合、共済組合、宗教法人等も対象です。
所管行政庁は?
景品表示法の所管行政庁は「消費者庁」です。この他、公正取引委員会、各県の都道府県知事なども、景品表示法の違反について対処しています。
景品表示法・2つの骨格
景品表示法は、大別すると、次の2つを骨格としています。不当表示とは、商品やサービスについて、事実よりも優れていると誇張し消費者をだますことです。一方、景品類の制限とは、自社のお客様に有償・無償問わず、景品に該当する物を配るときに限度額や範囲等を規制する物です。
1.不当表示の禁止
2.景品類の制限と禁止
1.不当表示の禁止
不当表示とは、商品の実態よりも優れていると見せかけたり、誤解を招く表現により、販売を誘発したりする行為を指します。この不当表示には、大きく分けると次の三つがあります。
- 優良誤認表示の禁止
- 有利誤認表示の禁止
- その他、誤認されるおそれがある表示の禁止
1.優良誤認
優良誤認とは、自社の商品やサービスが「実際の物」よりも著しく優良であると表現をしたり、事実と相違して、競争相手の商品よりも著しく優れていると表現したりして消費者を誤認させることです。(故意、過失問わず、規制の対象です。)
根拠法:景品表示法7条及び8条
具体例
- 中古車:10万キロ走行していた自動車を5万キロとして販売する。
- 栄養成分:実際は、1gしか入っていない栄養を5g入っていると偽り販売
2.有利誤認
有利誤認は、事業者が一般消費者に対して、自社の商品やサービスを購入する方が、ライバル社の商品を購入するよりも「著しく有利」だと説明し、消費者に誤認させる行為です。
例えば、ライバル社の製品の価格よりも「圧倒的に安い」などと宣伝し、消費者に対して誤認させることです。また「先着100名様のみ販売します!」とのタレコミで販売をしていたが、実際は、誰でも購入ができるなどのケースが当てはまります。
3.その他、誤認させる恐れがある表示
上記の他、内閣総理大臣は、次の6つを「誤認させる恐れがある表示」として指定しています。
- 消費者信用の融資費用に関する不当な表示
- 無果汁の清涼飲料水等に表示
- 商品の原産国に関する不当な表示
- 不動産のおとり広告に関する表示
- おとり広告に関する表示
- 有料老人ホームに関する不当な表示
その他、以下の場合も景表法の不当表示に該当する可能性があります。輸入商品の販売をしている場合は、特に「原産国の表示部分」が関係してきます。
- 二重価格を設ける
- 割引率/割引期間を偽る。
- 原産国表示を偽る。
- 期間の設定がエンドレス
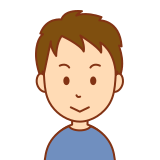
難しい言葉で表現されているけど、結局の所「消費者の誤解を誘発して商売をするな!」ってことですね! ゴミ商品やサービスをどれだけ偽ってもゴミであることは変わりないですし….
2.景品類の制限と禁止
次に「景品類の配布」の規制です。実は、お客に対して無料でプレゼントする等の行為(景品の配布)についても規制があります。
例えば、来店された方に対して「一つのミカンをプレゼント」「抽選で○○名様に当る!」などですね!これらの行為も景品表示法で数量や限度額等が細かく決められています。
景品の定義
景品とは、次の三つに該当する物を指します。
景品表示法上の「景品類」とは、
(1)顧客を誘引するための手段として、
(2)事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供する
(3)物品、金銭その他の経済上の利益引用元:政府資料
→さらに具体的には…
- 物品及び土地、建物その他の工作物
- 金銭、金券、預金証書、当せん金附証票及び公社債、株券、商品券その他の有価証券
- きよう応(映画,演劇,スポーツ、旅行その他の催物等への招待又は優待を含む。)
- 便益、労務その他の役務
引用元2:政府資料
事業者
が上記の「景品」を顧客を呼び込むために、自己の商品やサービスに付随して提供し、顧客に対して、経済的な利益を与えるときに「景品表示法の景品規制」を受けます。
例えば、スーパーマーケットに来店した方に対して「○○」を進呈するなどは景表法の対象です。一方、事業者でない者がツイッター(告知方法は自由)などで、何の条件を付けずに、無料プレゼント等をする場合は、景表法の対象ではありません。
- 事業者であること
- 商品やサービスに付随していること
- 経済的な利益を与えていること
上記の条件に当てはまるときが景品表示法の「景品類の規制」に該当します。なお、景品類を提供する行為を「懸賞」と言い、その中には、次の三つがあります。
- 一般懸賞
- 共同懸賞
- 総付け景品
1.一般懸賞
一般懸賞は、くじ、じゃんけん、抽選検討で無作為に選び景品類を提供することです。この場合の限度額や規制内容は、次の通りです。
| 取引額 | 景品類限度額 | |
| 最高額 | 総額 | |
| 5,000円未満 | 取引価額の20倍 | 懸賞に関係する売上予定の2% |
| 5,000円以上 | 10万円 | |
2.共同懸賞
共同懸賞は、一定の地域の事業者が共同で懸賞することです。この場合の限度額は、次の通りです。
| 最高額 | 総額 |
| 取引額に関係なく30万円 | 懸賞に関係する売上の3% |
3.総付け景品
商品やサービス利用者、来店者等に「もれなく」金品等を提供する場合に該当します。
| 取引額 | 景品の最高額 |
| 1,000円未満 | 200円 |
| 1,000円以上 | 取引額の20% |
なお、以下に示す業種は、一般的な景品規制ではなく「業種別の景品規制」があるため注意します。
- 新聞業
- 雑誌業
- 不動産業
- 医療用医薬品業
4.その他、オープン規制
商品の提供、サービスの利用者、来店者を対象にして、金品等を提供する場合は「取り引きに付随」するため、景品表示法の規制対象です。一方、ウェブサイト等で広く告知をして、何の条件も付けない場合は、景品表示法の規制を受けません。これを「オープン懸賞」と言います。
2020年現在、オープン規制の上限はなし!
違反になりやすいサービスや商品例
| 安心安全 | ガチャ 確率 | クレーンゲーム | クーポン |
| スタンプラリー | セミナー | ダイエット | キャンペーンの期間表示 |
| 懸賞/抽選会 | 福袋 | 除菌 | 健康食品 |
| ふるさと納税 返礼品 | ぼったくりバー | ズワイガニ | パワーストーン |
景品表示法の違反と罰則・相談窓口
景品表示法に違反している商品を見つけた場合の通報窓口、又は、事業者として相談をしたい場合は、どこに行けばいいのでしょうか?
景品表示法に違反し、かつ下記に示す「措置命令」に従わない場合は、景品表示法36条に規定されている通り「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が科せられます。実際の指導及び課徴金の課金は、次の流れがあります。
所管官庁
- 消費者庁
- 公正取引委員会
- 都道府県知事
通報から処分までの流れ
- 外部の人から上記3つの機関に通報が届く、
- 関係機関は横に連携し、調査、指導が行われる。
- 消費者庁又は都道府県知事は、対象者に弁明の機会を与える
- 措置命令を下す。
- 措置命令に従わない場合は課徴金をかす。
なお、景品表示法に関する相談、通報等は、消費者庁のホームぺージでできます。
輸入と景品表示法
上記の通り、商品を日本国内で販売するときは、消費者を「誤認」させる可能性がある表記や販売方法を避けることが重要です。最後に、輸入ビジネスをする上での景表法との付き合い方を考えてもみましょう。
景品表示法は、日本の「国内法」であるため、輸入許可後、日本国内で商品を販売するときに関係します。特に輸入品は「原産国の誤認表示」と関係してきます。
例えば、景品表示法の原産国表示に関する規制は、次のように決めらています。
原産国とは?
その商品を製造するときに「実質的な変更をもたらす行為をした国」です。
原産国の表示義務
原産国の表示「義務」はないです。ただし、商品の説明文章、パッケージ等の表示方法を通じて消費者に対して「優良誤認」させる可能性があるため、一般的には原産国を表示します。
どういう場合に原産国の不当表示になる?
- 日本国内で製造されている商品なのに、パッケージや表記方法等により、あたかも外国産であるかのように表示すること
- 外国で生産された商品について次のように表記すること→原産国以外の国旗等を表示、原産国以外の事業者の商標等を表示、文字表示が日本語で表示等をし、あたかも日本産であるように表示すること
原産国に関する総論
基本的に輸入時の関税法、輸入後の景品表示法ともに「原産国の表示」は義務化されていません。ただし、この部分は、申告した税関官署によっても見解が異なり、輸入申告した商品の内容を総合的に判断した結果、税関職員が「原産国の表示」を求めたり、訂正させたりする場合があります。
例えば、中国から貨物が届いている。インボイスには、MADE IN CHINAと記載されている。ところが実際の商品を確認すると、外装のダンボール等に「Made in Africa」等の表記があるなどです。
このような場合は、税関は、輸入者に「内容点検」を指示し、必要な場合は、保税地域から引き取る前に商品の外装等に正しい原産国を記したシール等を貼り付けるように指示します。よって、この辺りを考えると、やはり、輸入時から正しい原産国表示をするべきだと考えます。
よくある疑問
をご覧ください。
まとめ
- 景品表示法は消費者をだます事業者を規制する物
- 景品表示法には、商品の偽りを防止すること。偽り部分の競争ではなく、商品自体の競争を促す目的がある。
- 景表法は、故意や過失に関係なく事実に対して処分される。
- 事業者は、正直な商売をすることが重要

 この記事をお気に入りに登録
この記事をお気に入りに登録
カテゴリ
タグ一覧
新着記事の一覧
記事を検索する
| 種別 | 積み地 | 揚げ地 | 品目 | 輸送モード |
| 法人 | 大阪 | 厦門 | ビール 2トン | 海上輸送 |
| 法人 | 天津 | 金沢 | ビニールハウス資材 40トン | 海上輸送 |
| 法人 | 青島 | 埼玉県川口市 | 大人用おむつ | FCL |
| 法人 | 大阪 | 厦門 | ビール 2トン | 海上輸送 |
| 法人 | 天津 | 金沢 | ビニールハウス資材 40トン | 海上輸送 |
| 法人 | 青島 | 埼玉県川口市 | 大人用おむつ | FCL |




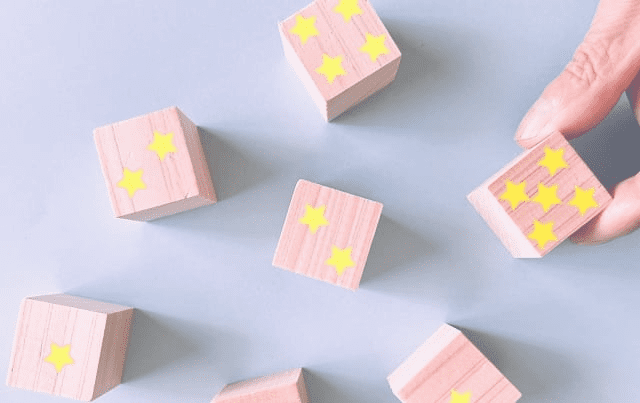
 目次
目次