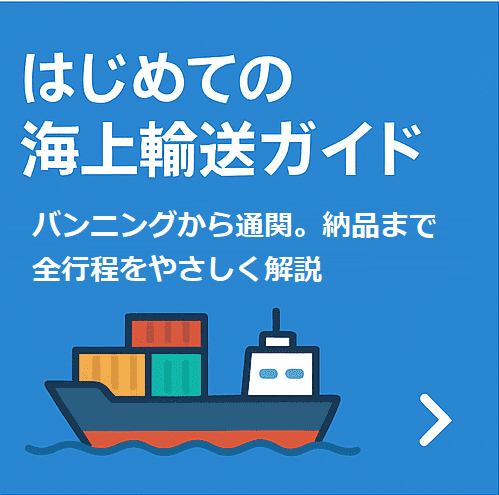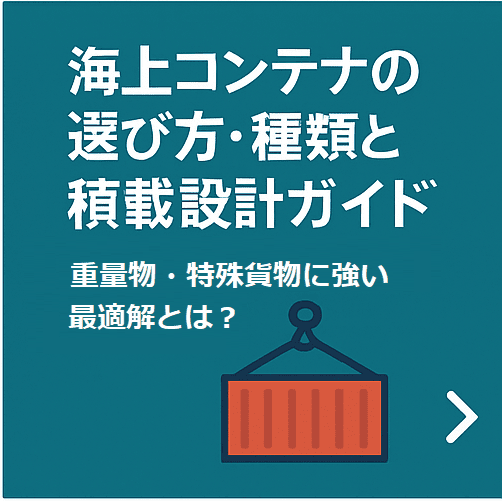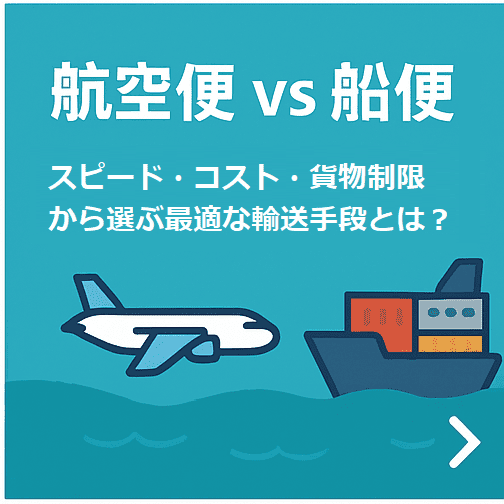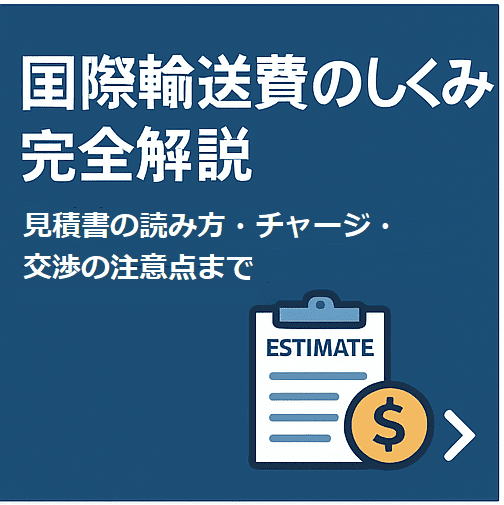「CTRL」+「D」を押すと、HUNADEをブックマークできます!
IMDGコード 完全ガイド|海上危険物輸送の実務ポイント
海上輸送では、火災、爆発、有毒ガスの発生など、危険物が原因となる事故が少なくありません。これらの事故は、船員や港湾作業者の命に直結し、船舶や港湾の操業にも重大な影響を与えます。そこで国際社会は、危険物の取り扱いを統一するためにSOLAS条約を採択しました。
こうした背景から、危険物を安全かつ統一的に扱うための実務規範として整備されたのがIMDGコードです。これは単なる条文ではなく、現場での判断基準や作業手順の指針にもなっています。
海上で危険物を輸送するすべての荷主は、この国際的なルールに従って輸送計画と書類を整える必要があります。
国際統一規則 IMDGコードの基礎
IMDGコードは、SOLAS条約の付属書を基に国際海事機関が定めた統一規則です。この規則は、定期船でコンテナ貨物として危険物を輸送する際に適用されます。
危険物の分類、容器の要件、積載の可否、ラベルの表示方法などが細かく決められており、国際輸送における共通の基準です。海上輸送に関わるすべての関係者は、このコードをもとに輸送の可否判断や書類の作成を行います。
これらの規定のうち、実務で最初に確認されるのがUN番号とクラス分類です。輸送の可否や書類作成は、すべてこの段階から始まります。
UN番号とクラス分類
危険物輸送の基本は、UN番号の確認から始まります。UN番号とは、危険物を種類ごとに分類するための国際的な番号です。この番号から、正しい品名(PSN)、危険物のクラス、包装基準、ラベル、積載条件がすべて決まります。UN番号を誤るとラベルも書類も間違い、積載不可や船積み拒否につながります。
次にクラス分類です。危険物はクラス1〜9に分類され、それぞれ性質が大きく異なります。さらに包装の強度を示すパッキンググループ(PG)がI〜IIIに区分され、危険度の高さを判断します。UN番号、クラス、PSN、PGが正確でない限り、正しい輸送は成立しません。
危険物クラス完全ガイド|IMDGコードの分類・PG・輸送可否を実務的に解説
ここまでで分類の仕組みを確認しました。次に、実務現場でこの情報をどのように入手し、確認すべきかを見ていきます。
UN番号・PSNの調べ方
UN番号、PSN(正しい船積み品名)、クラス、パッキンググループ(PG)の確認は、必ずSDS(安全データシート)のセクション14に基づいて判断します。SDSの情報が荷主の判断根拠となるため、その内容の正確性について荷主自身が責任を負う点は重要です。
また、IMDGコード冊子が手元にない場合は、以下の情報源が参照できます。
- 船会社・フォワーダーが提供している IMDG 検索ツール
- 日本の化学物質情報(NITE-CHRIP データベース)
- メーカー・輸出者が提供する最新版SDS
荷主の仕事は「危険性の見落としをゼロにすること」であり、ここが輸送トラブルの最大の防止策です。UN番号やクラス情報を把握した後は、実際にそれをもとに容器選定や書類作成を進めます。ここからは荷主の義務として求められる具体的な対応を整理します。
荷主の義務(包装と書類)
荷主には、危険物がIMDGコードの規定を満たす状態にする義務があります。まず容器はUN規格に合致したものを使用し、容器にはUNマーキングを表示します。UNマーキングから容器の種類、性能、用途、製造年などを読み取ることができます。
危険物の容器・梱包・ラベル完全ガイド|UN容器・表示義務・実務チェック一覧
次に危険物申告書(DGD)です。この書類にはUN番号、PSN、クラス、PG、数量、応急処置情報を正確に記載し、署名する必要があります。DGDは船会社が積載可否を判断する根拠となるため、誤記は即座に船積み拒否につながります。さらに、貨物によっては日本海事検定協会による収納検査が必要です。検査対象の品目は限られますが、対象となる場合は検査証を提出しなければ船積みできません。
海上危険物の申告フロー完全版|DGD・SDS・Approvalの提出手順と時間軸
船会社 Approval(積載承認)の実務プロセス
危険物コンテナを予約する際は、通常のブッキングとは別に、船会社の危険物積載承認(Approval)を得る必要があります。
実務の流れは以下のとおりです。
- ブッキング前または同時に、SDS と DGDドラフトを船会社へ提出
- 船会社は IMDGコード上の分類・包装・隔離条件を確認
- 問題がなければ承認(Approval)が出される
Approval には数日〜1週間以上かかることもあり、ブッキングの締切(CYカット)より前に承認が出ていることが絶対条件です。特に、初めて扱う危険物や、過去に事故のある貨物は審査に時間がかかる傾向があるため、リードタイムの余裕が必要です。
承認が得られたら、次に重要なのは輸送中の安全確保です。特に表示と積付(隔離)のルールは、事故防止の最後の砦です。
安全輸送のルール(隔離と標識)
危険物の輸送では、ラベルとマーキングの正確な表示が必要です。これは、船員や港湾作業者が貨物の性質を一目で判断するための情報です。さらに重要なのが「隔離」の概念です。
危険物同士や一般貨物との混載を判断する際には、IMDGコードに定められた隔離表を使用します。性質の異なる危険物を近い場所に配置すると、化学反応を起こす可能性があるためです。隔離基準を誤ると事故につながるため、フォワーダーや船会社はこの基準をもとに積載場所を調整しています。
隔離の実務的な影響
隔離基準は安全のために不可欠ですが、実務ではコストやスケジュールに直接影響します。
例えば…..
- 特定クラスはデッキ上(船外)にしか積載できないため、船会社が断るケースや運賃が上がるケースがある
- 他の危険物と混載できないクラスの場合、LCL(混載)輸送が不可となり、FCL専用コンテナが必要になる
- 隔離区分が厳しい場合、他の貨物との位置関係から配船(スペース)自体が取れないこともある
隔離は「安全ルール」であると同時に、輸送コスト・納期にも影響を与える要因です。国際的なルールを守るだけでは十分ではありません。日本の港湾や保管施設では、別途、国内法令が適用されるため、それらを併せて理解する必要があります。
国内法規との連携
危険物の輸送では、国際規則だけでなく国内法規にも従う必要があります。港則法では、危険物を積載した船舶が港へ入港する際の手続きを定めており、事前申請が必要です。さらに消防法では、港内ヤードでの危険物の保管方法が決められています。高圧ガス保安法や火薬類取締法など、品目に応じて多くの法律が適用されるため、輸入前後の国内物流の計画に大きく影響します。危険物輸送では、国際規則と国内規則の両方に適合することが求められます。
国内法規(港則法等)の手続きモデル
港則法に基づく、危険物を積載したコンテナの入港・荷役申請は、通常は船会社または船主代理店(ライナーエージェント)が行います。
荷主が行うべきことは以下です。
- DGD(危険物申告書)に正確な情報を記載し、期限までに提出する
- SDS、UN番号、クラス、数量など、港則法申請に必要な情報を正確に提供する
これらが不備の場合、港側から入港許可が出ず、コンテナが船に積めない/荷揚げできないという重大な遅延につながるため注意が必要です。
このように、IMDGコードは国際的な枠組みとして機能しますが、実際の輸送では国内法や港湾手続きとの連携が不可欠です。全体像を整理して初めて、現場で確実な判断ができるようになります。
まとめ
危険物の輸送では、UN番号の判断、正確な書類作成、容器の選定、隔離基準の遵守など、多くの実務が必要です。IMDGコードは、海上輸送における危険物取り扱いの中心的な規則であり、すべての判断の基準です。
荷主は、SDSを基にUN番号を正確に確認し、適切な容器とラベルを準備し、DGDを正しく作成することが最も重要です。また、港則法や消防法など国内法規の手続きを忘れず、輸送計画全体を整理する必要があります。危険物輸送はリスクが高い分、規則を守ることで安全に輸送ができます。

 この記事を登録
この記事を登録
 目次
目次