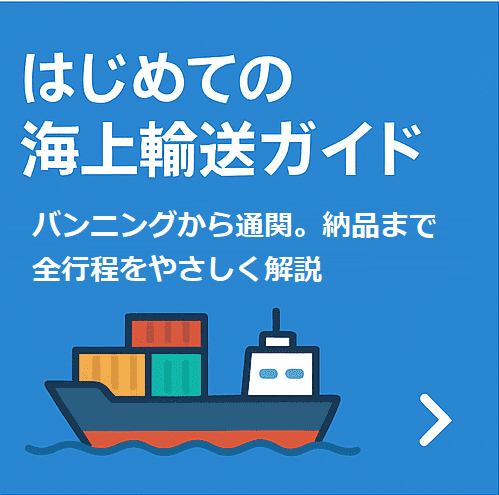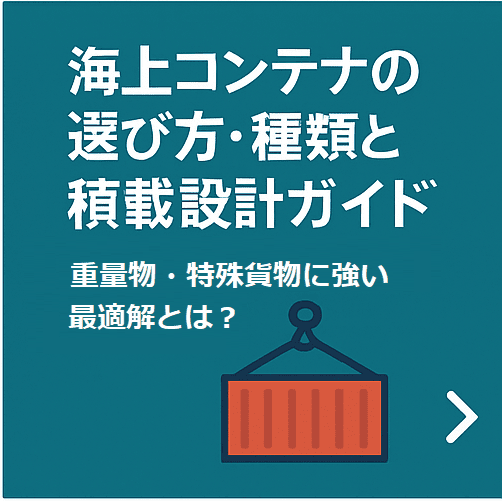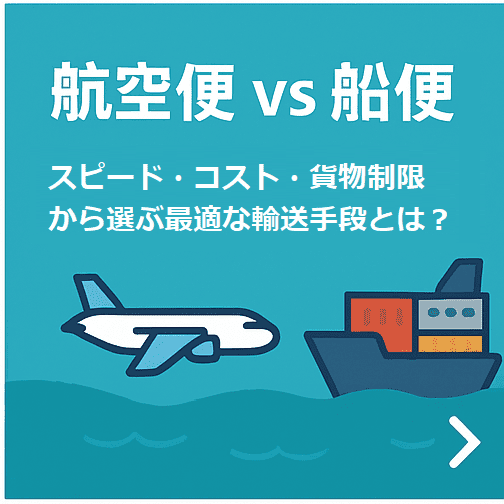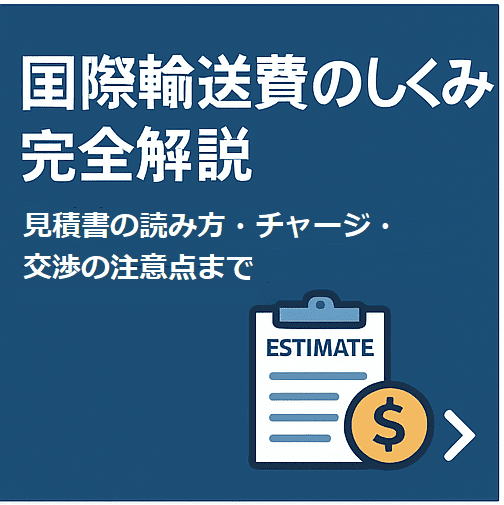「CTRL」+「D」を押すと、HUNADEをブックマークできます!
初めてのフォワーダー利用ガイド|小口輸入者が“宅配便から切り替える”ための具体手順と必要情報
本記事は「小口輸入の最適化シリーズ」です。第3回です。
宅配便からフォワーダーへ切り替える時に起きやすい戸惑い
小口輸入者が最初に感じる戸惑いは「どこから始めればよいのか分からない」という点です。宅配便は預けるだけで輸送・通関・配達まで進む仕組みですが、フォワーダーを使うと“必要な情報”が一気に増えます。
ただし、手順そのものは複雑ではなく、整理して準備すれば難しさはありません。切り替えることで費用が安定し、輸送方式の選択肢が広がるという効果もあります。
まず最初に“貨物の情報”をそろえる
フォワーダーに見積りを依頼する前に、最低限そろえるべき情報が決まっています。この段階が曖昧だと見積りが不正確になり、後の工程で混乱が生じます。
必ず必要になる情報は次の通りです。
- 荷物の種類
- 梱包サイズ(縦×横×高さ)
- 個数
- 重量(実重量)
- 希望納期
- 発地と着地
- 希望する輸送方式(未定でも問題なし)
この七つが揃うことで、初めて「正しい土台」に立つことができます。
フォワーダーが必要とする“追加情報”
初めての小口輸入者がつまずきやすいのが、この追加情報です。必要性が分かっていないため、後から確認作業が増えがちです。
追加で求められることが多い項目は次の通りです。
- インコタームズ(EXW、FOBなど)
- 商材の通関区分(一般貨物かどうか)
- 発地側の作業条件(集荷の有無)
- 書類の有無(インボイス、パッキングリスト)
- 原産国
- 税関で特別な規制があるか(食品や電気製品など)
特にインコタームズは費用負担の境界線を決めるため重要です。
例えば、FOBであれば「国際運賃以降」を輸入側が負担しますが、EXWであれば「工場から港までの現地集荷費用」も輸入者側の負担になります。切り替え時の誤解はほぼこの点に集中します。
インコタームズ簡易一覧表
| 用語 | 発地側の誰が費用負担? | 集荷は必要? | 小口輸入との相性 |
| EXW | ほぼ全部輸入者 | 必要 | △(手配が増える) |
| FOB | 輸入者は国際区間から | 不要 | ○ |
| CIF | 輸入者は日本側から | 不要 | △(保険内容に注意) |
詳細は、インコタームズを理解するで確認しましょう!
見積依頼の“正しい伝え方”
情報が不足した状態で見積りを依頼すると、返ってくる金額が大雑把になり、判断が難しくなります。正しい依頼の手順を知っておくことで、初回から精度の高い見積りを受け取ることができます。
重要なポイントは次の三つです。
- 最初にサイズ・重量・インコタームズを伝える
- 不明点はそのままにせず“提案してほしい”と伝える
- 総額・日数・費用内訳を基準に判断する
見積り比較するときは、次の費用項目に特に注目すると誤判断を防ぎやすくなります。
- 最低料金
- 通関手数料
- 国内配送料
- CFSチャージ(海上LCL)
- デバンニング料(海上LCL)
- 書類作成費
どこまでが「含まれているのか」を確認することが、後から費用が増えるリスクを避ける最重要点です。

見積りの精度は、初回よりも2回目、3回目と回数を重ねるほど上がります。最初から完璧を求める必要はありません。
実際の輸送の流れ(初回時の標準パターン)
宅配便との最大の違いは「細かい工程が見える」という点です。しかし構造を知ってしまえば、思ったほど難しくありません。
一般的な流れは次の通りです。
- 発地での集荷(自社手配または現地業者)
- 発地倉庫への貨物搬入
- 書類確認(インボイス・パッキングリスト)
- 国際区間の輸送(航空または海上)
- 日本側での通関
- 国内配送
- 納品
宅配便ではこの工程がすべて自動化されていますが、フォワーダーでは「工程が見える」だけで、作業自体が難しくなるわけではありません。

フォワーダーでは、貨物保険を輸入者側で手配するケースもあります。輸送中の破損や紛失に備えるため、初回時に保険の有無を確認しておくと安心です。
初めての切り替えで起きやすい“3つの失敗”
初回切り替えでは、次の三つの失敗が特に多く見られます。
1.サイズ情報の不足
→ 容積計算ができず、後から追加費用が発生しやすい。
2.インコタームズの誤解
→ 現地費用の負担範囲を理解せずに始め、想定外の費用が出る。
3.納期の誤読
→ 航空と海上では日数の桁が違い、計画とのずれが発生する。
この三つは非常に多くの小口輸入者が共通してつまずく部分です。
切り替え前に確認すべきチェックリスト
確実に切り替えを成功させるためのチェック項目です。
- 荷物のサイズを正確に測ったか
- 各箱の重量を把握しているか
- インコタームズをサプライヤーに確認している?
- 納期の優先度を整理したか(早い・普通・急がない)
- 商材に特別な規制がないか
- 複数方式の見積比較を行ったか
- 貨物保険の有無を確認したか?
これらを事前にそろえておけば、初回から大きな混乱を避けられます。
次の記事では“100〜300kgの最適解”を紹介
本記事では、切り替えの手順と必要情報を整理しました。次の記事では、特に悩む人が多い100〜300キロ帯について、どの方式が最適になりやすいのかを具体的に解説します。「自分の場合はどれが最適か?」という疑問に答えられる内容になります。
あなたの貨物(重量・サイズ・発地・インコタームズ)を教えていただければ、航空・海上のどちらが合理的か、構造に基づいて解説できます。判断に迷う場合は一度ご相談ください。

 この記事を登録
この記事を登録
 目次
目次