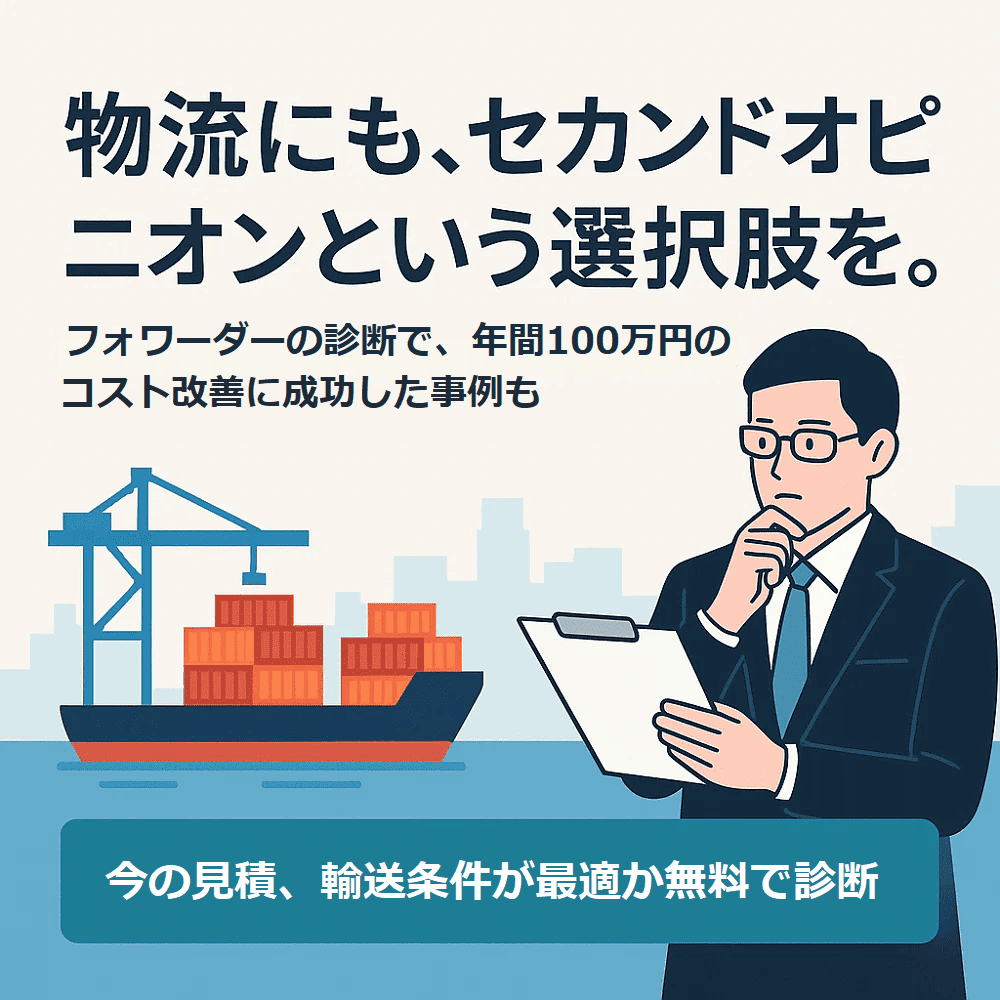中国側の現場で何が起きているか知っていますか?
中国と日本を結ぶ国際輸送では、多くのトラブルが「中国側」で発生。しかも、それらの多くは、荷主がリアルタイムで気づけず、問題が大きくなってから初めて発覚することが多いです。
「本船に間に合っていなかった」「通関で貨物が止められていた」「出荷済みと聞いていたが、実はまだ倉庫にあった」──こうした問題はよく起こります。背景には、現地業者との連携不足や、書類の不備、輸出規制の変更、検査のルールの違いなど、さまざまな要因があります。
2025年現在、中国の港によっても状況は異なります。たとえば深圳(塩田)はLCL(混載)の頻度が高く、青島ではFCL(コンテナ単位)の出荷が多く、月末はコンテナ不足が起きやすい傾向があります。港の特徴と輸送方法が合っていないと、スケジュールにも影響します。
さらに、中国では輸出入の規制が強化されており、HSコードの扱いや許可が必要な品目の見直しが頻繁に行われています。そのため、書類の整備や事前確認の重要性はこれまで以上に高まっています。
この記事では、実際のトラブル例をもとに、荷主が事前に知っておくべきリスクとその対策についてわかりやすくまとめます。
ケース1:混載便のスケジュールが勝手に変更された
あるアパレル会社は、CIF契約で広州からLCL便を使って商品を輸入していました。ところが、現地で他社の貨物が集まらず、自社貨物も便に載せられないまま2週間遅延。
荷主が知ったのは、出荷予定を大きく過ぎてから。「もう船に乗った」と思っていたのに、まだ倉庫にあったのです。
背景
- 混載は複数社の貨物で1便を構成するため、他社の遅れに巻き込まれやすい
- CIF契約では、スケジュール変更が事後報告になりやすい
対策
- 出荷前に「スケジュール確定済みか」をフォワーダーに必ず確認
- FOB契約であれば、自社フォワーダーから直接情報取得・調整が可能
ケース2:HSコード違いで通関がストップ
電子部品を輸入していたあるメーカーでは、中国の通関時に「この品目は輸出規制対象」と指摘され、港で1週間以上貨物が止まりました。
実は、同じHSコードでも日本と中国での扱いが違っていたのです。
背景
- 中国では技術品・電子部品・工業製品などは許可制・届出制が多い
- HSコードの誤認で通関が止まるのはよくあるトラブル
対策
- 中国側通関業者に「このHSコードは輸出に問題ないか」を事前確認
- 必要なら、サプライヤーに追加書類(許可証・適合証明)を依頼
ケース3:「出荷済み」と聞いていたのに出ていなかった
玩具メーカーのケース。サプライヤーから「もう出荷済み」と報告を受けていたものの、実際は現地倉庫に貨物が残っていました。原因はINVOICEとPACKING LISTの不備で通関が進まなかったこと。
背景
- サプライヤーが輸出書類に不慣れで、テンプレートも未整備
- 通関業者が書類ミスを指摘したが、修正に数日かかった
対策
- INVOICEとPACKING LISTに不備がないか、事前にテンプレートを共有
- 書類が貨物と一致しているか、検品時点で確認

このようなトラブルを防ぐには、INVOICEとPACKING LISTに書かれている情報(品目名・数量・重量・サイズ・HSコードなど)が、実際の貨物と完全に一致しているかを事前にチェックすることが重要です。通関の遅れは、こうした書類ミスからよく起きます。
トラブルの4大要因と予防
| 原因カテゴリ | よくある事例 | 予防策 |
| 港の混雑 | LCLの便遅延、積み残し | 港の選定と週末回避 事前スケジュール確認 |
| サプライヤー対応 | 書類ミス、出荷遅れ | 書類テンプレ提供、進捗の定期確認 |
| 通関 | HSコード不一致、規制違反 | 通関業者との事前すり合わせ |
| 情報の不透明性 | CIFで状況把握不可 | FOB/EXW契約で主導権確保 |
書類ミスを防ぐ5つのチェックポイント
- 品目名は具体的か?(例:Electronic device → USB Controller Board)
- HSコードは中国での扱いを確認済みか?
- 数量・重量・寸法が実物と一致しているか?
- 原産国・企業情報は正しいか?
- 型番・製品仕様が揃っているか(税関照合時に重要)
CIFとFOB/EXWの“対応力”の違い
| 契約形態 | 情報入手 | スケジュール調整 | トラブル対応 |
| CIF | 売り手経由で遅い | 不可 | 売り手任せ |
| FOB/EXW | 自社が即確認可 | 可能 | 自社主導で動ける |
自社がフォワーダーを選び、現地ネットワークと直結することで、輸送の「見えない部分」が一気に可視化されます。
まとめ:トラブルの種は“見えない”ところにある
中国側で起きるトラブルは、「価格の問題」ではなく「情報の質とタイミング」の問題です。
だからこそ、輸送の主導権を自社で握り、現地との連携を強化することが、納期とコストの安定化につながります。
“出荷済み”を信じる前に、“確認できる体制”を作りましょう。
次の記事「第4回|どの輸送手段が最適か?」
おすすめのサービス
基幹記事
貿易学習コースの一覧
分野別記事
関連記事
◆スポンサード広告


 目次
目次