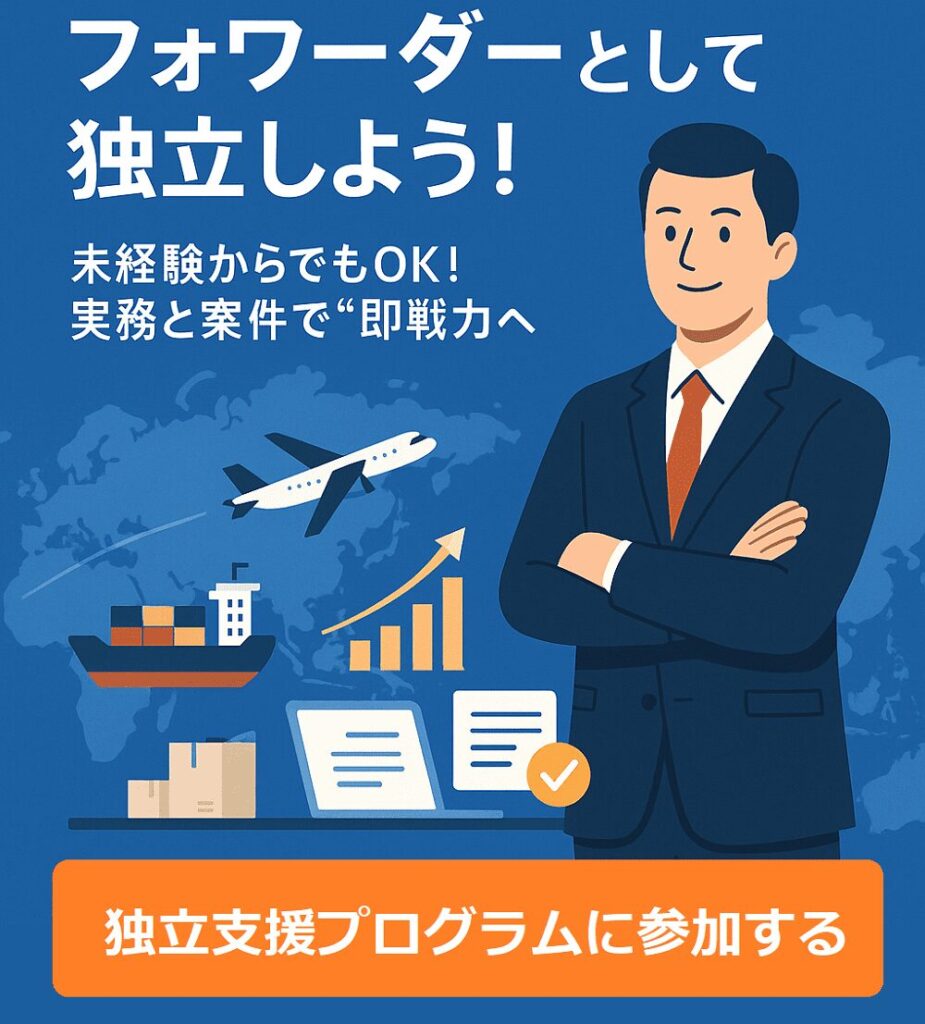「CTRL」+「D」を押すと、HUNADEをブックマークできます!
AI時代に選ばれるフォワーダー
ChatGPTやRPAなど、テクノロジーが急速に進化するなかで、「このままの働き方でいいのか?」と不安を感じているフォワーダーの方も多いはずです。とくに10年前後の実務経験を積んできた中堅層ほど、過去に身につけたスキルがAIに取って代わられる可能性に直面しています。
この記事では、AI時代においても“選ばれ続けるフォワーダー”になるために、どのようなスキルが必要か、その育て方や活用例を国内外の事例とともに紹介します。
AIに置き換えられやすい仕事とは?
物流の仕事の中には、AIやRPAで置き換えられやすいものがあります。たとえば以下のような業務です。
- インボイスやパッキングリストの作成・入力
- 船積書類のチェックや転記
- アライバルノーティスやB/L(船荷証券)の出力
- 貨物の追跡やスケジュールの管理
これらは「決まった手順どおりにやる作業」で、自動化が進みやすい分野です。実際、日本ロジスティクスシステム協会の2024年の調査では、物流業務の約40%が自動化の対象とされています。

型に当てはめれば完了する業務は全て終了です。パターンを学習したAIには誰誰も勝てません。残念ながら20年、30年のキャリアがあっても同じです。まだAIに勝てると考えるのは間違いです。パターン型の業務は、どんな分野でもとってAIに代わられる可能性があります。(弁護士の仕事や裁判官の業務ですら)
逆に、AIでは代わりがきかない仕事は?
AIでは難しい、人間にしかできない仕事もあります。今後も必要とされるのは、こんなスキルです。共通するのは、ある定型的なパターンに落とし込めないものです。人間の感情、密な関係性から生まれる強力なコネクションなどです。
- トラブルが起きたときの判断(例:遅延時の代替ルートの提案)
- 荷主との信頼関係づくりとその維持
- 海外の業者など複数相手との柔軟な調整力
- 国ごとの商習慣や文化に合わせた対応・提案力
- 海外の個人フォワーダーと信頼ネットワークを作る力
ここで重要なのは、あなた自身の「視座」を上げることです。物流は、単なる輸送コストにとどまりません。商品価格に占める物流コストの割合は非常に大きく、荷主企業の営業成績や利益率に直結する戦略的要素です。つまり、物流を制する者は、商品の競争力そのものに関われるということ。
そのため、「価格が安いこと」だけを前面に押し出す営業は、荷主にとって意味を持たなくなりつつあります。物流部分しか見えておらず、全体最適の視点がない──そう判断されれば、選ばれないのは当然です。
単なる「物流屋」ではなく、物流を起点に荷主の経営課題に踏み込める存在へ。コスト構造、納期、在庫管理、販売戦略など、周辺領域も含めて最適化できるパートナーとして信頼されてこそ、これからの時代に選ばれ続けるフォワーダーです。

AIが得意な所で勝負するのはダメです。(正面からぶつかる)AIが苦手な部分を理解し、いわば斜め45度から勝負するのです。
「AIに負けない」ではなく「AIを使いこなす」力をつける
AIを「敵」と考えるのではなく、「どこに使えるか」を考えることで、仕事の効率や質を上げることができます。これからのフォワーダーには、AIを“うまく使う力”が大切です。
以下のような使い方が、現場で役に立ちます。
ChatGPTで英文メールや提案文を作る
→ 英語が苦手でも、短時間で文章がまとまります。
よくある質問をAIにまとめてもらい、社内マニュアルに使う
→ 荷主対応の手間が減ります。
案件ごとの調査をAIに任せる(関税率、通関条件など)
→ 自分は判断や提案に集中できます。
RPAやマクロでルーチン作業を自動化する
→ 書類作成や転記の時間を減らし、営業活動に時間を使えます。
AIで物流のニュースや競合情報をまとめてもらう
→ 提案や会話のネタが増えます。
さらに一歩進んだAI活用──「経営支援型フォワーダー」への進化
物流は、商品価格に占める割合が大きく、荷主企業の利益に直結する要素です。したがって、ただ「安い物流を提供する」のではなく、AIの力とご自身の経験を融合させて、荷主の経営に寄与する提案ができるかどうかが今後の大きな分かれ目です。どちらが欠けてもNGです。
そんな視点に立てば、AIは次のような使い方が可能です。
経営層に向けた提案資料の構成支援
AIにより「物流コスト分析」「最適インコタームズの提案」「在庫戦略の見直し案」などを要点整理させることで、提案の質が格段に向上します。
業種別・課題別の成功・失敗事例を収集し、提案に活用
「御社と同じ業界でこのように改善した例があります」と説得力ある説明が可能になります。AIによる事例収集が、競合との差別化につながります。
輸送戦略の全体最適を試算(年間コスト・納期・倉庫圧縮)
→ 単発の「安さ」ではなく、年間視点で「利益に直結する物流設計」が可能になります。AIはその試算を補完してくれる心強いパートナーです。
このように、「AIにできることはAIに任せる」「自分にしかできない仕事に集中する」だけではなく、AIを“経営提案の武器”として活用する視点があれば、荷主からの見られ方も根本的に変わってきます。

スーパーの安売り営業であれば、あなたを選ぶ理由はないと思います。
AI活用スキルを実務で伸ばす習慣
AIを使える力は、一度に身につくものではありません。でも、普段の仕事の中に少しずつ取り入れることで、自然とスキルになります。
すぐに始められる取り組みはこちら
- ChatGPTで作成した文例や対応メモを週1回SNSで発信
- 荷主とのやり取りで出てきた質問を、社内マニュアルとしてAIで整理
- AIがまとめた輸送ニュースや業界動向を週次レポートにして共有
- 月1回、自動化やAI活用に関する勉強会・ウェビナーに参加
- AIを使って自社提案資料のフォーマットを作り、営業時間を短縮
こうした習慣は、最初は慣れが必要ですが、半年〜1年後には「フォワーダー×AIを使いこなせる人材」として社内外から信頼を得る武器になります。
スキルは“日常の積み重ね”から“未来の武器”へ
こうしたAI活用の習慣や実践は、目の前の業務改善にとどまりません。続けることで、それ自体が「キャリアの選択肢を広げる力」になっていきます。
将来的な独立や副業にもつながるスキル資産
日々の業務の中で身につけたスキルは、いずれ「副業」や「独立」といった次のステップでも役に立ちます。
たとえば、副業で荷主案件を紹介して報酬を得るモデルでは、信頼関係を築ける力や交渉力が重要です。また、提案資料をまとめる力や、SNSなどでの発信経験も、「営業力」として強みになります。
つまり、「今」の仕事で育てたスキルは、「将来の自分を守る資産」でもあるのです。
まとめ
- AIで置き換えられるのは、定型業務や単純処理だけ
- 判断・信頼づくり・調整・提案は人にしかできない強み
- AIを使いこなす習慣が、業務効率と評価を引き上げる
- 日々の発信・記録・学習が、キャリアの大きな差になる
- こうしたスキルは、将来の副業や独立にも直結する
もし「もっと自由に、もっと正当に評価されたい」と感じているなら、以下の記事もご覧ください。
次の記事「フォワーダー営業力を可視化する6つの実践法」

 この記事を登録
この記事を登録
 目次
目次