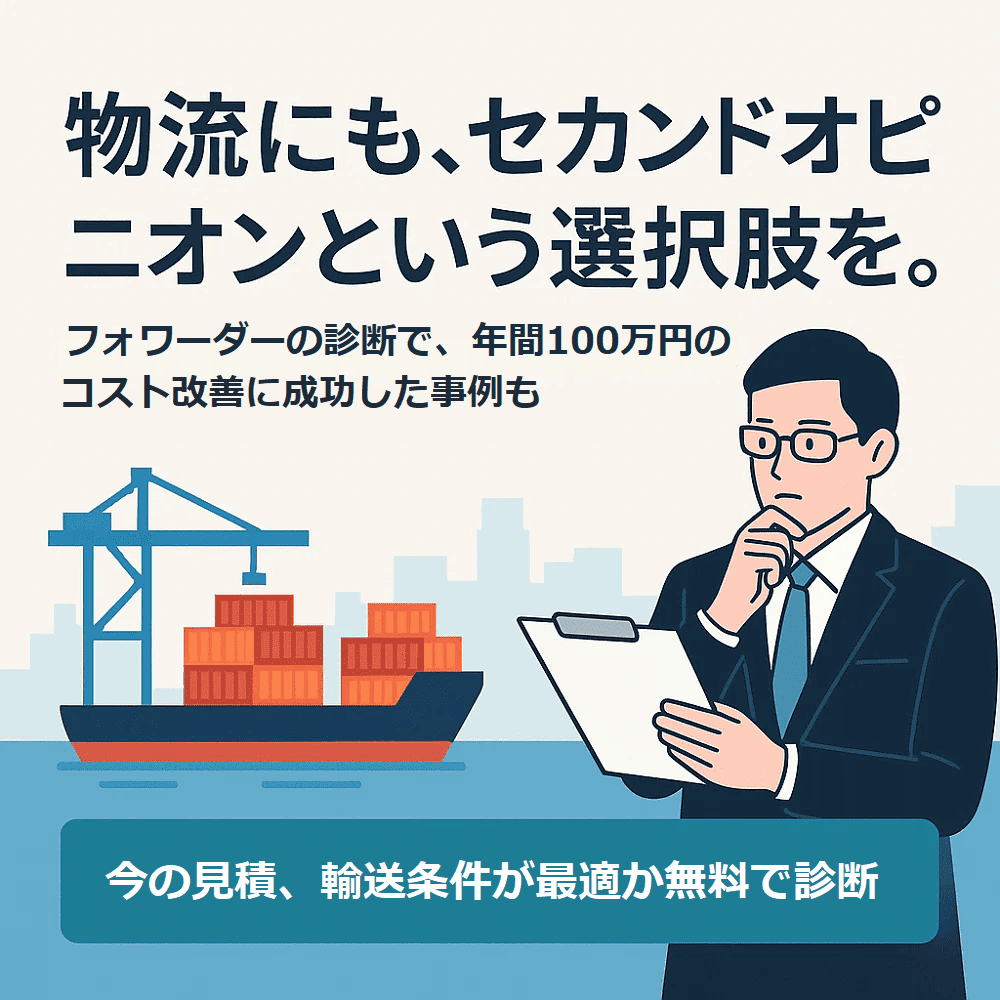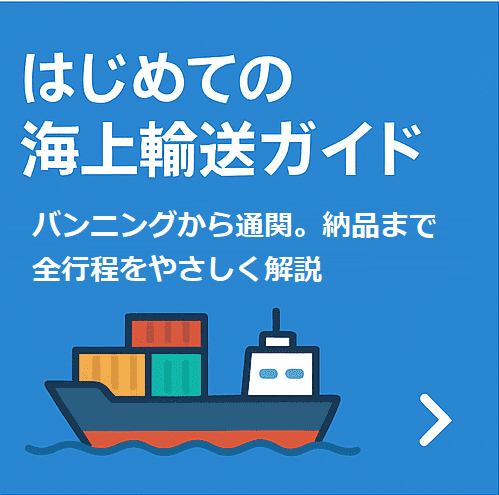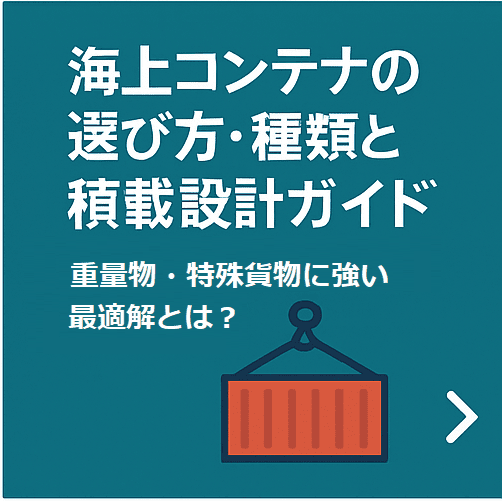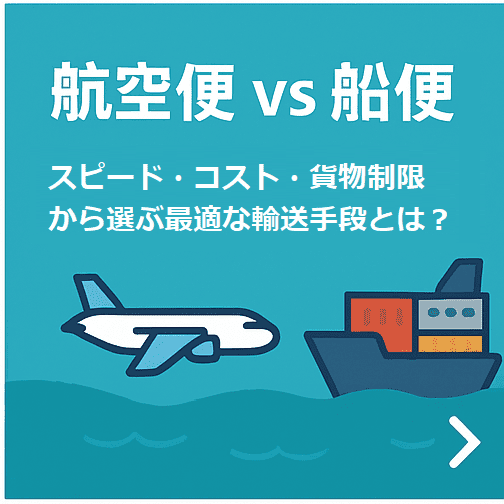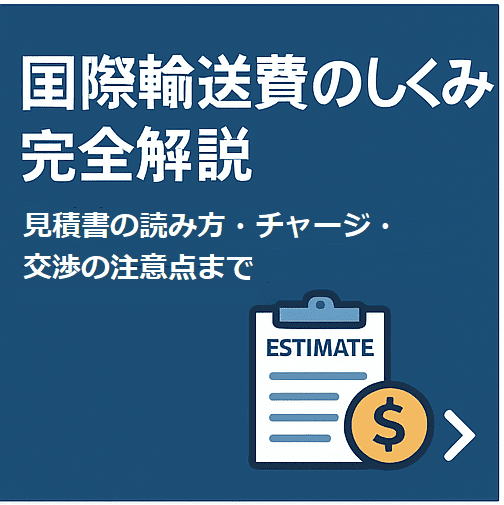「CTRL」+「D」を押すと、HUNADEをブックマークできます!
有事に備える関税救済制度ガイド|災害・事故・輸送停止時に活用できる関税法・定率法・特例制度のすべて
はじめに
地震、台風、感染症、港湾閉鎖などの突発的な災害は、サプライチェーンを寸断し、企業の通関・輸送体制に深刻な影響を与えます。こうした非常時に、どの制度をどの条文に基づいて使えばよいか、どんな書類を添付すべきかを即座に判断できる体制は、企業の「止まらない物流」を実現する生命線です。
この記事では、関税法・関税定率法・国税通則法などに定められた救済制度を網羅的に整理し、BCP(事業継続計画)の中でどう運用するかを具体的に解説します。
平時からの準備が非常時の差を生む――この原則を前提に、条文の正確な整合性を確認しながら、実務的観点でまとめます。
関税救済制度の全体像
| ケース | 制度名 | 法令根拠 | 主な要件 | 必要書類 | 実務上の留意点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 港・空港が停止 | 保税運送 | 関税法63条 | 保税地域間の外国貨物移送(税関長承認) | 運送申請書、運送目録、保税管理台帳 | 被災時は保税地域外への一時退避が可能(税関長の個別承認要) |
| 受入不能・契約解除 | 違約品の再輸出・廃棄 | 関税定率法19条 | 契約解除・返品時の輸入関税払い戻し | 契約書、返品証明、輸出入番号対応表 | 原状同一性を証明することが必要。誤って20条を引用しないこと |
| 保税中に破損・浸水 | 変質・損傷による減税・戻し税 | 関税定率法10条 | 災害・事故による価値減少 | 写真、第三者評価書、在庫台帳 | 損害額評価を第三者報告で裏付け。評価基準は税関審査に準拠 |
| 修繕・加工後の再輸入 | 再輸入減税 | 関税定率法11条 | 修繕・加工後に再輸入、修繕費のみ課税 | 修繕明細、請求書、輸出入記録 | 海外修繕との混同に注意。減税の対象は国内修繕費用のみ |
| 国内で加工・検査後に再輸出 | 再輸出免税 | 関税定率法17条 | 加工・修繕・試験後の再輸出 | 輸出入書類、同一性証明、製造記録 | 関税法42条ではなく17条が根拠。免税対象は要件を厳密に確認 |
| 17条に満たない場合 | 再輸出減税 | 関税定率法18条 | 軽微加工後の再輸出 | 同上 | 減税率の算出根拠を明示。帳簿管理の連動が鍵 |
| 混雑・検査遅延 | 輸入許可前引取り(BP) | 関税法73条 | 担保提供による先行引取り | C5400様式、担保書類 | 包括担保・特定担保を事前設定しておくことで発動が容易 |
| 納税資金繰り | 延納 | 関税法9条の2 | 納期限繰下げ | 延納申請書、担保、財務資料 | 銀行保証または担保提供により最長2ヶ月の延納可 |
| 災害による納付不能 | 納税猶予 | 国税通則法46条 | 被災後2か月以内申請、最長1年猶予 | 被災証明、資金繰表 | 期限延長との併用で柔軟運用が可能 |
| 申告・納付期限の延長 | 災害等による期限延長 | 関税法11条/国税通則法11条 | 災害で期限内処理困難 | 延長申請書、被災証明(任意) | 税関長承認後、正式に延長可能。平時に手順確認を |
| 誤納・過納の訂正 | 更正の請求 | 関税法9条の5 | 誤納・過納に対する訂正 | 請求書、証拠書類 | 法定期間内の請求が必須(原則5年) |
制度別の詳細実務ポイント
保税運送(関税法63条)
災害時に港や空港が使えなくなった場合でも、保税地域間で外国貨物を移送できます。税関長の承認により保税地域外への一時退避も認められることがあります。被災で保税台帳が滅失した場合は、B/Lやインボイス等で外国貨物であることを証明します。輸送後は必ず「保税運送完了報告書」を提出し、税関確認を受けることが求められます。
違約品の再輸出・廃棄(関税定率法19条)
契約解除や返品によって輸入貨物を国外に戻す場合、輸入時の関税を還付できます。誤って定率法20条(修繕関係)と混同しないよう注意が必要です。再輸出時には同一性を立証するため、シリアル番号・ロット・写真・在庫記録を整備しておくことが実務上の鉄則です。
修繕・加工関連(定率法11条・17条・18条)
- 11条(再輸入減税):国内で修繕した貨物を再輸入する場合、修繕費部分のみに課税されます。
- 17条(再輸出免税):国内で加工・試験後に再輸出した貨物に対して免税。保税上屋の許可(関税法42条)とは無関係。
- 18条(再輸出減税):17条要件を満たさない軽微な加工に対して減税が適用されます。 これら3条は相互に関連しており、原状同一性と帳簿管理が共通の審査基準となります。
損傷・破損(定率法10条)
地震・火災・浸水などで貨物が損傷した場合、税関長の承認により関税額を軽減可能です。損害評価書や現場写真を添付し、発生日時・原因・影響範囲を明確にする必要があります。立証不足は否認理由となるため、保険会社の査定報告を添付すると信頼性が高まります。
通関遅延・滞留(関税法73条)
輸入許可前引取り(BP)は、有事において特に有効な制度です。担保を提供することで貨物を先に引き取ることができ、港湾閉鎖時でも事業継続を確保できます。包括担保制度を利用すれば複数貨物にまとめて対応できます。銀行保証枠を平時から確保しておきましょう。
納税救済措置(9条の2・46条・11条)
延納・納税猶予・期限延長は、いずれも資金繰りと経営継続に直結する制度です。被災企業は、まず期限延長を申請し、続けて納税猶予を併用することで最大限の効果を得られます。担保提供は必須ではありませんが、提出すれば承認率が高まります。
更正の請求(関税法9条の5)
誤納・過納が判明した際、原則5年以内に更正請求を行うことができます。申告納税方式に基づき、誤りの証拠を添付して申請します。電子申請(NACCS)での受付も可能で、審査結果は電子通知で受領できます。
実務強化・BCP統合のポイント
- 担保管理の可視化:銀行保証枠や包括担保残高をERP・NACCS連携で管理。
- 災害時の代替通関ルート:港湾停止時に備え、保税運送+BPをセットで手順化。
- 証拠管理テンプレート:輸入番号↔輸出番号を紐づけるExcel/ERPテンプレートを整備。
- 期限延長・猶予の順序運用:被災直後はまず延長、復旧後に猶予へ切替える運用設計。
- 教育と訓練:通関担当・経理・倉庫管理者が年1回合同でBCP訓練を実施。
よくある誤記と否認リスク(再整理)
- ❌ 「再輸出免税=関税法42条」 → ✅ 正しくは関税定率法17条。
- ❌ 「違約品再輸出=関税定率法20条」 → ✅ 正しくは関税定率法19条。
- ❌ 「更正の請求=関税法7条の15」 → ✅ 正しくは関税法9条の5。
- ❌ 「期限延長=納税猶予」 → ✅ 異なる制度(関税法11条と通則法46条)。
- ❌ 「保税運送=自由な移送」 → ✅ 承認範囲内のみ有効(税関長の許可制)。
まとめ
関税救済制度は、災害時・事故時・感染症流行時など、あらゆる物流停止シナリオにおいて企業を支える「法的安全網」です。条文を正確に理解し、証拠と台帳を備え、税関との信頼関係を築くことで、迅速かつ確実な適用が可能になります。BCPの観点では、通関・物流・経理・法務の各部門が制度理解を共有し、SOP(標準作業手順書)に落とし込むことが最重要です。
シリーズ:BCP×関税×リロケーション
国際分業を「関税設計」と「BCP(事業継続性)」で最適化する実務ガイド。全体像 → 制度 → 体制 → 事例 → 対米実務の順で読めます。
- 第1回:リロケーション・スキームの全体像
- 第2回:再輸出免税と保税加工の違い
- 第3回:製造と通関を一体化するBCP戦略
- 第4回:中国+1から日本+1へ
- 第5回:中国企業の日本生産シフトと対米輸出
- 第6回:サプライチェーン強靭化補助金の実務対応
- 第7回:サプライチェーン停止に備える貿易BCP完全ガイド
- 第8回:港・空港・保税地域の被災リスクマップ2025
貿易学習コースの一覧

 この記事を登録
この記事を登録
 目次
目次