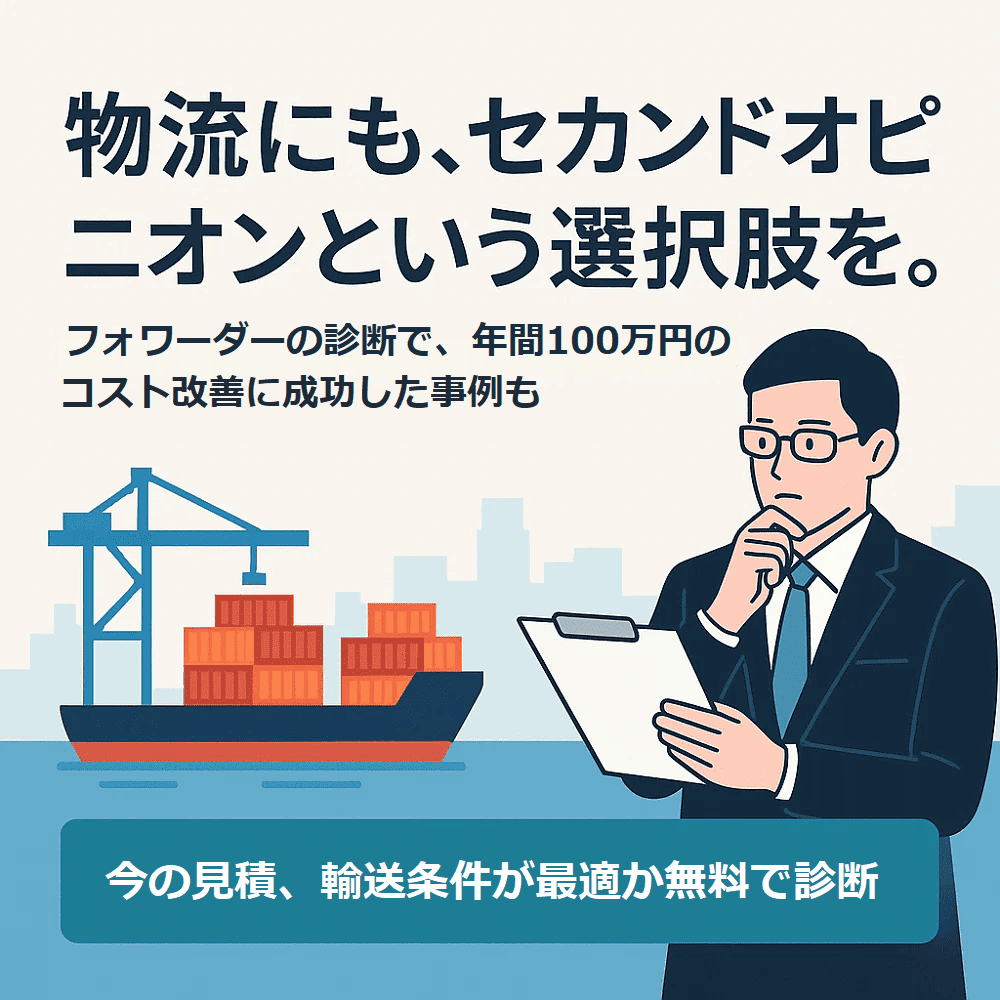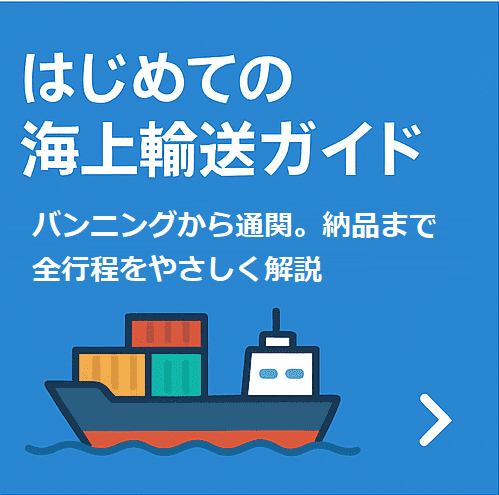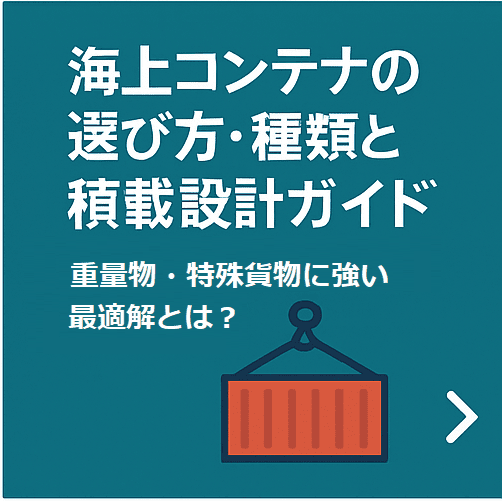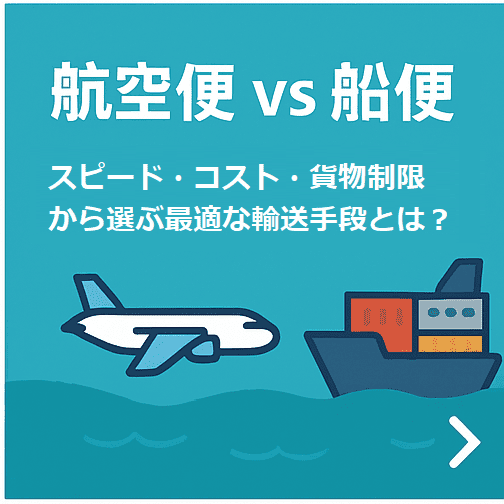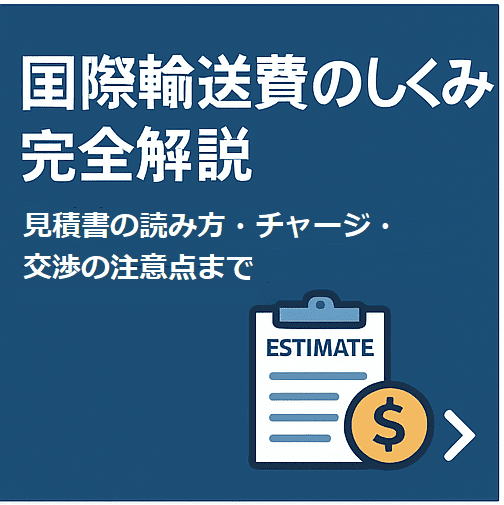「CTRL」+「D」を押すと、HUNADEをブックマークできます!
サプライチェーン停止に備える貿易BCP完全ガイド
――災害・感染症・制度変動に強い輸送設計と即応体制
はじめに|「止まらない物流」は偶然ではなく設計
コロナ禍や港湾ストライキで「輸送が止まる」現実を経験した企業が急増しています。BCP(事業継続計画)は単なる文書ではなく、通関・輸送・契約・人材・データの設計で成り立ちます。
この記事では、「災害・感染症・制度ショック」の3階層に対応する実務BCPの構築方法を解説します。
想定すべき3層リスクと実務への影響
| リスク層 | 主な要因 | 実務への影響 | 代表例 |
|---|---|---|---|
| 物理的リスク | 地震・津波・洪水・台風 | 港湾・道路閉鎖、貨物滞留 | 南海トラフ・首都直下 |
| 人的リスク | 感染症・ストライキ・人員逼迫 | 通関遅延、検査停滞 | コロナ、港湾労使紛争 |
| 制度的リスク | 制裁・輸出管理・システム障害 | 通関不能、支払遅延 | ロシア制裁、NACCS停止 |
これらのリスクの中でも、最も影響範囲が広く、今なお教訓が残るのが感染症による物流停止です。まずは「コロナショック」を通じて、物流停止の実態を振り返ってみましょう!
コロナショックに学ぶ“静かな停止”の実態
コロナ期には、航空減便で運賃が5倍に高騰し、貨物スペースが消滅しました。港湾混雑と検疫強化で輸入許可が1か月遅延し、リモート通関で承認リードタイムも2〜3日延びました。

教訓:港やシステムが動いていても、人の稼働と書類の流れが止まれば物流は止まるのです。
この経験を踏まえ、今後は「止まらない輸送経路」をいかに平時から設計できるかが鍵となります。以下では、海・空・陸の3輸送モードごとに、実務的な二重化の方法を整理します。
輸送ルートの二重化設計(海・空・陸)
海上輸送:港湾分散
東(東京・横浜)+西(名古屋・神戸・博多)の二系統化を推奨します。CONPASなど港湾の搬出予約システム(VRS)は、港・ターミナルごとに導入状況が異なるため、対象範囲とAPI連携可否を事前確認してください。
また、保税運送(関税法第63条)を活用すれば、被災港から別港・内陸CFSへの移送が可能です(税関長への申告と承認が必要)。
航空輸送:アライアンス分散
成田/羽田+関空/中部で同航路を二社契約し、BSA(Block Space Agreement)を半期更新で確保します。これにより運賃変動リスクを緩和できます。
陸送・内航:モーダルシフト
内航RORO船や臨海鉄道を代替ラインとして確保し、海陸複合ルートの訓練を年1回実施することが重要です。
物理的な輸送経路を確保しても、人や制度が止まれば物流は途絶します。
次に、感染症や制度変更といった「人・制度リスク」への対策を見ていきましょう。
感染症・社会的停止への対応(人・制度リスク)
検疫・通関を含む「人依存プロセス」の電子化
- eD/O・eB/L・オンライン検査予約を標準運用化(※全国一律導入ではないため要確認)
- 在宅通関向けVPNと電子署名IDを整備
「物流を止めない」企業は、人をリモートに逃がせる体制を事前に持っています。
データと書類の多層バックアップ
- NACCS/ERPデータをクラウド+暗号USBで二重保存
- Form 28/29(米国向け照会通知)や輸入許可書をPDF統一命名で管理
- 日本向け貨物ではNACCS帳票を保存対象に設定
- 原産地証明書・B/L・インボイスをリンク化(輸入申告番号↔輸出申告番号)
- 監査要求に即応できる「即時照合シート」を常備
データや書類の安全網を整えたうえで、次に重要なのが“輸送経路そのものの多層化”です。とくに国際輸送では、第三国経由(TS)やSea–Air輸送を組み合わせることで、有事でも出荷を維持できます。
Sea–Air・第三国経由(TS)による代替輸送
| ルート例 | 所要日数 | 利点 | 注意点 |
| 中国→釜山→日本(TS) | +2〜3日 | 港湾スト回避 | 再輸入扱い時の課税要件に注意(関税定率法第17条) |
| バンコク→シンガポール→関空(Sea–Air) | +3〜4日 | 航空停止時に有効 | 原産地証明再確認 |
| ベトナム→台湾→成田 | +4〜5日 | 感染症・台風回避 | AMSではなくNACCS/AFR連携が必要 |
Sea–Airはハブ(例:シンガポール)を軸にBSA確保+AFR申告で運用するのが安全です。
契約・保険・補助金の三点防御
輸送ルートや代替経路を整えるだけでは十分ではありません。いざという時にその体制を発動できるかどうかは、契約文言と保険設計にかかっています。ここでは、制度面での“守りの三点セット”を確認します。
- 契約条項(Force Majeure):代替輸送権・共同負担条項を明記する。
- 貨物保険:地震・津波・スト・感染症補償を特約化
- 補助金活用:経産省「サプライチェーン強靭化補助金」でBCP設備・代替輸送投資を検討
書類と契約の“文言”がBCP発動可否を左右します。
実務SOP|発動と判断の流れ
制度的な備えを整えたら、次は「いつ・誰が・どの順序で動くか」という現場手順の設計です。以下に、実際の発動フロー(SOP)を示します。
- トリガー監視:気象庁・港湾局・WHO通達を常時モニタリング
- 切替判断:T–48h時点で輸送・通関・営業が合同判断
- 通関代行切替:副委託先へ電子委任状を送信
- Sea–Air/フェリーへ転送予約
- 顧客通知:「Delay Notice」テンプレート発信
- 演習・レビュー:半期ごとにBCP演習とKPI更新
KPIと改善サイクル
一度体制を構築したら、それを継続的に点検・改善していくことが不可欠です。次の表は、BCPを定量的に運用するための主要KPIです。
| 指標 | 目標値 | 管理方法 |
| 代替輸送切替リードタイム | 6時間以内 | ログ自動記録 |
| 代替稼働率 | 95%以上 | 月次監査 |
| 書類復旧時間 | 24時間以内 | クラウド同期テスト |
| Sea–Air発動率 | 年1回以上 | 定期訓練 |
今すぐできる初動チェックリスト
指標を定めても、現場で実行できなければ意味がありません。以下は、今日から確認できる初動チェックリストです。
- 港湾・空港の二重契約を締結済みか
- 保税運送(関税法第63条)/再輸出免税(関税定率法第17条)の申請書式を保管しているか
- Sea–Airルート・レートを更新済みか
- NACCS/ERPデータの二重保存を完了しているか
- BCP演習を年1回以上実施しているか
まとめ
災害・感染症・制度変動は避けられません。重要なのは「止まる前に切り替えられる仕組み」をどれだけ事前に構築できるかです。
BCPは文書ではなく、通関・輸送・契約・データを統合した即応システムです。
次へ: 第7記事「港・空港・保税地域の被災リスクマップ2025」
シリーズ:BCP×関税×リロケーション
国際分業を「関税設計」と「BCP(事業継続性)」で最適化する実務ガイド。全体像 → 制度 → 体制 → 事例 → 対米実務の順で読めます。
- 第1回:リロケーション・スキームの全体像
- 第2回:再輸出免税と保税加工の違い
- 第3回:製造と通関を一体化するBCP戦略
- 第4回:中国+1から日本+1へ
- 第5回:中国企業の日本生産シフトと対米輸出
- 第6回:サプライチェーン強靭化補助金の実務対応
- 第7回:サプライチェーン停止に備える貿易BCP完全ガイド
- 第8回:港・空港・保税地域の被災リスクマップ2025

 この記事を登録
この記事を登録
 目次
目次