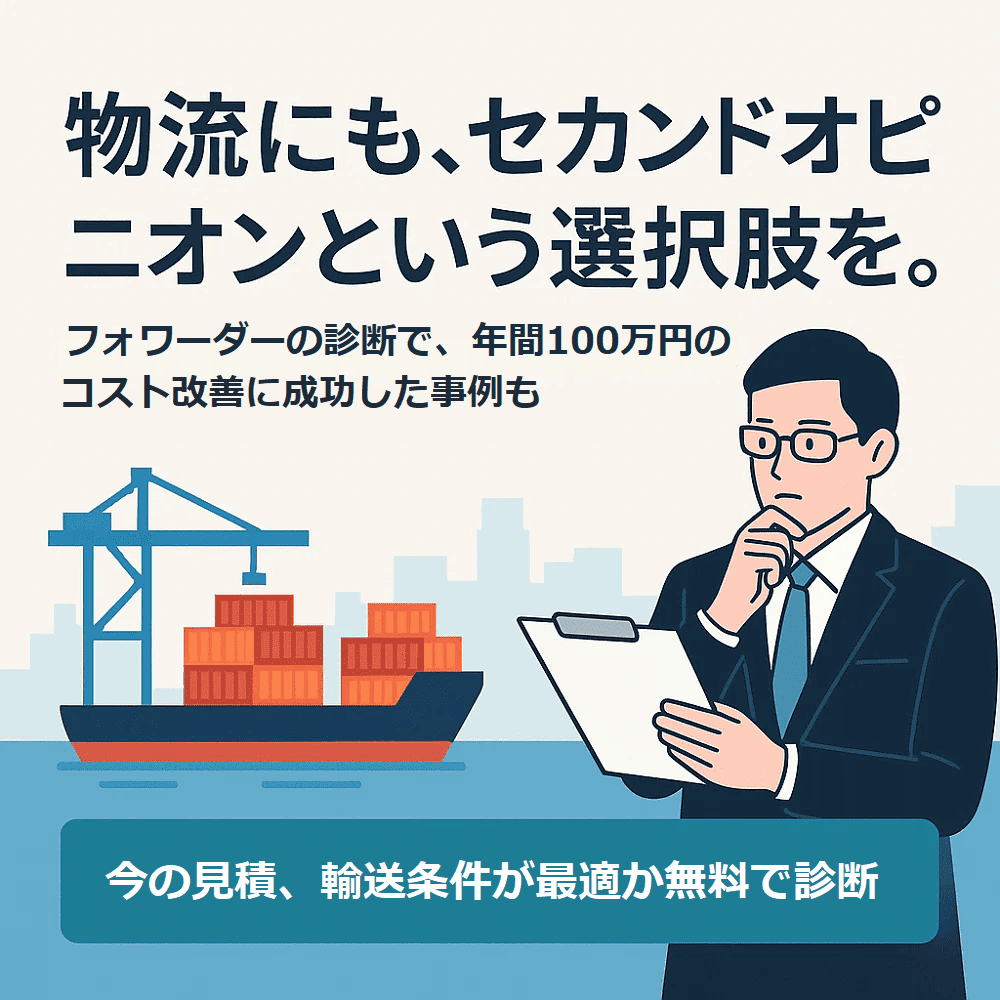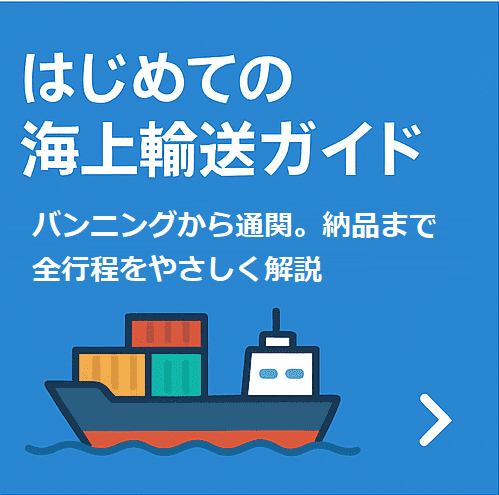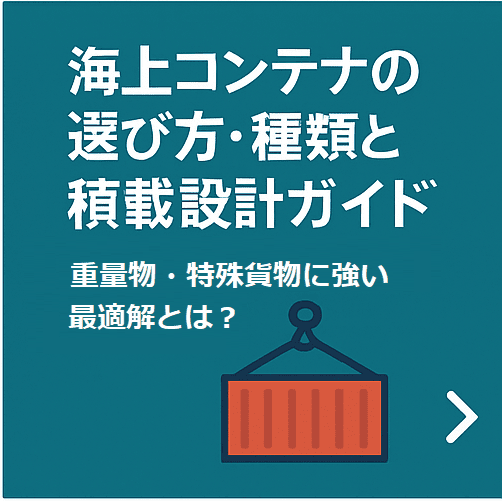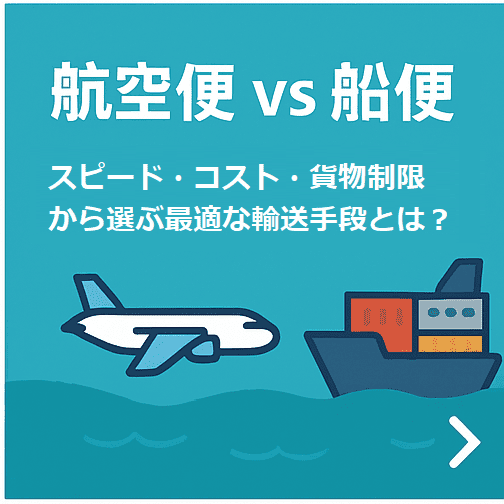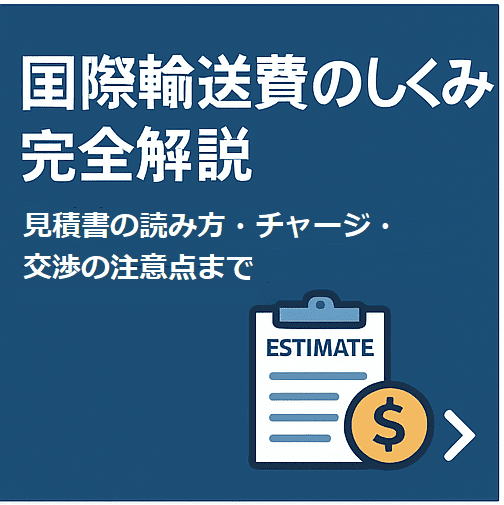「CTRL」+「D」を押すと、HUNADEをブックマークできます!
中国から日本へ移転する新たな流れと背景
中国から日本へ移転する動きが増えている理由
ここ数年、中国の製造業が日本へ拠点を移す動きがあります。2025年現在、中国法人が日本の廃工場を買い漁る動きがあるとの情報も聞きます。
背景には、対中制裁関税(Section 301)の継続に加え、地政学的な緊張、物流コストの上昇、パンデミックによる供給途絶リスクなどです。
こうした外部要因を前提に、企業が選び始めている現実解が「日本を核に据えた中間加工・再輸出」という設計です。
米国市場を重視する企業は、製品を直接中国から輸出する場合の高関税リスクを避けるため、日本を経由した中間加工・再輸出モデルを選択しています。これは単なる税制対策ではなく、BCP(事業継続計画)を中心とした生産の再構築です。
BCPの要件を満たすには、停止しにくい制度基盤と透明な執行環境が不可欠です。日本が注目される理由はまさにこの点にあります。日本の高い通関信頼性、制度の安定性、知的財産保護体制が「安全で透明な供給拠点」として注目され、アジア全体のハブ機能を強めています。
同時に、環境規制や脱炭素対応の観点からも、日本での製造・仕上げを通じてグローバルサプライチェーン全体のESG評価を高める戦略も広がっています。環境要件まで含めて総合最適を図ると、拠点戦略はコスト一辺倒から「日本+1」へと舵が切られます。
こうした複数の理由が重なり、「中国+1」から「日本+1」への流れは加速しています。
Substantial Transformation(実質的変更)の判断基準と事例
では、この戦略を実装に落とすうえで最初の関門となるのが、米国での原産国判定、すなわち Substantial Transformation です。
米国税関(CBP)は、輸入品の原産国を判定する際、Substantial Transformation(実質的変更)という厳密な原則を適用します。これは、単なる組立や外観変更ではなく、製品が機能・用途・性能の面で「新しい製品」に変化したかを問うものです。形式的な加工や再梱包では原産国変更とみなされない点に注意が必要です。
このSubstantial Transformationは、特に米国で設定されている関税を回避するため、優遇されている国の製品として輸出するときに関係するものです。(例:中国の会社が日本の工場で生産し、日本製品としてアメリカ向けに輸出など)
| 判断要素 | 該当しやすい条件 | 注意すべき非該当例 |
|---|---|---|
| HS分類変化 | 第4桁以上の変更(例:8536→8537) | 同章内での変更は非認定の可能性あり |
| 付加価値比率 | 加工費が総価値の10〜20%以上 | 組立や検査のみでは認定困難 |
| 機能・用途変化 | 製品の性質や用途が根本的に変化 | 外装変更・塗装・包装では非該当 |
抽象論に留めず、CBPの判断傾向を把握するために代表的な事例を確認します。
代表的な米国CBP判断事例(HQ Rulings)
- HQ例:電子基板を制御装置に組み立てた場合、機能変化を伴うとして実質的変更を認定
- HQ例:塗装・再包装のみでは原産国変更を否定
- HQ例:医療器具の部材組立ではなく性能試験工程の追加で変更を認定
これらの事例から、単純なTariff Shift(HSコード変化)に加え、付加価値創出と機能転換を同時に伴う加工が実質的変更の要件であることが分かります。日本側の生産工程を設計する際は、これらの判断を参考にすることで、米国CBPでの認定リスクを軽減できます。
「Made in Japan」表示と日米要件の違い
原産国の決定と表示は隣接するが別領域です。運用上の誤解を避けるため、日米の要件差を整理します。
「Made in Japan」表記は、国際的にブランド力を持ちますが、その使用には日米双方の異なる法制度の理解が必要です。誤った表示は輸出禁止・罰金・信用失墜のリスクを伴います。
| 国・地域 | 原産地判断基準 | 表示要件 | 注意点 |
| 日本 | 品目ごとの個別法です。例:不当表示防止法/JIS法に基づく「最終実質的加工地」 | 「日本製」と表記可 | 軽微加工は除外対象 |
| 米国 | FTC「All or Virtually All」基準 | CBPの原産国決定+19 CFR Part 134(マーキング規則) | 材料・工程比率の定量評価が必要 |
米国で「Made in Japan」と表示する可否は、CBPの原産国決定(非特恵=Substantial Transformation等)に基づき、19 CFR Part 134の規則どおりに“Japan”とマーキングすることで満たします。FTCの「All or virtually all」基準は“Made in USA”(米国原産主張)に適用される基準であり、外国原産表示には直接適用されません。
いずれの要件も、最終的には裏づけ資料の整合で担保されます。したがって記録設計は表示・通関双方の土台です。
原産地証明・書類整備の実務フォーマット
信頼性の高い原産地証明を維持するためには、製造段階から出荷後まで一貫した証跡管理が不可欠です。以下のような文書を統一フォーマットで整備することが推奨されます。
| 書類名 | 内容 | 提出タイミング | 保管期間 |
| BOM(部品構成表) | 部品・材料の原産国、数量、仕入日を記録 | 製造計画前 | 5年 |
| 加工記録 | 工程・作業者・設備・ロット番号 | 各製造日 | 5年 |
| 材料証明書 | サプライヤー発行。COA(分析証明書)添付推奨 | 調達時 | 5年 |
| 検査報告書 | 品質試験結果、写真・動画証跡 | 出荷時 | 5年 |
| 原産地証明書(Form A、Manufacturer’s Affidavit) | 通関提出用正式書類 | 通関時・監査時 | 永久保存推奨 |
これらをクラウド管理(ERP/WMS統合)することで、CBP監査対応時間を大幅に短縮でき、原産地証明の信頼性も向上します。さらに、AI OCRによる自動抽出や電子署名の導入で法的証拠力を強化できます。
証憑の実効性を保証するのは契約です。監査要請に即応できる義務設計を、取引基本契約へ織り込みます。
契約・監査体制の実装:法的リスク回避の鍵
日本と中国の企業間契約では、製造責任・証明義務・再監査対応の明記が極めて重要です。以下の条項を標準契約書に組み込むことが推奨されます。
- 原産地責任条項: 工程・生産拠点・責任者を特定
- 証明・再検証義務条項: CBPや税関の要請に応じ、原産地資料を即時提出
- 偽装防止条項: Transshipment(第三国経由偽装)や外注再委託を禁止
- 情報保持条項: 全製造関連データを5年以上保存する義務を明記
- 法令改正時再協議条項: 規制変更時に契約更新を行う旨を追加
こうした契約整備は、コンプライアンスのみならず、BCP観点からもリスク分散の基盤になります。特に日米間では監査頻度が増加しており、「監査を恐れない契約設計」が企業信頼性を左右します。
仕組みとしての契約を機能させるには、現場フローがセットで必要です。通知受領から提出・是正までを標準手順に落とし込みます。
原産地監査対応のプロセスと運用
CBPによる監査通知を受けた場合、迅速な対応が求められます。以下のフローをマニュアル化することで、混乱を最小限に抑えられます。
- 通知受領と初期分析: Form 28/29を確認し、調査対象品とHSコードを特定
- 証拠提出準備: BOM・工程記録・サプライヤー証明を整理。30日以内に提出
- 社内レビュー: 関連部署(製造・物流・法務)で事実確認を実施
- 追加照会対応: CBPの質問に対し、翻訳資料と写真証拠を添付して返答
- 再発防止策報告: 工程変更・データ整備の改善点を提出
- 監査記録の長期保存: 全資料を電子保存し、5年間追跡可能に
特に、監査プロセスの事前訓練(模擬査察)を実施することで、担当者の即応性を高められます。近年ではAI文書管理システムを活用した「e-Verification対応」が広がりつつあります。
ここまでの要件整備は守りの設計ですが、日本側にとっては攻めの機会にも直結します。具体的には次の領域です。
日本企業に広がる実務チャンスと戦略的対応
中国企業の日本生産移転は、日本企業にとってOEM・共同製造・品質保証・通関支援のビジネス拡大チャンスです。特に、通関・EPA証明・監査代行を専門とする中小企業が新たな価値を発揮できる局面です。
具体的なアクション例
- 原産地証明やCBP対応の専門人材を社内育成
- 生産工程をBCPと連動させた「二重ライン構築」
- 契約・証明・監査支援を含むワンストップ体制を整備
日本企業がこれらの対応を進めることで、単なる受託先ではなく「信頼性の高い国際製造パートナー」として地位を確立できます。これは将来的に、日米間の安定的なサプライチェーンを形成する基盤にもなります。
個別施策を束ねる視点に立ち返ると、「日本+1」は法令順守・BCP・データ証跡を核にした再輸出モデルだと言えます。
まとめと今後の展望
「中国+1」から「日本+1」への移行は、地政学リスク管理・法令順守・BCP体制強化を統合した国際生産モデルです。
Substantial Transformationや「Made in Japan」基準の理解を深めることは、取引継続と信頼維持の前提条件です。日本企業と中国企業が正しい原産地戦略を設計し、データ証跡と法令対応を一体化させることで、合法的で持続可能な再輸出モデルを構築できます。
シリーズ:BCP×関税×リロケーション
国際分業を「関税設計」と「BCP(事業継続性)」で最適化する実務ガイド。全体像 → 制度 → 体制 → 事例 → 対米実務の順で読めます。
- 第1回:リロケーション・スキームの全体像
- 第2回:再輸出免税と保税加工の違い
- 第3回:製造と通関を一体化するBCP戦略
- 第4回:中国+1から日本+1へ
- 第5回:中国企業の日本生産シフトと対米輸出
- 第6回:サプライチェーン強靭化補助金の実務対応
- 第7回:サプライチェーン停止に備える貿易BCP完全ガイド
- 第8回:港・空港・保税地域の被災リスクマップ2025

 この記事を登録
この記事を登録
 目次
目次