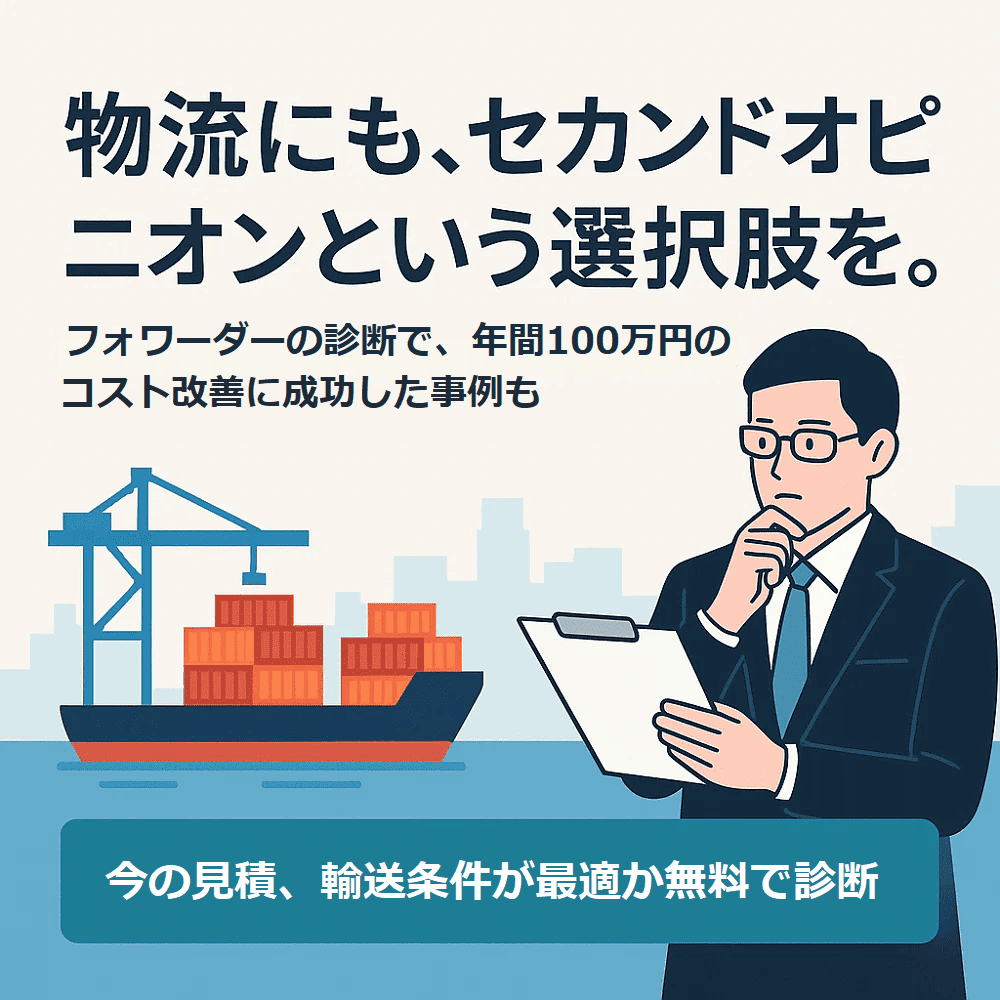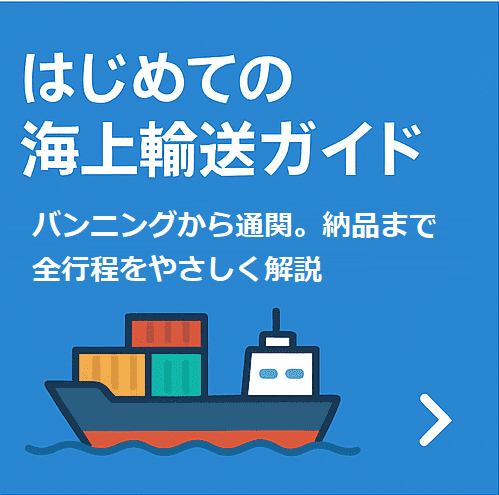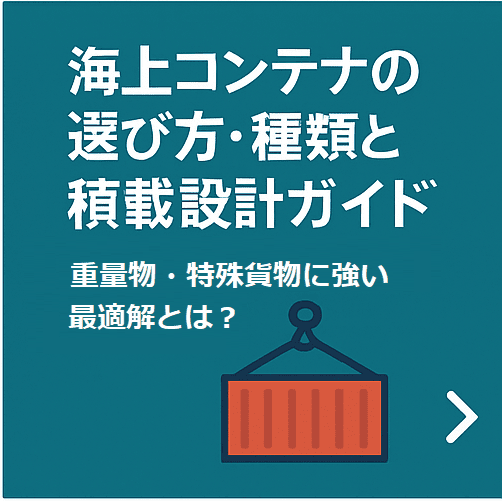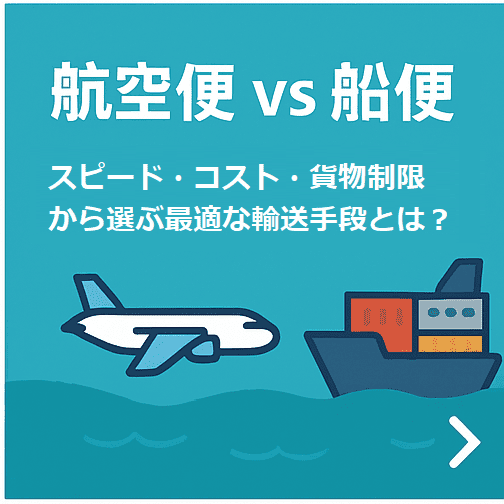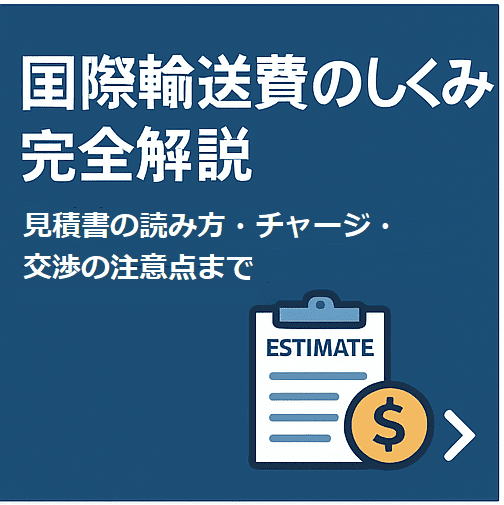「CTRL」+「D」を押すと、HUNADEをブックマークできます!
港・空港・保税地域の被災リスクマップ2025
被災時の「物流機能不全」はどこから起きる?
南海トラフ・首都直下地震の想定被害では、港湾・空港・保税倉庫の広域停止が現実的な脅威とされています。特に東京湾・大阪湾沿岸の埋立地は液状化や津波被害のリスクが高く、港や滑走路が機能停止すれば国際物流全体が麻痺します。
この記事では、被災可能性の高い拠点と実務的な代替ルートを検討してみます。
主要港湾の被災リスク
| 港湾名 | 想定被害 | 主な影響 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 東京港 | 液状化・護岸崩壊 | コンテナ搬出不能 | 物流の中枢機能停止 |
| 横浜港 | 津波・液状化 | ふ頭閉鎖・道路寸断 | 高潮・津波リスクも高い |
| 名古屋港 | 埋立地液状化 | コンテナクレーン傾倒 | 飛島ふ頭が高リスク(耐震化後でも一部リスク残存) |
| 神戸港 | 津波・岸壁損傷 | 積替え遅延 | 港島・六甲アイランドに集中リスク |
| 博多港 | 港湾道路冠水 | 保税倉庫浸水 | 九州北部物流の遅延 |
主要空港の被災リスク
| 空港名 | 想定被害 | 実務影響 | 備考 |
| 成田空港 | 液状化・滑走路沈下 | 航空貨物運航停止 | 内陸代替拠点なし |
| 羽田空港 | 津波・冠水 | 輸入航空便全停止 | 東京湾沿岸部の最前線 |
| 中部国際空港(セントレア) | 液状化・アクセス橋断絶 | 空港孤立 | 陸送不能リスク |
| 関西空港 | 台風・高潮・橋損壊 | 航空貨物孤立 | 2018年同様の再現リスク |
保税地域(倉庫エリア)の被災リスク
保税倉庫の多くは港湾近接地に位置するため、港湾機能停止と同時に被災が想定されます。特に以下の地域は液状化・津波被害の想定域に該当します。
| 地域 | 主な倉庫エリア | リスク | 備考 |
| 東京湾岸 | 潮見・有明・青海 | 液状化・浸水 | 輸出入貨物集中地帯 |
| 名古屋港 | 飛島・鍋田ふ頭 | 地盤沈下・液状化 | 自動車関連貨物多数 |
| 神戸港 | 六甲アイランド・ポートアイランド | 津波・液状化 | 関西圏保税機能集中 |
| 博多湾 | 東浜・多の津 | 高潮・津波 | 九州北部物流中心 |
大規模災害別の被害想定と具体策
ここからは、災害別の被害想定と具体策を検討していきましょう!
首都直下型地震|国際・国内物流の被害想定と具体策
東京湾沿岸(東京港・横浜港・羽田)で液状化・護岸損傷・滑走路沈下が想定されます。首都圏ハブの停止により、港湾オペレーション・通関・ドレー・混載が一斉に遅延します。
国際物流の被害
- コンテナガントリー/岸壁損傷で船社の入出港制限、滞船・デマレージ増
- 羽田/成田の滑走路沈下・潮位上昇による欠航・貨物搭載カット
- 湾岸CFS・保税蔵置の浸水で貨物引渡し不能(書類・在庫システム被害)
- 首都高湾岸線や東名の橋梁損傷による陸送断絶
48時間以内に発動する対策
- 代替港:新潟/仙台塩釜/清水/苫小牧を優先候補に事前契約
- 代替空港:新千歳/茨城/静岡/富山/神戸/福岡をルート表に明記
- 保税運送:関税法第63条により、内陸CFS(古河・守谷・春日井等)へ移送(税関長への承認要)
- ドレー中継:被災境界でトラクター/シャーシ分離リレー
- モーダル:JR貨物の代替輸送認定を事前登録。
72時間〜7日での復旧計画
- CY再開順序の優先度表(医薬・食料・重要部材→一般貨物)。
- 混載迂回:関東→北関東・東北ハブへ中継(宇都宮・小山・郡山)。
- 通関・在庫システムをクラウド二重化
南海トラフ地震|国際・国内物流の被害想定と具体策
太平洋側の広域で巨大地震+津波。名古屋・大阪・神戸・和歌山の臨港道路が長期停止する想定です。
国内外物流の被害
- 飛島・鍋田・六甲アイランド等で液状化
- 岸壁損傷→大型船の寄港制限。
- 西日本のコンテナ取扱が長期減速→スケジュール崩壊、輸出入の滞留が慢性化。
- 東名/新名神/阪神圏の幹線遮断→東西幹線の断裂。関西・中京の製造集積が停止
- フェリー・ROROの港湾被害で内航振替の余地が一時的に縮小
- 名古屋港停止→自動車部品輸出入停止→完成車ライン停止→下請へ資金ショック
48時間以内に発動する対策
- 代替港:日本海側(敦賀・金沢・境港)、九州側(博多・北九州・志布志)を事前リザーブ
- 代替空港:岡山・広島・北九州・福岡・新千歳などを代替候補に指定
- 保税運送(関税法第63条)を活用し、臨港倉庫から内陸(美濃加茂・草津・神戸内陸・岡山)へ移送
- JR貨物のBCP輸送・内航RORO(阪九・名門大洋・オーシャン東九)と連携協定
72時間〜14日での復旧計画
- 日本海側中心の臨時ネットワーク(舞鶴・敦賀↔首都圏)を運用
- 混載を中四国・九州のLTLハブに移管
- 部品調達:海外直送を新潟・富山着地に切替
契約・運用の具体化
- 船社との寄港地変更条項(Force Majeure時のCY変更、Free Time延長)。
- 在庫の二地域分散(太平洋側/日本海側)と発注点の二重化。
- 主要サプライヤーの「東西ミラー工場」化(同一工程の二拠点実装)。
富士山などの山の噴火|降灰時の物流被害と具体策
降灰が首都圏〜東海に広域沈着。道路・鉄道・空港の機能が低下し、視界不良・機械故障・滑走路使用停止が多発。
国内外物流の被害
- 羽田/成田/静岡などで滑走路閉鎖→航空貨物の欠航・遅延
- 港湾は運用可でも、臨港道路の走行制限・除灰遅れでCY↔倉庫間が麻痺
- トラック走行不能(降灰5〜10cmで停止想定)→ドレー・混載が止まり、内陸搬送ができない
- フォークリフト・ベルトコンベアの故障増→荷役効率が急落。
48時間以内に発動する対策
- 除灰動員:港湾・空港・倉庫・幹線の優先除灰計画(動線と機材・人員の割付)。
- 代替空港:新千歳・富山・神戸・福岡・北九州へ臨時経由。トランジットで主幹線を維持
- 代替港:首都圏貨物は清水・新潟・仙台塩釜・鹿島へ分散。内陸CFS直行の保税転送を即時実施。
- 車両対策:エアクリーナ・オイル・タイヤ・ワイパー等の消耗品在庫を倍積み。洗浄場を臨時設置。
72時間〜7日での復旧計画
- LTLの再開順:医療・食品・ライフライン→生産部材→一般貨物。
- 倉庫屋根・排水の点検と仮復旧、庫内は粉塵対策のPPEを標準化。
- 配送は夜間・早朝に時間分散し、混雑・視界不良時の事故を回避。
契約・運用の具体化
- 空港・港湾の代替スロット確保(降灰期間の臨時スケジュール)
- レンタル重機・清掃業者のBCP協力契約(除灰SLA:着手/完了時刻)
- 粉塵下での荷役安全SOP(マスク・フィルタ・清掃周期・車両点検項目)
代替拠点リスト(例示)
港(太平洋側停止想定)
- 日本海側:新潟/敦賀/舞鶴/金沢/境港
- 北日本:仙台塩釜/八戸/苫小牧
- 西日本:博多/北九州(新門司)/志布志
空港
- 東日本代替:新千歳/仙台/茨城/新潟/富山
- 西日本代替:神戸/岡山/広島/福岡/北九州
内陸CFS・倉庫(例)
- 関東:古河/守谷/桶川
- 中京:春日井/小牧
- 関西:草津/京都南 ・九州:鳥栖
内航RORO・フェリー(例)
- 阪九(新門司—泉大津/神戸)
- 名門大洋(新門司—大阪南港)
- オーシャン東九(有明—徳島—新門司—東京)

災害の直接被害よりも、「通関・輸送・情報」が分断されることが最大の損失です。
内陸輸送ネットワーク(ドレー・チャーター・混載便)の停止リスクと代替策
災害により想定される停止シナリオは以下の通りです。
1.コンテナドレー輸送の機能不全
港湾〜CFS・倉庫間を結ぶドレージは、ドライバーと車両基地が被災エリア内にあるケースが多いです。
例:東京港・名古屋港周辺(潮見・港区・飛島・港南)は液状化や道路沈下の想定域。車両不足や道路寸断により、搬出・搬入の遅延が1〜2週間単位で発生するリスクがあります。
2.チャータートラック網の分断
幹線道路(東名・新名神・湾岸線・首都高湾岸線)の橋梁損壊・通行規制で広域配送が停止。特に東京〜名古屋・名古屋〜大阪間は、全国物流の要であり、その被害は甚大です。
3.混載便(LTL)拠点の閉鎖
大手運送会社のハブ(関東・中部・関西)の多くが沿岸・低地帯に集中。例:川崎・一宮・枚方などは液状化・浸水リスクが高く、拠点停止時に配送網全体が麻痺します。
| 被害発生地点 | 影響 | 連鎖結果 |
| 港湾エリアの道路沈下 | コンテナ搬出不可能 | 船会社のデマレージ発生 |
| 幹線道路崩落 | チャーター便停止 | 在庫滞留・納期遅延 |
| 混載ハブ閉鎖 | LTL配送網麻痺 | 食品・小口貨物が大幅遅延・滞留 |

港や空港が使えても、「陸送ラインの断裂」で物流全体が止まるケースが最も多いです。
実務的なバックアップ施策
これらの災害に対するバックアップ策は以下の通りです。
ドレー代替策
- 被災想定外エリア(例:茨城・岡山・北九州)のドレー業者とBCP協力契約を締結
- 保税運送(関税法第63条)を活用し内陸CFSへ直接搬送
- 「ドレー中継方式」(被災地境界での車両リレー)を標準化
チャータートラック網の多層化
- 荷主・3PLが複数路線契約を持つ形に再構築する。
- 東名・新名神に加え、「中央道・北陸道経由」のBCPルートを年1回検証
- 東西拠点を持つ物流会社(例:日通・センコー)と相互融通協定を締結する
混載便ネットワークの再設計
- 大手運送会社(佐川・ヤマト・福山など)は災害時に”代替拠点移行計画”を策定済み
- 自社契約時に、被災時の迂回拠点リストを契約書に明示することが重要
- 地方拠点型混載業者(九州・北陸・東北)との連携ハブ契約も有効
鉄道・内航船へのモーダルバックアップ
- JR貨物の「JR貨物の災害時の迂回・代替輸送スキーム(事前協議・計画登録)」を事前登録しておくことで、トラック代替を即時発動可能
- 内航Roro船(阪九フェリー、名門大洋、オーシャン東九など)を定期代替ラインとしてBCP計画に組み込む
| 優先順位 | 対応内容 | 担当部署 |
| 第1層 | 港湾/空港との連絡ルート確保 | ロジ部門 |
| 第2層 | ドレー代替協定先との連携 | 通関・倉庫管理部 |
| 第3層 | 混載ハブ拠点再開情報の取得 | 営業・情報システム部 |
| 第4層 | BCPトラック配車計画発動 | 配送・輸送管理 |
実務者向けポイント
コロナ期の”輸送停滞”は港よりもトラックでした。トラックBCPの核心は「契約と地理の分散」です。被災地外の協力ネットワークを平時から繋いでおく企業が最終的に動けます。
ハザードマップ・情報ソース一覧
まとめ
南海トラフ・首都直下地震では、単に「港湾・空港の被災」だけでなく、ドレー・混載・チャーター網という陸送ラインの停止が物流断絶の最大の要因です。
BCPの実効性を高めるには、港湾・空港・倉庫・陸送ネットワークの四層分散を具体的な契約・演習で裏付けることが不可欠です。
シリーズ:BCP×関税×リロケーション
国際分業を「関税設計」と「BCP(事業継続性)」で最適化する実務ガイド。全体像 → 制度 → 体制 → 事例 → 対米実務の順で読めます。
- 第1回:リロケーション・スキームの全体像
- 第2回:再輸出免税と保税加工の違い
- 第3回:製造と通関を一体化するBCP戦略
- 第4回:中国+1から日本+1へ
- 第5回:中国企業の日本生産シフトと対米輸出
- 第6回:サプライチェーン強靭化補助金の実務対応
- 第7回:サプライチェーン停止に備える貿易BCP完全ガイド
- 第8回:港・空港・保税地域の被災リスクマップ2025

 この記事を登録
この記事を登録
 目次
目次