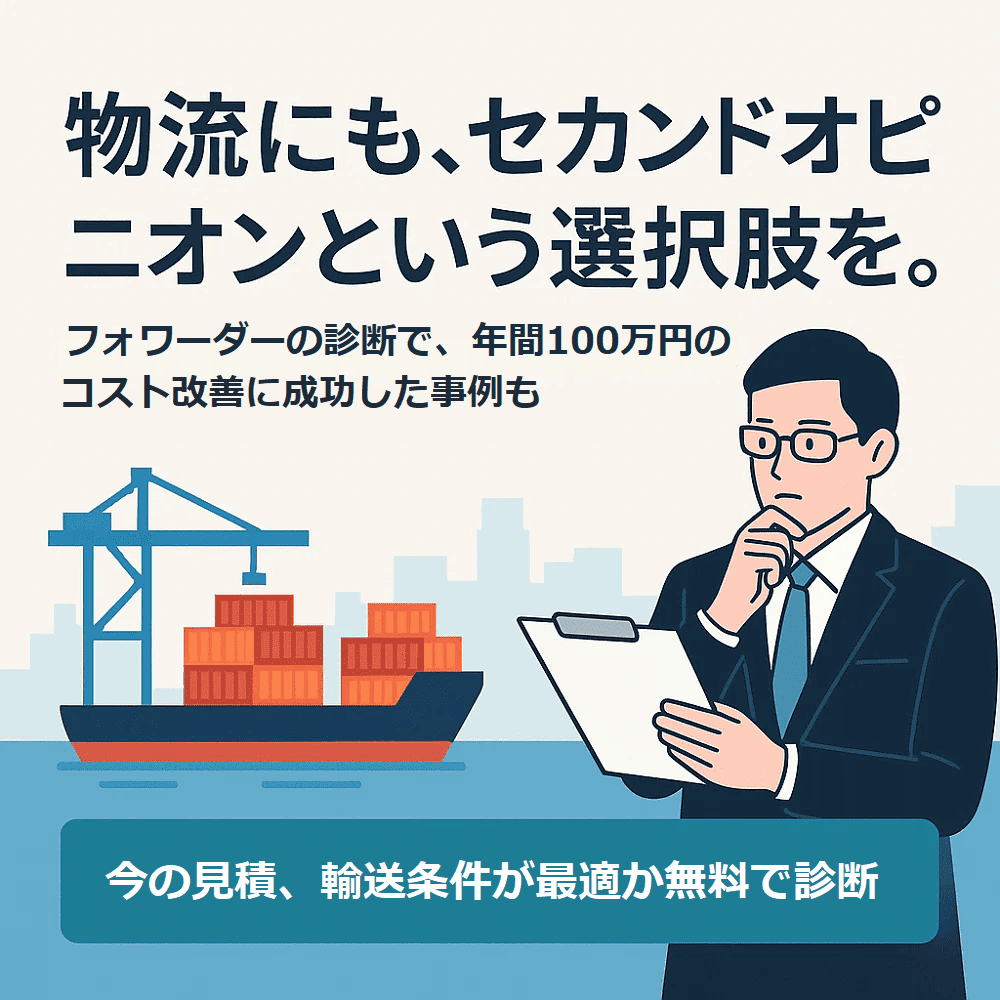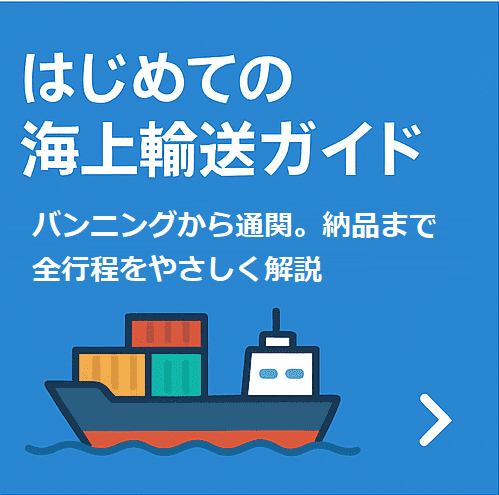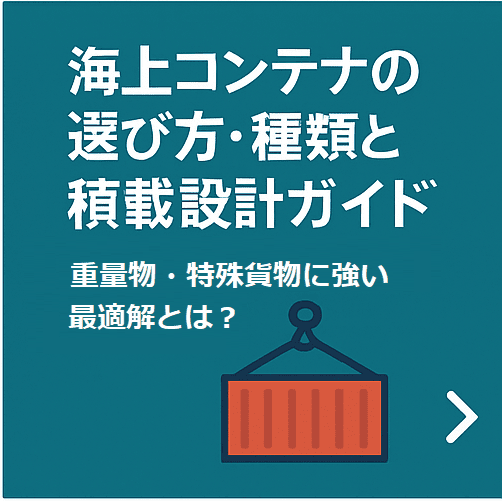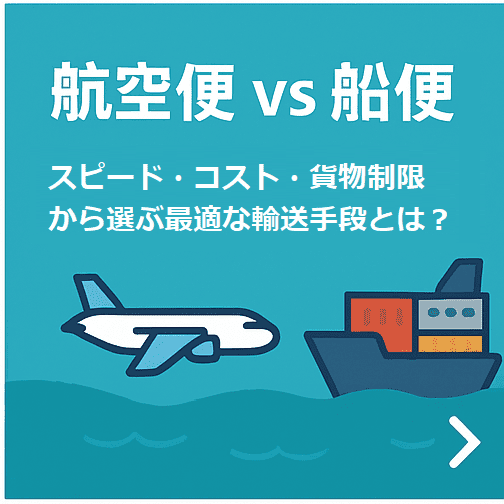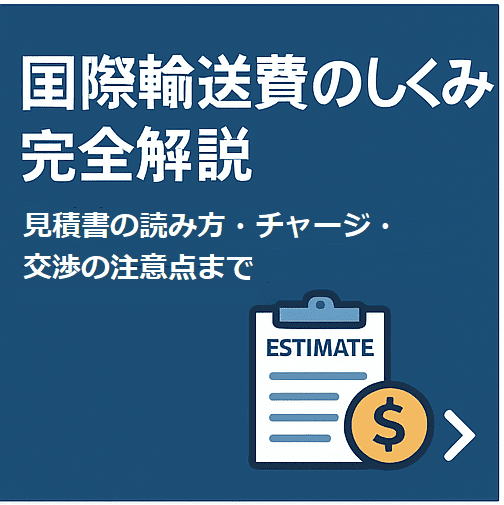「CTRL」+「D」を押すと、HUNADEをブックマークできます!
中国+1から日本+1へ|型分類(国内中核/分散モジュール/原料循環)×コスト/リスク比較×ASEAN協業モデル
世界的再編の流れと「日本+1」への進化
中国の人件費上昇、米中摩擦、制裁関税、物流のボトルネックなどにより、企業の供給網は歴史的な転換期を迎えています。
かつて主流だった「中国+1」戦略は、ASEANや南アジアへの分散を目的とするものでしたが、近年では”日本を再び中核に据えた”「日本+1」モデルが浮上しています。これは、品質・信頼性・リスク回避・環境対応を総合的に満たす現実的な解決策として注目されています。特にRCEP発効以降、ASEANとの原産地累積が容易になったことも追い風です。
本記事では、経営判断に直結する設計視点だけに絞り、次の観点を順に整理します。制度の詳細や対米実務は別稿に分け、意思決定の材料に特化します。
- 導入パターン分類
- コスト/リスク比較表
- ASEAN協業モデル
- リスクマトリクス
比較表:中国+1と日本+1の構造差(最新版)
| 項目 | 中国+1モデル | 日本+1モデル |
|---|---|---|
| 中核拠点 | 中国 | 日本 |
| 補完地域 | ASEAN・南アジア | ASEAN・南アジア |
| 主目的 | コスト削減・リスク分散 | 継続性・品質・安全保障 |
| 生産構造 | 海外主軸+一部多元化 | 国内主軸+海外補完 |
| 政府支援 | 外資誘致・ASEAN中心 | 国内回帰・サプライチェーン強靭化枠 |
| 適用制度例 | FTA特恵・加工貿易 | 再輸出免税・RCEP累積・EPA連携 |
この対比は単なる生産地の選択ではなく、重視する価値基準そのものが異なることを示します。以下、その含意をもう一歩具体化します。
「日本+1」モデルの三つの導入パターンと発展形態
では、その思想の違いが現場設計にどう現れるのか。代表的な導入パターンを三つに整理します。
1.国内中核型
主要工程を日本に残し、ASEANを一次加工拠点として活用。食品・精密機器など品質要求が高い業種で採用。ISO認証の統一や、国内最終包装体制との接続が要点です。
2.分散モジュール型
ASEANで部品を加工し、日本で組立と最終検査。機械・電子分野で主流。一部企業は年次のサプライチェーンの切替訓練(スイッチテスト等)を実施している所もあります。
3.原料循環型
原料を日本から輸出→ASEANで一次加工→再輸入し仕上げ→再輸出。化学・素材・金属などで多いパターン。RCEP累積制度を活用し、原産地証明の継続性を確保します。
これら基本パターンを土台に、近年はデータ連携を核にした発展形も台頭しています。象徴的なのが「デジタル双方向型(Digital BCP Model)」です。
参考情報:発展形
発展形として、デジタル双方向型(Digital BCP Model)が登場しています。これは日本とASEAN双方の生産情報をクラウド上でリアルタイム共有する仕組みで、トラブル時に生産切替を自動化する動きが広がっています。
コストとリスクの比較モデル(経営判断指標)
設計の良し悪しは、最終的にコストとリスクのバランスで判断されます。次に、意思決定で重視される評価軸を比較します。
| 評価項目 | 中国集中型 | 日本+1モデル |
| 想定総コスト(短期) | 低 | 中〜高 |
| 想定停止リスク | 高 | 低 |
| サプライリードタイム | 長 | 短 |
| 品質・保証コスト | 中 | 低(安定) |
| 復旧速度(BCP発動時) | 遅 | 速 |
| 為替変動リスク | 高 | 中(円建比率増) |
| 政治・制裁リスク | 高 | 低 |
この比較表を基に、企業は「短期コスト重視型」から「長期安定収益型」への転換を検討する時期に来ています。BCPの視点を取り入れた場合、トータルコストでは日本+1が優位になるケースも多く見られます。
ASEAN連携の具体モデルとBCP耐性
この評価軸を前提に、日本+1を支える実務面の要となるのがASEAN側の連携設計です。代表例を三つに整理します。ASEAN側の連携モデルには以下の3パターンが見られます。
1.技術移転型
日本側が監修・品質保証を担い、現地は労働集約・一次加工を担当。現地認証との整合性を取ることで輸出時の非関税障壁を削減します。
2.OEM/合弁型(JV型)
資本・技術・人材を折半し、BCP時に柔軟な操業切替が可能。マレーシアやタイではこの形が増加中です。
3.委託製造+データ連携型
ERP・WMSを共通仕様で運用。日本本社がリアルタイムで生産進捗・在庫・輸出データを監視。地震・洪水時でも業務継続性を確保します。
近年は、クラウド連携を中心とした「ハイブリッドBCPネットワーク」化が進んでおり、単なる拠点分散ではなく”データ主導の分散管理”が鍵となります。
地政学・災害リスク別マトリクスと地域対応
連携モデルは外部ショックにどれだけ耐えられるかで価値が決まります。主要リスクを地域別に見取り図で確認します。
| リスク種別 | 高影響地域 | 日本+ASEAN体制の主な対応策 |
| 制裁・関税(対米) | 中国 | 日本経由再輸出/原産地変更で回避 |
| パンデミック | ASEAN | 在庫分散・遠隔勤務・多拠点教育 |
| 自然災害 | 日本・東南アジア沿岸 | 代替拠点+クラウドBCP+港湾分散 |
| 政治不安 | 一部ASEAN | JV監査・契約統合・サプライ契約の再定義 |
| 環境規制 | 中国・ベトナム | 脱炭素化拠点の日本集約で対応 |
このマトリクスは、地域別のリスク要因を分かりやすく示すツールとしても活用できます。特に「日本+ASEAN連携」の強みは、自然災害・地政学両面におけるリスク補完能力にあります。
こうした設計を後押しするため、制度面の下支えも整いつつあります。活用しうる政策・協定の枠組みを概観します。
制度・政策との連動(補助金・国際協定)
政府施策としては、経済産業省の「サプライチェーン強靭化補助金」「国内投資促進税制」などが企業の再投資を後押ししています。
JETROは「ASEAN連携支援プログラム」を通じ、RCEP・EPA制度の活用を促進。これにより、「ASEANで加工→日本で仕上げ→再輸出」の流れが制度的に裏付けられています。

一例:地方自治体では、長崎県・愛知県・静岡県などが「地域BCP連携支援」を開始。中小製造業でも、BCP策定支援金を通じて情報一元化とサプライ回復計画が進められています。
成功企業の共通構造と実務課題
制度の後押しを前提に、現場で成果を上げている企業には共通構造があります。要点を抽出します。
成功企業は、制度理解(FTA/EPA)×BCP設計×データ統合を三位一体で運用しています。通関・製造・原産地情報をクラウドで連携し、トラブル発生時も別拠点で即時再稼働ができます
一方で、運用定着を阻むボトルネックも明確です。最も顕著なのが人材と教育の持続性です。特にEPA証明・原産地判定を理解する通関担当者の確保が中小企業では難しく、デジタルツール活用による補完が求められています。
これらの課題を踏まえ、実装段階で優先すべき打ち手を四点に絞ります。
今後の展望と実務提言
「日本+1」戦略は単なる国内回帰ではなく、データ連携と制度運用を融合させた”知的BCP”モデルへと進化しています。
実務者が注力すべきは次の4点です。
- 拠点ごとのSPOFを特定し、システムの冗長化を優先する
- RCEP累積・再輸出免税・EPAなどの制度をBCP運用に組み込む
- クラウド連携を用いて遠隔監査・品質検証を可能にする
- 人材継承・教育計画をBCPの一部として定期更新する
これらを実装することで、企業はコスト・品質・リスクの三要素を総合的に最適化し、国際環境の変動にも耐える”止まらない供給体制”を築けます。
以上を踏まえると、日本+1は回帰ではなく“設計の再定義”です。最後に全体像を再確認します。
まとめと今後の展望
「中国+1」から「日本+1」への転換は、単なるトレンドではなくリスク対応型経営へのシフトです。地政学、災害、物流停滞などの不確実性が高まる中、BCPを中核としたサプライチェーン再設計が企業存続の鍵を握ります。
今後は、関税・EPA・BCPを連携させた「統合型再輸出スキーム」が主流になります。
Hunadeでは、こうした制度と実務を結びつけた「再輸出スキーム設計支援」やBCP策定支援を通じ、企業のリロケーション実務をサポートしています。いまこそ、自社の供給構造を見直し、変化に強い生産体制を築く時です。
シリーズ:BCP×関税×リロケーション
国際分業を「関税設計」と「BCP(事業継続性)」で最適化する実務ガイド。全体像 → 制度 → 体制 → 事例 → 対米実務の順で読めます。
- 第1回:リロケーション・スキームの全体像
- 第2回:再輸出免税と保税加工の違い
- 第3回:製造と通関を一体化するBCP戦略
- 第4回:中国+1から日本+1へ
- 第5回:中国企業の日本生産シフトと対米輸出
- 第6回:サプライチェーン強靭化補助金の実務対応
- 第7回:サプライチェーン停止に備える貿易BCP完全ガイド
- 第8回:港・空港・保税地域の被災リスクマップ2025

 この記事を登録
この記事を登録
 目次
目次