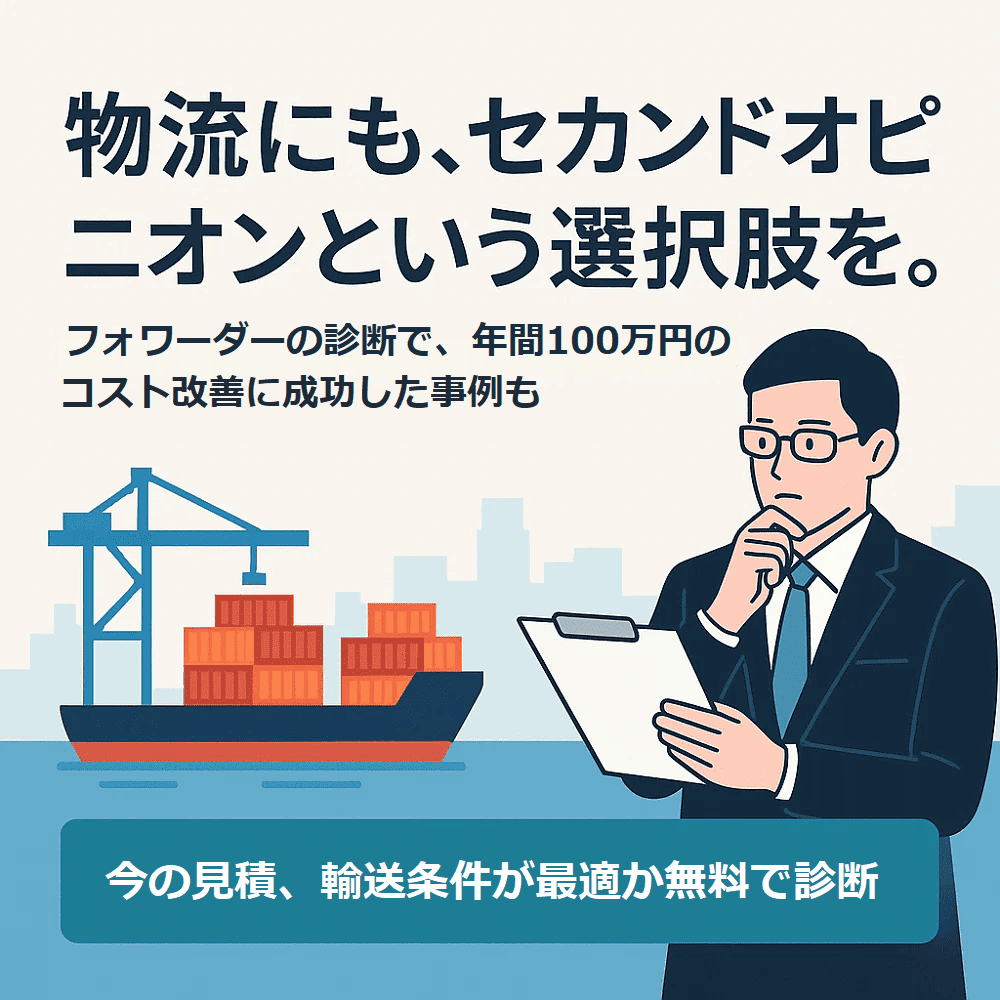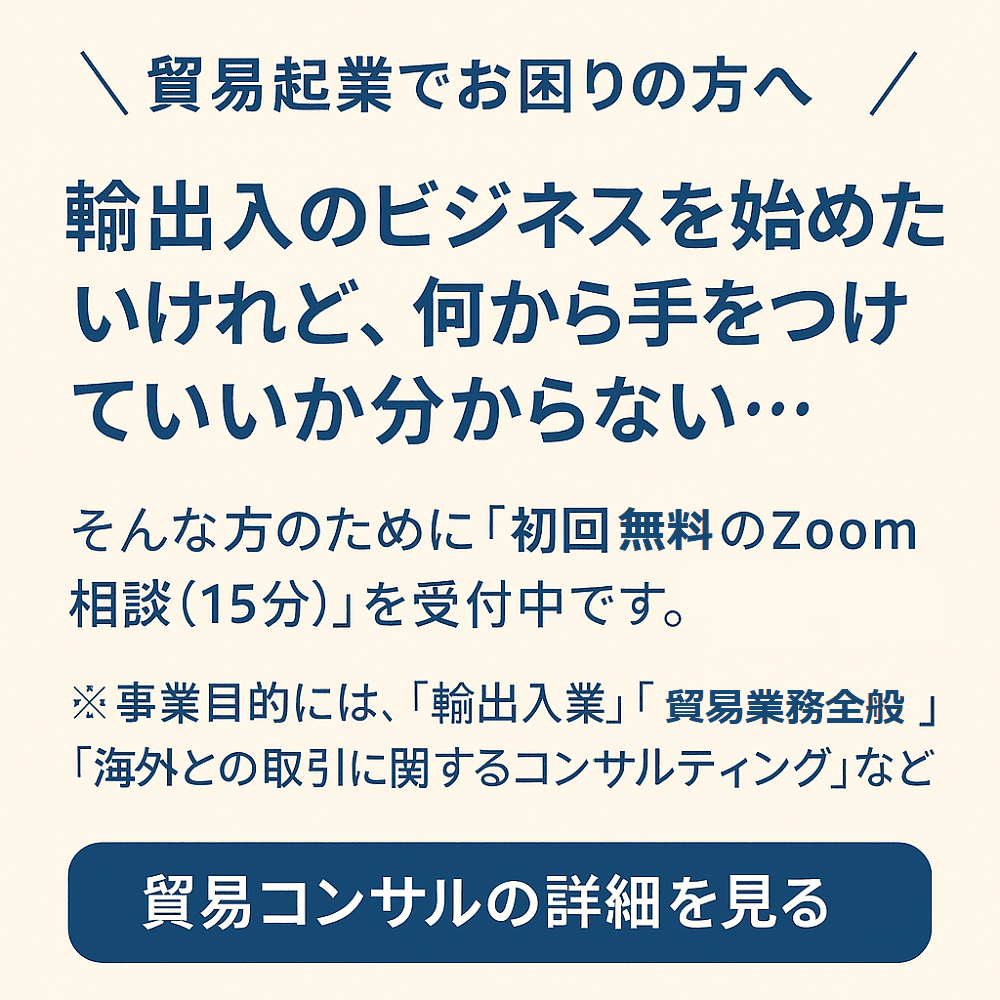港を変えればコストが変わる|北米インランド費を“設計”で削る最適化フレーム
値下げ交渉より効く、ネットワーク再設計という発想
多くの企業は「インランド費が高い」と感じると、フォワーダーや運送会社との値下げ交渉を思い浮かべます。しかし、実際に効くのは“ネットワークの設計”そのものを見直すことです。港、通関地、分配方式を最適化すれば、同じ海上運賃でも総コストは大きく変わります。
この記事は、第1回で示した「構造理解」を前提に、具体的な設計フレームを提示します。
なんとなく決まっている港・ルートの落とし穴
多くの輸出実務では、「昔からこの港だから」「通関は港でやるのが普通だから」といった慣習で設計が固定されています。その結果、海上費は安いのに、内陸輸送コストが跳ね上がるという“逆転現象”が起きています。
典型的なのが、西岸(ロサンゼルス/ロングビーチ)経由で中西部向けの長距離レール+都市圏トラックを組み合わせたケースです。港湾混雑や滞留(Demurrage & Detention)も発生しやすく、結果として総コストが膨らみます。
こうした「固定設計」がコスト上昇の温床となります。
では、インランド費を下げるためには何を再設計すべきでしょうか?
最適化の3レイヤーで考える
レイヤー1:港湾選定(West / Gulf / East)
港を選ぶ際の基準は、航路・内陸距離・混雑傾向・鉄道接続・季節要因の5軸で整理できます。
例えば…..
- 西岸(LA/LB・Prince Rupert):航路頻度が多く、アジア発着に強いが、鉄道距離が長く滞留リスクも高い。
- 湾岸(Houston):南部・中西部へのアクセスが良く、エネルギー関連貨物に強い。
- 東岸(Savannah・New York):通関率が高く、港湾混雑が比較的少ないが、航路が長くリードタイムが延びやすい。
レイヤー2:ルート選択(Rail / Intermodal / Truck)
IPI(Inland Point Intermodal)、Mini-IPI、Landsideなど、輸送方式の選択によって費用構造は変わります。鉄道が有利なのは1,000マイル超の長距離。逆に、近距離ではトラック輸送が柔軟かつ速い。貨物特性(重量・容積・温度管理)に応じて、どこでレールからトラックに切り替えるかを設計段階で決めておくことが重要です。
レイヤー3:通関地・分配設計(In-Bond / Cross Dock / Inland DC)
通関を港で行うか、内陸で行うか(In-Bond移送を利用するか)で、リードタイムとコストは大きく変わります。また、Cross Dock(港で分配)と内陸DC(集約後再配送)のどちらを採用するかも、在庫回転率と最終配送コストに影響します。とくに「Place of Delivery」の設定を誤ると、スルー運賃が発生し、想定外の内陸費を抱えるリスクがあります。
港別・都市別・方式別の比較で見える違い
理論を整理したところで、実際に港やルートを変えるとどの程度コストやリードタイムが変化するのか、数値で確認してみましょう。
| 港→都市 | 距離 | 輸送モード | リードタイム | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| LA/LB → Chicago | 約2,000マイル | Rail | 約6~7日 | 滞留リスクあり |
| Savannah → Atlanta | 約250マイル | Truck | 約1~2日 | 高頻度出荷向け |
| Houston → Dallas | 約240マイル | Truck | 約1~2日 | 南部集中型に適す |
| Prince Rupert → Midwest | 約2,500マイル | Rail | 約8日 | 距離長いが混雑少 |
シミュレーション例:港別TDC比較
TDC(Total Delivered Cost)の基本式は次の通りです。
TDC = 海上費 + 内陸費 + 附帯費(Fuel, Storage, D&Dなど)
| 経路 | 海上費 | 内陸費 | 附帯費 | TDC合計 | リードタイム |
| LA経由 | 1,200USD | 2,800USD | 200USD | 4,200USD | 約7日 |
| Savannah経由 | 1,400USD | 1,000USD | 150USD | 2,550USD | 約3日 |
→ わずか数百ドルの差でも、リードタイム短縮・滞留リスク低減につながります。設計次第でTDCは構造的に変わるのです。
また、設計を変えることで何が変わるかも比較しておきましょう。
| 設計変更 | 影響要素 | メリット | デメリット |
| 港湾通関 → 内陸通関 | 通関タイミング/保税移送費 | 港湾滞留減少 | 保税輸送手配が必要 |
| Cross Dock → 内陸DC | 在庫/配送頻度 | リードタイム安定 | 集約コスト増 |
季節・天候リスクも設計上の重要要素です。
例えば….
- ハリケーンシーズン(8〜10月)は湾岸ルートを避け、東岸や西岸ルートに代替港を設定
- 冬季ストーム(12〜2月)は北部港を避け、南部港を利用するなど
港別に代替ルートを2案持つ設計が望ましいです。
意思決定マップと5ステップ手順
単なる概念整理ではなく、設計変更を社内で実行に移すには、判断手順が不可欠です。
意思決定マップ(3軸)
仕向地 ─┬─ 港近郊
├─ 内陸・メガハブ
└─ 内陸・ロングテール
貨物特性 ─┬─ 重量物/容積勝ち
├─ 高頻度・定期
└─ 温度管理・不定期
納期要求 ─┬─ 定時性重視
├─ コスト最優先
└─ 短納期
この3軸で設計案を分類し、TDC・Lead Time・Reliabilityという共通KPIで評価します。
5ステップ実務手順
- 過去6か月の仕向先を地域クラスタに分類(中西部/南部/東海岸)
- 各クラスタに対し港候補を最低2つ設定(例:西岸+湾岸)
- 各候補でPort→Door概算ルート(Rail/Truck)を引き、リードタイムを算出
- 通関地(港/内陸)と分配方式(Cross Dock/内陸DC)を2案比較
- TDCとサービスレベルで2案に絞り、RFP作成へ
RFPには、IPI可否、鉄道キャリア、シャーシ課金、フリータイム、滞留時課金、内陸通関対応可否、Cross Dock地点、渋滞回避オプションなどを明記します。
ケーススタディ:LA経由とSavannah経由を比較する
同一貨物を中西部に納品する場合、
- 案A:LA/LB → Rail → 内陸通関 → 内陸DC
- 案B:Savannah → Truck/Short Rail → 港湾通関 → Cross Dock
案Aは海上費が安いもののリードタイムが長く、D&Dリスクも高いです。一方、案Bは海上費がやや高いが内陸距離が短く、リードタイムが安定。結果的にTDCではBが有利になるケースもあります。
設計ミスの典型と回避策
- 港固定の思考で長距離IPIを強制し、D&Dを招く。
- Place of Deliveryを不用意に設定し、スルー運賃が発生。
- Cross Dockの選定を誤り、労務コストや予約制限で遅延。
- 季節・天候リスクを無視し、柔軟な港替えができない設計。
これらを避けるためには、少なくとも年1回、港・通関地・分配方式を見直す“設計リビュー”を実施することが望まれます。
まとめ:“設計で勝つ”とは、候補を増やしTDCで判断すること
このような比較とステップを踏むことで、設計を定量的に評価できるようになります。港・ルート・通関地はセットで再設計すべき要素です。候補を持つこと自体が交渉力となり、フォワーダーに対しても優位に立てます。最終判断は「TDC(Port→Door総額)」と「サービスレベル」で行いましょう。
第3回では、こうして設計した構造を契約・運用・データでどう管理するかを解説します。

 この記事を登録
この記事を登録
おすすめのサービス
基幹記事
貿易学習コースの一覧
分野別記事
◆スポンサード広告


 目次
目次