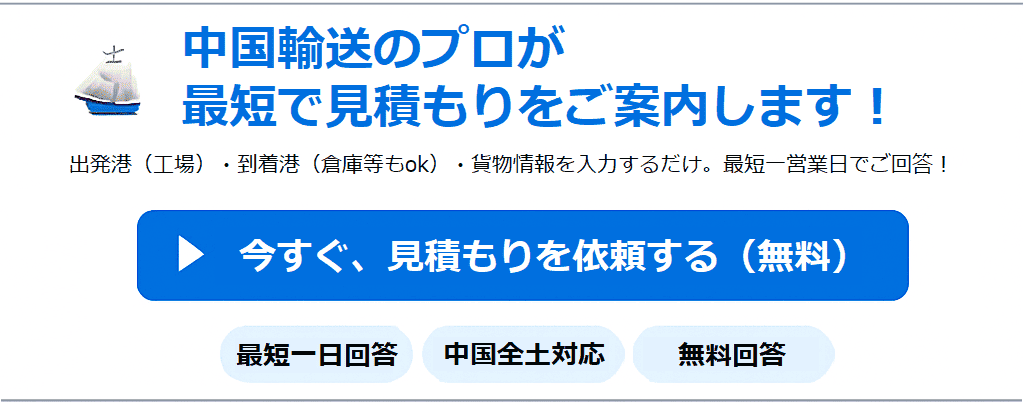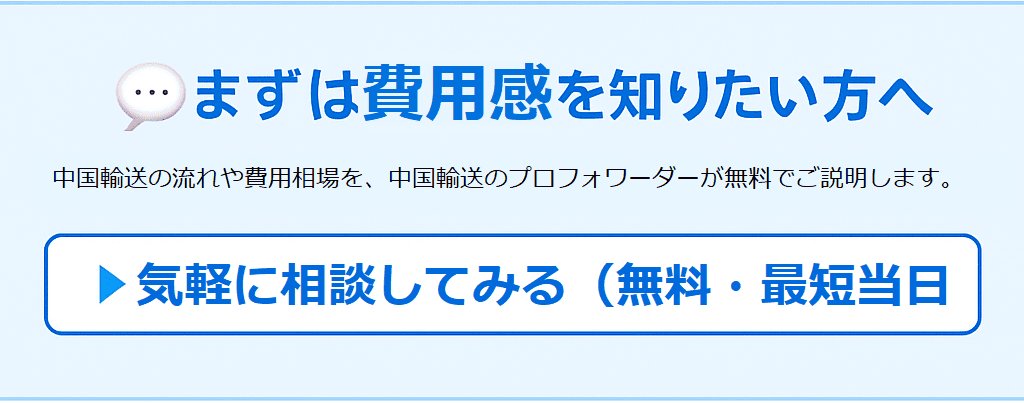中国輸送コストを“構造”で最適化する方法

見積書の中身を「戦略設計」に変えましょう!
この記事群(この記事含めて8つ)は、中国から日本に輸送する事業者の方を対象とした「輸送費コストの最適化」をテーマにしたものです。読者の対象は、現在、FCL、LCL、航空輸送、あるいは、フェリー輸送をしている方で、一定、規模の物量をとり使っている方です。
なぜ“費用構造”から考える必要がある?
中国輸送では「海上運賃を安くしたい」という言葉がよく聞かれます。しかし、それだけを見て判断すると大きな落とし穴があります。
総コストは、運賃だけで決まりません。
- THC(ターミナルハンドリングチャージ:港での荷役・保管・設備使用料)
- CIC(China Import Charge:中国側で発生する書類費・港湾費・輸出通関費など)、D/O費用、国内配送費、通関手数料
などが複雑に絡み合います。一部を削減しても別の工程で上乗せされる「構造的な転嫁メカニズム」があるため、単純な運賃比較では真のコスト削減にはつながりません!
つまり、フォワーダー見積を「安い・高い」で比較しても、実際の利益には直結しません。
そこで本記事では、輸送コストを構造単位で細かく分解し、その動かし方を解説します。

物流は点ではなく『線』で見ることが重要です。
単一視点の交渉が“トータル赤字”を生む
具体的な例で問題点を見ていきましょう。
中国から日本への輸送では、「部分的な削減」がむしろ全体コストを上げることがあります。
例えば…..
- 海上運賃の値下げ交渉に成功 → 結果的にCICやTHCが増える。
- 現地集荷を安く抑えた → トラック不足で出港逃し → 倉庫保管費が発生する。
- コンテナ単価で比較 → LCL輸送の単価を割高にするなど
ある企業では上海港からの混載便を安く抑えた結果、荷受け遅延により港で滞留費が発生し、結果的に総コストが8%増となったケースもあります。
このような事例からも、見積の“部分最適化”は全体赤字の原因になりかねません。
輸送コストを“構造”で見直す4つの設計ステップ
1.コストを「固定費」「変動費」「リスク費」に分類する
まず全体像の整理が必要です。
- 固定費:港湾費・通関費・書類費など、案件ごとに変動しない部分
- 変動費:海上運賃・燃油サーチャージ・国内輸送費など、相場で変動する部分
- リスク費:遅延・倉庫滞留・チャーター手配など、突発対応で発生する部分
多くの企業は「変動費」にしか目を向けていません。しかし、見積書をこの3層で色分けすれば、「どこを動かすべきか/動かせないか」が明確になります。
この学習コースを読まれましたか?
2.原価構造を可視化する(FOB→CIF→DDPの流れ)
中国輸入では、契約条件(インコタームズ)によって費用の発生箇所が異なります。代表的な流れを簡略化すると以下の通りです。
【現地引取】→【海上輸送】→【輸入通関】→【国内配送】
例えば、CIF取引では海上運賃と保険料までが含まれますが、日本到着後のTHC・通関・配送は輸入者負担です。
同じCIFでも、港湾費が高い港を選ぶとトータルで割高になります。
このように、見積の「どの段階で費用が生じるか」を把握することで、不透明だったコストの流れを自社管理に引き戻すことができます。
3.為替・燃油・港湾費の変動を“変動要因表”で管理する
このようなコストの変動要因は、常に監視し対策が必要です。
| 要素 | 管理ポイント | 実務での影響 |
|---|---|---|
| 為替(USD/JPY) | ±5円変動でCIF価格が3〜5%変化 | 見積比較は常に同レート換算で行う |
| 燃油(BAF/LSS) | 相場変動+フォワーダーごとに設定差 | 月次で比較・更新を依頼 |
| 港湾費 | 博多・大阪・東京で最大8,000円差 | 地域別KPIとして可視化 |
3か月単位で追跡すれば、フォワーダー見積の「値下げトリック(他項目転嫁)」にも気づきやすくなります。
4.フェリー・LCL・航空を“総合単価”で再評価する
「どの輸送モードが安いか」は、単純な運賃比較では判断できません。
- LCL運賃が安く見えても、デバン費・配送費を含めるとFCLより高くなるケース
- フェリー便は通関連動性が高く、総額で最も安定するケース
- 航空便も、バッチ運用(複数ロットまとめ輸送)により、フェリーと競合可能
例えば、月2回のフェリー+月1回の航空緊急輸送を組み合わせると、在庫圧縮とリードタイム短縮を両立できる事例もあります。

このような「ハイブリッド輸送設計」により、総合単価を基準とした最適化ができます。
数値で見る“総コスト構造表”
以下の表は『海上輸送費』として認識している部分を項目ごとに数値化し、各項目がどれほどの影響があるのかを数字でとらえられるようにした物です。
例えば、いわゆる海上運賃と言っているものは、下記4項目の一つでしかないのです。実際は、1~4の合計が輸送費と考えることが重要です。「木を見て森を見ず」まさにこの言葉がぴったりと当てはまります。
| 項目 | FCL | LCL | フェリー | 航空 |
| 海上運賃 | 100 | 70 | 80 | 300 |
| 港湾費・書類費 | 40 | 55 | 40 | 30 |
| 通関・D/O | 25 | 30 | 25 | 20 |
| 国内配送 | 35 | 60 | 40 | 25 |
| 総計 | 200 | 215 | 185 | 375 |
※単位は仮定値。目的は「構造比較を理解する」こと。

実際、ある日用品メーカーではLCLからフェリー輸送へ切り替えることで、輸送費を年間12%削減し、納期変動も半減した例があります。
実務で使える“コスト最適化チェックリスト”
- 見積書を固定費/変動費/リスク費の3層構造で整理している?
- 港湾別のTHC・CIC差を把握・更新している?
- 為替・燃油・港湾費の変動率を3か月単位で管理している?
- LCL・フェリーの総額シミュレーションを定期的に行っている?
- フォワーダー比較を「運賃」ではなく「総合構造」で評価している?
このチェックリストを自社のSOPや稟議資料に組み込むと、“価格交渉ベース”から“構造設計ベース”へと議論の質が変わります。
💡インサイト(戦略的視点)
- タイトル:削減ではなく“設計”でコストを下げる
- 一手:年2回の港湾費レビュー+燃油相場を見越した契約更新サイクル
- 効果:年間10〜15%の実質コスト減(安定輸送を維持したまま)
- 前提:為替・港湾費データを継続的に記録・比較する体制
- リスク:部門間で部分最適化が進むとスケジュールロスが発生
- 指標:港別・週別の総合CIFコストを社内KPIとして可視化
まとめ
- “削る”よりも“構造で見る”ことが、中国輸送コスト最適化の第一歩。
- 固定費・変動費・リスク費を分類して可視化する。
- 港湾費・燃油・為替の三要素を変動管理に組み込む。
- 輸送モードは単独比較せず、総合単価で評価する。
実際の数字と工程を見える化することで、「削減ではなく設計」という発想が社内に根づく。
中国輸送の基本コース
中国輸送の”高速化”コース

 この記事を登録
この記事を登録
おすすめのサービス
基幹記事
貿易学習コースの一覧
分野別記事
関連記事
◆スポンサード広告


 目次
目次