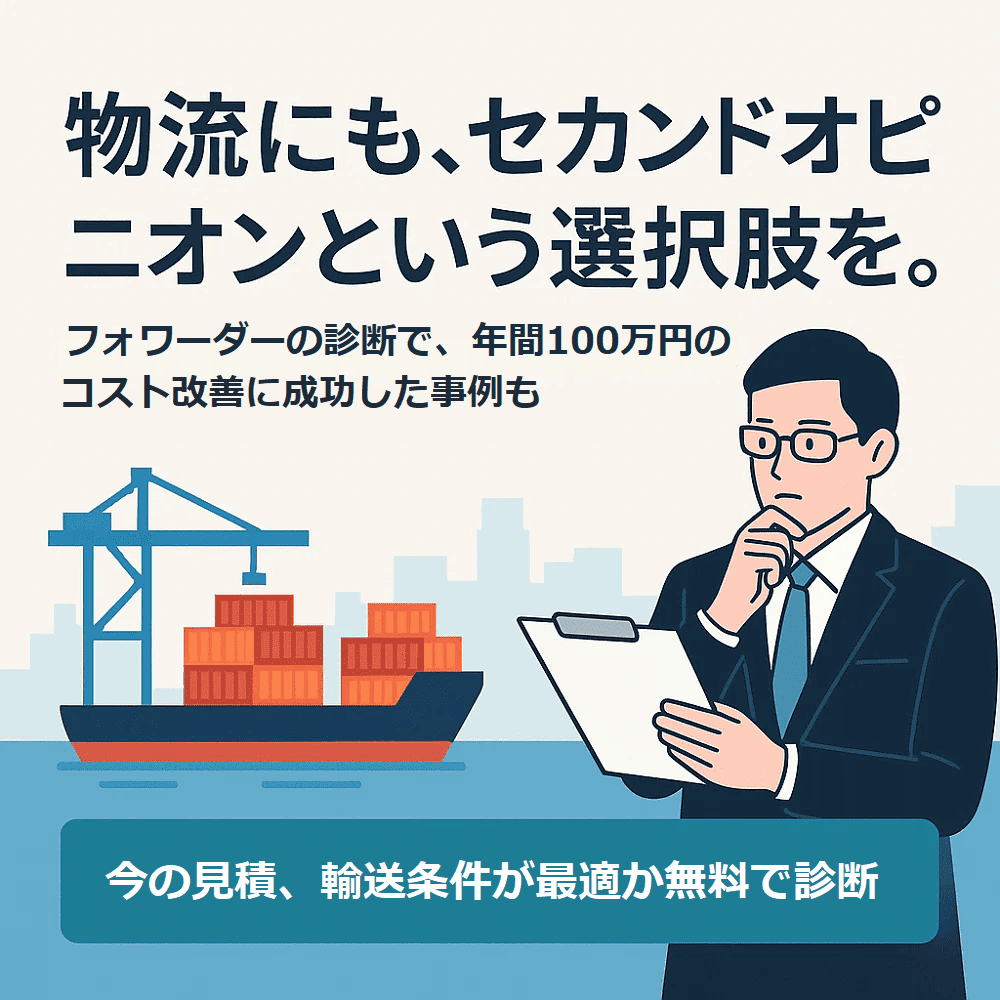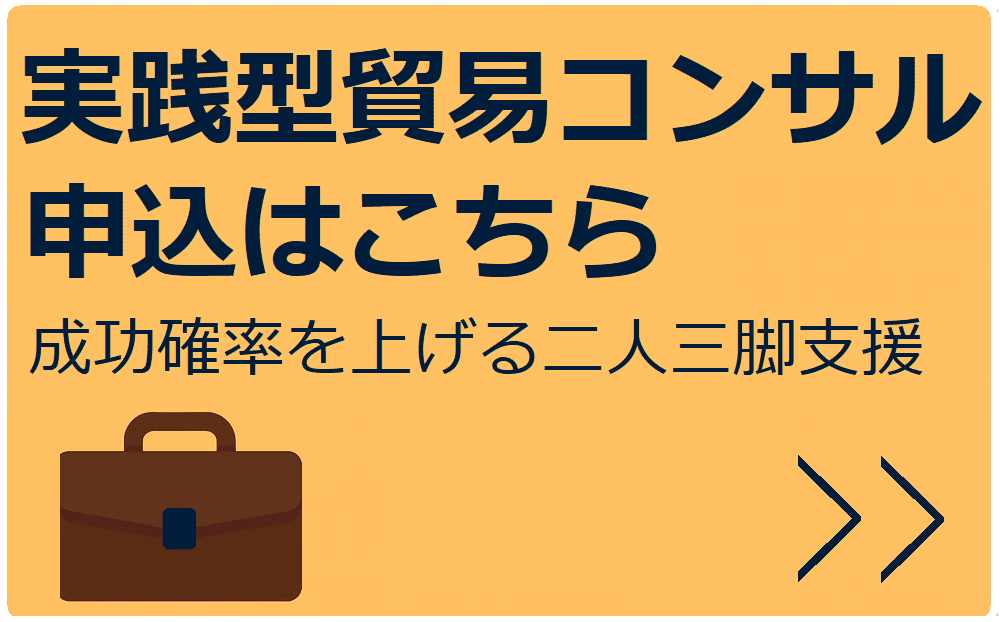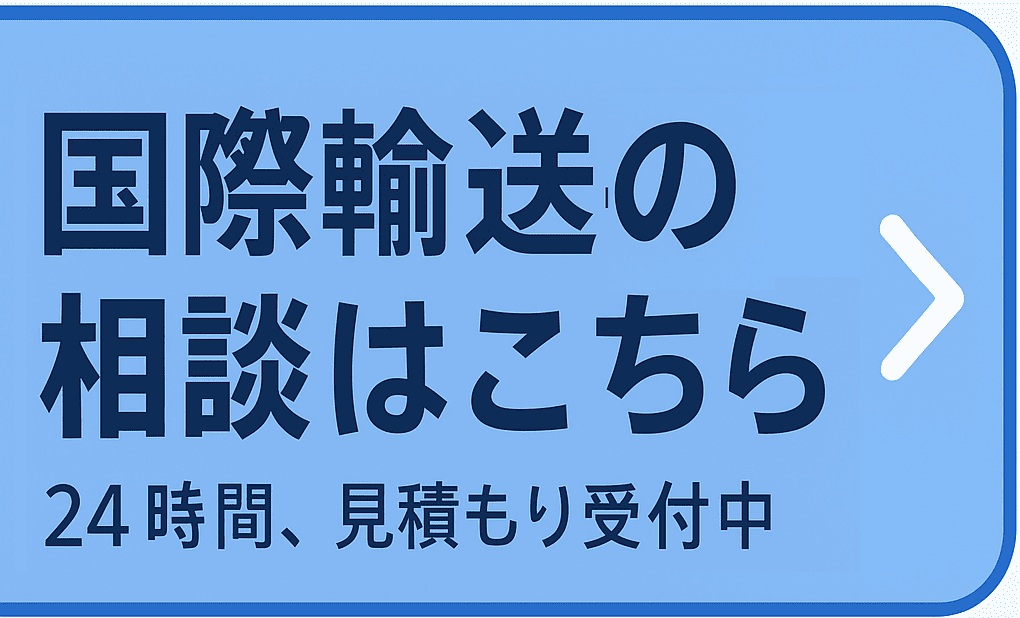再輸出免税とEPA累積の設計基準|関税定率法第17条/関税法第56条・保存要件・帳票連携の実務
この記事は、日本の関税法および各種経済連携協定(RCEP/CPTPP/日EU)に基づく再輸出免税と原産地累積制度の設計実務を整理します。米国CBPのSubstantial TransformationやMade in Japan表示義務については別稿で解説します。
再輸出免税の適用範囲と否認リスク(関税定率法第17条)
再輸出免税は、関税定率法第17条に基づく制度で、課税済みの輸入貨物を一定期間内に加工し、再輸出した場合に関税が還付される仕組みです。適用により大きなキャッシュフロー改善効果が得られますが、誤用や書類不備による否認リスクも高いため、法的条件を理解する必要があります。
主な否認リスクと理由
| 区分 | 内容 | 否認理由 |
|---|---|---|
| 軽微作業 | 検査、再梱包、マーキング、仕分けのみ | 実質的な加工と認められない |
| 部品交換 | 機能変更を伴わない軽微交換 | 加工価値が発生しない |
| 書類不備 | 加工記録欠如・輸出期限超過(原則1年以内) | 条件不充足として免税否認 |
| 原材料不一致 | 輸入原料と加工内容が不一致 | 原産性証明が困難 |
| 輸出証明欠如 | 船荷証券・輸出許可書の欠落 | 再輸出を立証できない |

適正運用のためには、加工価値比率や用途変化を証明する客観的記録の整備が不可欠です。
再輸出免税と保税加工(保税工場)の比較
再輸出免税の仕組みを正しく理解するためには、似た制度との違いを押さえることが重要です。特に「保税工場制度(関税法第56条)」は混同されやすいため、ここで両者を整理しておきましょう。
両者はいずれも輸入原料を加工して輸出する点で共通しますが、課税のタイミングや運用形態が異なります。
| 制度 | 法的根拠 | 主な特徴 | 適用場面 |
| 再輸出免税 | 関税定率法第17条 | 一旦輸入・課税後に加工して再輸出時に還付 | プロジェクト単位の加工・再輸出取引 |
| 保税工場制度 | 関税法第56条 | 輸入時点で課税を留保し、加工後再輸出時に免除 | 継続的な輸出加工を行う製造業 |
| 保税運送 | 関税法第63条等 | 保税地域間で貨物を運送 | 保税倉庫・工場間の連携輸送 |

制度の選択基準は、課税発生の有無と加工拠点の恒常性にあります。再輸出免税はプロジェクト単位、保税加工は量産型ビジネスに適しています。選択を誤ると、追徴課税や監査対応の遅れを招くおそれがあります。
これらの制度は輸入時点での課税を制御する仕組みでしたが、輸出側ではさらに「原産地ルール」の活用が重要です。次に、EPAにおける累積制度を見ていきましょう。
EPA累積(Cumulation)の種類と実務活用
EPA(経済連携協定)における「累積(Cumulation)」とは、複数国間で行われた生産・加工工程を合算し、原産資格を確保できる仕組みを指します。協定によって累積の範囲や方法が異なります。
| 累積方式 | 概要 | 採用協定 | 実務上の留意点 |
| 双方累積(Bilateral Cumulation) | 二国間での加工を合算可能 | 日EU EPAなど | 相互協定が前提。対象原料を限定 |
| 地域累積(Regional Cumulation) | 地域内複数国の加工を合算 | RCEP、ASEAN+日本など | 供給網設計段階でルール確認が必要 |
| 生産行為累積(Production Cumulation) | 原産資格を持たない工程も評価可能 | CPTPPなど | 工程記録の完全開示が求められる |
累積の理解を誤ると、原産地証明書の発給が拒否される場合があります。BOM(部品表)設計段階から「どの工程がどの国で行われたか」を明確化し、EPA判定システム(例:TradeWaltz、NACCS)との連携を整えることが重要です。
こうした制度を適用するには、申告の正確性を裏づける書類管理が欠かせません。税関や協定原産地当局による事後調査にも耐えられる体制を構築する必要があります。
書類保存要件と期間(関税法第94条の2〜第95条)
免税や特恵を適用するためには、長期間の帳簿・証憑保存が必要です。形式上の義務ではなく、監査・事後調査時に説明責任を果たすための根拠でもあります。
| 保存対象 | 保存期間 | 根拠 |
| 帳簿 | 7年間 | 関税法第95条 |
| 証憑書類(請求書・インボイス等) | 5年間 | 関税法施行令第87条等 |
| 原産地証明書 | 協定別に3〜5年 | RCEP第14章など |
| 電子データ | 真正性・可視性・検索性を確保 | 電子帳簿保存関連通達 |
クラウド型ERP(SAP、OBIC7など)と通関システムを連携させ、改ざん防止・証拠保全・監査即応性を同時に確保することが理想です。
しかし、単に書類を保管しているだけでは十分ではありません。税関は、輸入から輸出まで一連の整合性を重視するため、各帳票を連携させたトレーサビリティ設計が求められます。
トレーサビリティ連携の構築例
税関は単独の書類ではなく、輸入から輸出までの一貫した整合性を確認します。そのため、帳票・証憑の連携設計が欠かせません。
- 輸入申告番号 → 加工指図書 → 輸出申告番号(番号紐付け)
- BOM記録 ↔ HSコード分類(加工価値比率の整合)
- 原産地証明書 ↔ 輸出インボイス・B/L(照合可能性)
- サプライヤー宣誓書 ↔ 原材料ロット台帳(突合)
ERP内でハイパーリンク管理を導入し、税関調査時にワンクリックで証憑を提示できる体制が望まれます。これは情報レジリエンスの一部としてBCP評価にも繋がります。
ここまで見てきたように、個々の制度や書類管理を最適化するだけでは十分ではありません。これらを一体的に組み合わせ、企業全体のリスク耐性を高める視点が必要です。
実務提案|関税・EPA・BCPの三位一体設計
制度を個別に運用するのではなく、再輸出免税 × 原産地ルール × 継続運用体制(BCP)を統合的に設計することで、企業は次の効果を得られます。
- 税務最適化:課税→免税→FTA適用の三段階でコスト削減
- 工程安定化:製造・通関・システムの連携によるリスク最小化
- BCP強化:多拠点バックアップと電子保存で継続性確保
- コンプライアンス強化:説明責任を満たす内部統制体制
地政学リスクやサイバー攻撃の増加を背景に、「制度耐性を持つサプライチェーン設計」が企業競争力の分岐点となっています。
まとめ
再輸出免税は単なる税務制度ではなく、企業の経営安定性を支える重要な仕組みです。正確な法令理解と帳簿・証憑の一貫管理を行うことで、コスト削減とリスク回避を同時に実現できます。特にEPA累積を組み合わせることで、アジア全域の供給網最適化にもつながります。
参考リンク(公的情報源)
シリーズ:BCP×関税×リロケーション
国際分業を「関税設計」と「BCP(事業継続性)」で最適化する実務ガイド。全体像 → 制度 → 体制 → 事例 → 対米実務の順で読めます。
- 第1回:リロケーション・スキームの全体像
- 第2回:再輸出免税と保税加工の違い
- 第3回:製造と通関を一体化するBCP戦略
- 第4回:中国+1から日本+1へ
- 第5回:中国企業の日本生産シフトと対米輸出
- 第6回:サプライチェーン強靭化補助金の実務対応
- 第7回:サプライチェーン停止に備える貿易BCP完全ガイド
- 第8回:港・空港・保税地域の被災リスクマップ2025

 この記事を登録
この記事を登録関連記事
基幹記事
貿易学習コースの一覧
分野別記事
カテゴリの一覧
関連記事
◆スポンサード広告


 目次
目次