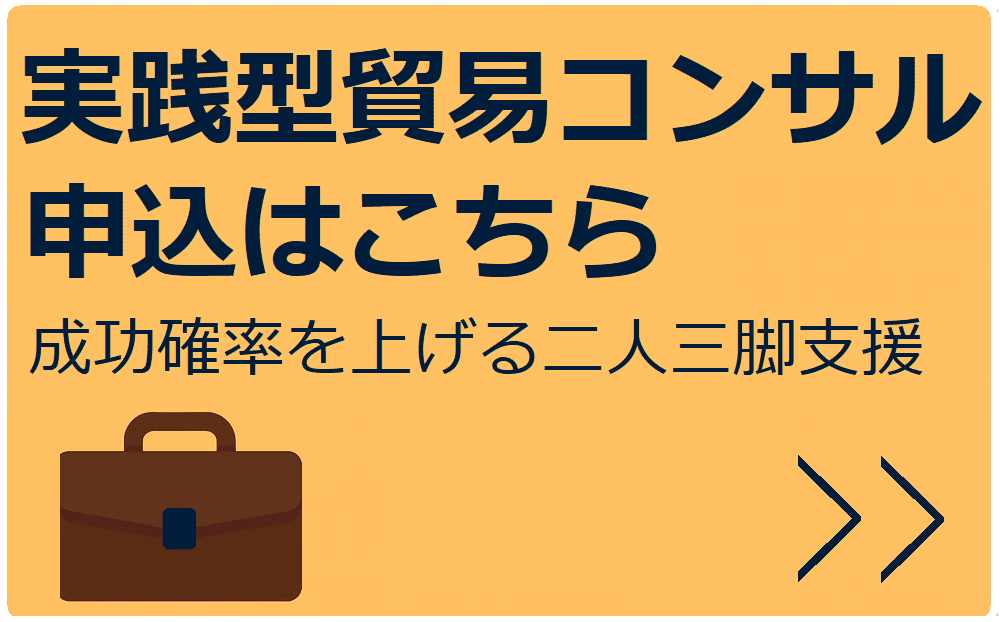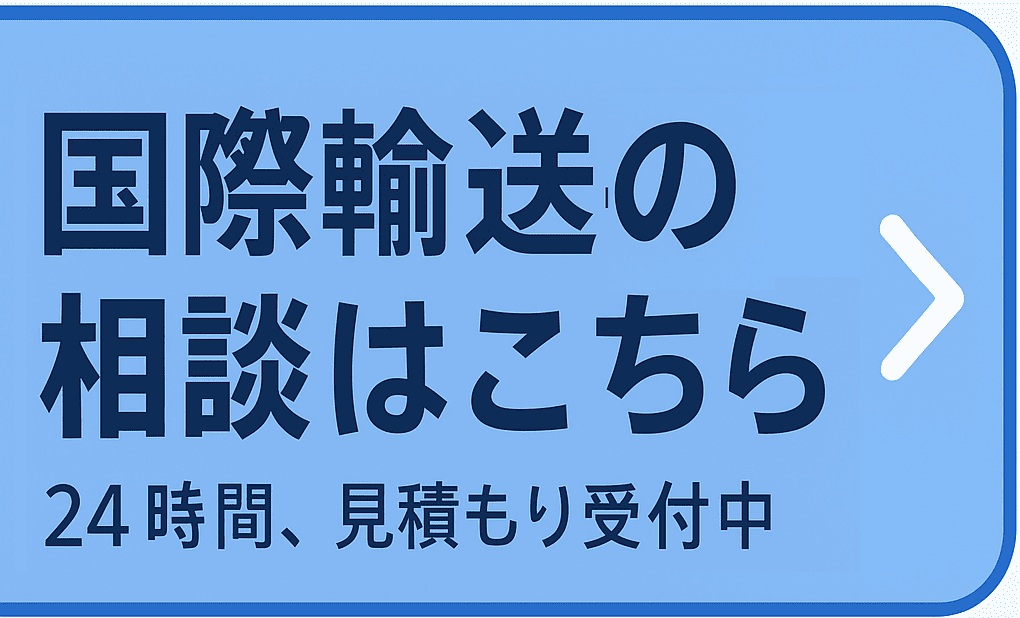柔軟性でつくる国際物流の新戦略
はじめに|なぜ今、“物流”を経営から見直すのか
世界情勢が不安定化し、米中摩擦や為替変動、人件費の上昇が続いています。さらに日本国内では「物流2024年問題」や人手不足が深刻化し、これまでの「効率化一辺倒」では対応しきれない時代に入りました。
高市政権の所信表明(2025年10月24日)では、「供給網の強化」「危機管理投資」が明確に掲げられています。政府レベルで“変化対応力”が重視される今、企業にも柔軟なサプライチェーン設計が求められています。
この記事では、関通×フレートマンロジックス社のセミナー資料を基に、「柔軟性」「見える化」「設計力」という3本柱で、国際物流を経営戦略の視点から再定義します。これらを単なる概念ではなく、実務に落とし込む方法を具体的に解説します。
こうした変化の時代において、物流を単なるコストではなく「経営の変化対応装置」として捉え直す視点が重要です。次章では、その基盤となる“柔軟性”と“コスト設計”の考え方を整理します。
経営を支える物流 ― 柔軟性とコスト最適化で築く競争力
物流は単なる輸送ではなく、調達から販売、資金までをつなぐ経営基盤です。これまでのように「効率」だけを追い求める仕組みでは、変化が起きた瞬間に脆くなります。
米中貿易摩擦や為替変動、海上運賃の乱高下が続く中、物流を「安定供給のための設計対象」として再構築する必要があります。効率を最優先するJIT(Just in Time)型モデルは限界を迎え、柔軟性を持った構造が求められています。
ここで言う柔軟性とは、「可変性」と「選択肢の事前設計」を指します。具体的には、輸送モードの切り替え判断を迅速化するための承認フローの短縮、複数の運送会社やルートを常に確保しておく仕組みです。欧州では港湾ストライキを回避するため、ロッテルダムとハンブルクを併用する複線物流設計が一般化しています。
耐変動制
柔軟な物流は、急な需要変動やルート寸断にも対応できる「耐変動性」を持ちます。これは単なるコスト削減ではなく、経営の保険です。柔軟な仕組みを実現するには、現行のコスト構造自体を見直すことが欠かせません。どんなに仕組みを工夫しても、費用配分が固定的では変化に対応できないためです。
こうした柔軟性を維持するためには、コストの中身を「固定費」から「可変費」に再設計する発想が必要です。費用をどう配分するかが、変化への対応速度を決めます。
効率から柔軟性へ ― コスト構造の再定義
世界のサプライチェーンの潮流は、効率最優先から「変化対応最優先」へと移行しています。為替や燃料費、通関制度、地政学的リスクなど、外部要因を吸収できる構造が必要です。
柔軟性を高める実務設計として、以下の要素があります。
- 輸送ルートを複線化する(海上・航空・陸上の併用)
- 在庫拠点を分散させる
- 契約条件に為替・燃料条項を組み込む
コスト構造の再定義
コスト構造の再定義とは、単にコストを削減することではなく、変動を前提に「設計する」ことです。
例えば、物流コスト比率は売上の8〜12%を目安に設定し、在庫回転率は年5〜8回を維持するなど、業界標準のKPIを管理するようにします。
危機管理投資
高市総理が述べた「危機管理投資」は、まさにこの“耐変動性”の考え方と一致します。国交省が推進する「物流DX推進ロードマップ(2024年度改訂)」とも軌を一にし、効率よりも変化吸収力を備える構造設計が求められています。政府主導の取り組みは、企業の現場設計を後押しするだけでなく、国際的なサプライチェーン再編の動きとも呼応しています。
このような考え方は、日本だけでなく世界的な潮流になっています。各国でも“変化吸収型の物流設計”が経営戦略の中核に位置づけられています。
世界でもリスク分散の動き
世界の海運・航空業界でも、リスク分散の動きが進んでいます。
例えば、米国では港湾混雑を避けるため東海岸・メキシコ湾港への迂回輸送を拡大、欧州でも内陸鉄道の代替ルート整備が進行中です。このように、世界の物流は「分散と設計」を軸に再構築されています。
では、日本企業はどのように自社の構造を強化すべきでしょうか。
柔軟性が利益を生む ― 経営改善につながる打ち手
外部環境は変えられません。変えられるのは「自社の構造」です。
成功する企業には、以下の3つの共通点があります。
- 設計力:経路・在庫・契約・情報を一体で設計している
- 見える化:データを意思決定に活用している
- 協働体制:経営と物流が分断されていない
この3要素の中でも、最も実務に直結するのが「見える化」です。現場のデータを可視化できなければ、設計力も協働体制も形だけに終わります。
特に「見える化」は、BI(Business Intelligence)ツールやEDI・TMS・WMSの連携によって実現します。これにより、輸送進捗、在庫残量、通関遅延などを即時に把握でき、現場から経営までの判断速度が向上します。
例えば、アパレルや雑貨、EC、機械部品などの業種で、これらを実現した企業は「部分最適」から「全体最適」へ移行し、物流コストと利益のバランスを安定化させています。
こうした現場の取り組みは、国の政策とも密接に関係しています。政府の方向性を理解しておくことは、今後の制度変化に備えるうえでも重要です。
経済安全保障の再定義
高市政権が掲げる「経済安全保障の再定義」も、単なる防衛ではなく供給網全体の再設計を意味します。企業もまた、通関遅延や輸送規制の変動、為替変動などに対応する“レジリエンス設計”を進めるべき時期に来ています。さらに、為替予約や貿易保険を併用することで、金融面からの危機管理投資もできます。
では、こうした考え方を自社の現場でどう実行に移すべきか。次に、現状を把握するための診断ポイントを整理します。
自社を見直す ― サプライチェーン診断の5つの視点
柔軟なサプライチェーンを構築するためには、まず現状を「見える化」することが必要です。以下の5項目は、その第一歩です。
- 輸送効率:ルート・モードの最適化(FCLとLCLの使い分け)
- ✓ 複数モード輸送の運用実績がありますか?
- 在庫回転率:欠品と過剰のバランス設計
- ✓ 在庫回転率を定期的に測定していますか?
- 物流コスト比率:売上対比でのKPI管理
- ✓ 売上に対する物流費率を把握していますか?
- 契約条件:為替変動や燃料サーチャージのリスク対策
- ✓ 契約条件を毎年点検していますか?
- システム活用度:属人化を減らし、情報を共有化する
- ✓ 輸送・在庫データが部門間で共有されていますか?
政府が進める「デジタル強靱化」の方針とも一致し、これらを実践する企業こそが変化に強くなります。各項目を自社で点検し、課題を整理することで、投資すべき領域や改善優先度が明確になります。

「5項目セルフチェックリスト(PDF)」を設置し、読者が自社の課題を把握できるようにすると効果的です。
まとめ|柔軟性と設計力が、これからの国際物流を動かす
効率化の時代は終わり、これからは「構造設計の時代」です。柔軟性、見える化、協働体制を組み合わせることで、変化に強い経営基盤を築くことができます。
今すぐ取り組むべき3つの行動は以下の通りです。
- 自社の現状を「見える化」する
- コスト構造を“固定費”から“変動設計”へ転換する
- 経営層と現場が同じデータで判断できる体制をつくる
この3つを実行することが、持続的な利益を生み出す第一歩です。本記事で紹介した考え方をさらに深めたい方は、以下の関連記事で実務事例やチェックリストを確認してください。
関連リンク
- ▶ 国際輸送コース第11回:国際輸送の全体像と最終チェックリスト
- ▶ 高市政権で変わる貿易実務(https://hunade.com/trade-2025-roadmap)
- ▶ 参考資料:フレートマンロジックス株式会社 山田俊哉氏:関通×フレートマンロジックス共催ウェビナーの資料より

 お気に入りから削除登録済の記事を確認
お気に入りから削除登録済の記事を確認
基幹記事
貿易学習コースの一覧
分野別記事
カテゴリの一覧
関連記事
◆スポンサード広告


 目次
目次